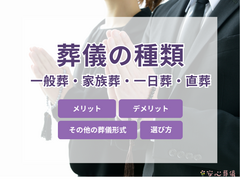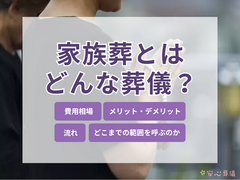直葬とはどんなお葬式?流れや費用、メリット・デメリットを解説

近年、通夜や告別式を行わない「直葬」での葬儀が増えています。
非常に質素な葬儀形式の直葬には、さまざまなメリットがありますが、後々のトラブルにつながるデメリットも少なくありません。この記事で、直葬の流れやメリット・デメリット、掛かる費用や注意点を知っておきましょう。



直葬とはどんなお葬式?
直葬は、逝去後に一定期間遺体を安置した後に火葬場へ移送し、荼毘に付す葬儀手法です。
また、直葬は葬儀業界では「ちょくそう」と読み方をするのが一般的ですが、「じきそう」と読む人もいます。
直葬の増加にともなって、近年はバリエーションを増やし、「火葬式」「お別れ式」等の名称で、花を追加したり、納棺の儀式を含めたグレードアッププランを提案している葬儀社が増えています。
一般葬と直葬の違い
| 項目 | 一般葬 | 直葬 |
| お通夜 | あり | なし |
| 告別式 | あり | なし |
| 所要時間・日程 | 2日 1日目通夜・2日目告別式と火葬 | 1日 火葬 |
| 参列者 | 30人以上 | 10人以下 |
| 費用目安 | 130万円~150万円 | 20万円~50万円 |
一般葬は1日目に通夜を執り行い、2日目に葬儀・告別式を行った後、出棺・火葬という流れになります。
直葬では通夜や告別式といった世間的な式典は行いません。また、一般葬は2日かけて葬儀を行うのに対し、直葬は1日で完了します。
直葬は、通夜や告別式を行わず、参列者も少ないため、費用が抑えられるのも特徴です。
直葬の流れ
一般葬はお通夜や告別式、火葬など、2日間かけて行います。一方で直葬は、お通夜や告別式は行わず、1日で葬儀を終えます。
ただし、死後24時間以内に火葬することは法律で禁じられているため、24時間の安置期間が必要です。
具体的な直葬の流れは、以下の通りです。
臨終・お迎え・安置
臨終後24時間は火葬できないため、ご遺体を迎えに行き、安置所へ搬送します。
自宅に安置できる場合は自宅へ、自宅が難しい場合は葬儀社の安置所へ搬送します。安置したら、葬儀社の担当者と打ち合わせをして、直葬の準備を進めましょう。
納棺
納棺の際は、故人に仏衣を着せて、故人の好きだったものを一緒に棺に入れます。
副葬品は、不燃物が不可の場合もあるため、事前に確認してください。
火葬
火葬の前に、火葬炉の前で僧侶にお経を読んでもらいます。
火葬が終わるまで1時間ほどかかるため、ご遺族は控室で待機します。
骨上げ
骨上げは、火葬後に遺骨を骨壺へ納める工程です。
2人1組で遺骨を挟み、骨壺へ納めます。血縁の濃い順に骨上げを行い、足側から拾い始め、最後に咽仏を納めて完了します。



直葬のメリット
直葬は費用が安く抑えられるほか、身体的な負担が少ないというメリットがあります。ここでは、直葬のメリットについて具体的に見ていきましょう。
直葬は他の葬儀と比べて費用が安い
直葬は、お通夜や告別式などを行わない最小限の葬儀であるため、他の葬儀形式より費用が安いのがメリットです。
一般葬の費用相場は130万円~150万円ほどが相場であるのに対し、直葬の費用相場は20万円~50万円ほどです。
直葬にかかる費用については「直葬にかかる費用はどのくらい?」でも詳しく解説します。
遺族の身体的負担が少なく済む
直葬は、ご遺族の身体的負担が少ないのもメリットです。
一般葬では、香典返しをしたり、葬儀の手伝いをしてくれた人への挨拶回りをしたりと、葬儀の後もしばらくは体が休まりません。直葬は、香典返しや挨拶回りも最小限の対応で済むため、体への負担が少ないでしょう。
直葬のデメリット|後悔するって本当?
直葬は費用が安く抑えられる葬儀方法であるものの、デメリットもあります。後で後悔しないように、デメリットも確認しておきましょう。
葬儀が終わった後の弔問が負担になる場合もある
直葬は、多くの場合限られた身内だけで行います。
そのため、直葬後はしばらく、自宅に弔問客が訪れます。電話やメール、SNS等でお悔みメッセージが頻繁にある場合や、弔問客の訪問がある場合、遺族の負担になってしまうでしょう。
親族や参列希望者から理解を得づらい場合がある
直葬は、親族や参列希望者から反対される場合もあります。親族との関係性が悪くなってしまうこともあるため、事前に直葬をする理由を説明して納得してもらうとよいでしょう。
なお、どうしても納得してもらえない場合は「故人の希望であること」を理由にすると、理解を得やすいでしょう。
菩提寺に納骨を断られる可能性がある
火葬の後は、菩提寺に納骨するのが一般的です。
しかし、直葬では宗教的儀式を行わず火葬するため、菩提寺への納骨を断られる可能性があります。葬儀をしないからといって、法要を簡略化できるわけではありません。四十九日法要時に戒名(法要)をいただいたり、納骨時には納骨法要を行います。四十九日法要時に戒名(法名)をいただいたり、納骨時には納骨法要を行います。事前に菩提寺に相談し、理解を得ておくことが必要です。



直葬にかかる費用はどのくらい?
直葬は、一般葬に比べると費用を大幅に抑えられます。
地域にもよりますが、かかる費用は葬儀だけで10万円~30万円程度と言われています。一般葬(会葬者30〜100人くらいとして)にかかる葬儀費用は130万円~150万円と言われているので、かなりの節約です。
また、これらにお布施などを勘案すれば葬儀総額の見当もつけられます。ただ、直葬でも節約できない費用があります。たとえば以下のようなものです。
- 遺体の搬送料(病院から安置施設への「遺体搬送」、安置施設から火葬場への「霊柩搬送」)
- 安置・保管施設の使用料(日数分)
- 遺体の保冷用ドライアイス(日数分)
- 棺、収骨容器代
- 火葬場費用(火葬料・休憩室使用料など)
- お別れ用の生花代など少々
直葬の料金を調べる場合の注意点
直葬にかかる費用を、さまざまな葬儀社がホームページに掲載しています。ただ、料金の中にどんな項目が含まれているかは、葬儀社によって異なります。
葬儀社を「安いから」という理由で選ぶと、後から「公表している料金には火葬料金が含まれていなかった」「設備人件費などが別料金だった」などで、トラブルになるケースもあります。
葬儀社に依頼する場合は、必要なサービスが料金に含まれているのか、事前に確認しましょう。
また、遺族の希望によって追加費用がかさんでしまうこともあります。「遺影写真の制作」や「火葬後の『後飾り段』の設置」などの要望があれば、費用は大きく変わってきます。
この他、火葬場に僧侶などの宗教者を呼ぶ場合は、その謝礼も必要になります。宗教者への謝礼は、読経やお祈りの「時間の長短」で推し量るものではありません。事前に聞いておくことも必要です。
家族葬の費用を比べるなら「安心葬儀」がおすすめ
「安心葬儀」は、全国で厳選された7,000の葬儀社から、ご予算に合わせたプランをご提案いたします。
直葬の最安値プランは8.6万円からご用意しており、サービス内容なども含めて比較いただけます。費用を抑えた直葬ができる葬儀会社を見つけるなら、「安心葬儀」がおすすめです。
直葬でよくあるトラブルと防止策
直葬でトラブルを回避するには、よくあるトラブルを知り、事前に防止策を施すことが大切です。ここでは、よくあるトラブルとその防止策を紹介します。
費用が思ったよりも高額だった
直葬では、思ったよりも費用が高額だったというトラブルがよくあります。
トラブルを防ぐには、事前に費用を確認することが大切です。直葬は他の葬儀方法よりも費用が抑えられるものの、手配方法により費用が異なります。
遺族が直接手配するのが最も安い方法ですが、手間がかかります。葬儀社へ依頼すると割高ですが、手間をかけずに葬儀の手配ができるのがメリットです。
手配の手間と金銭的負担を総合的に判断し、手配方法を選んでください。
葬儀の方法について親族ともめた
直葬では、葬儀方法について親族ともめるのもよくあるトラブルです。トラブルを防ぐには、事前に親族の了承を得ることが大切です。直葬にする理由や形式、流れを真摯に説明すれば、理解を得られるかもしれません。
特に、宗教的儀式やしきたりを大切にする方は、直葬に不満を持つ可能性が高くなります。
故人の意向であることや納骨場所など、反対理由となるポイントをしっかり説明し、理解を得られるよう尽力してください。
故人の知人・友人から非難された
故人の知人・友人から非難されるのも、直葬で起こりやすいトラブルです。
トラブルを避けるには、事前に直葬にすることを案内状で知らせておきましょう。近親者のみで行うことや、弔問に来てほしい時期、直葬は故人の意思であることを案内状に盛り込んでおけば、故人の友人・知人の気分を害する可能性も少なくなります。
菩提寺とトラブルになった
菩提寺とのトラブルを防ぐには、直葬前に菩提寺に相談しましょう。
菩提寺に無断で直葬を行い納骨をお願いすると、拒否されることがあります。事前に相談し、火葬前の読経など何らかの形で直葬に関わってもらうことで、菩提寺との関係を良好に保ち、納骨もお願いできるでしょう。法要が省略できるわけではないので、四十九日法要などで戒名(法名)をいただいたり、納骨時には納骨法要を行います。



直葬の葬儀社選びで注意すべきポイント
直葬の葬儀社選びでは、次のポイントに注意しましょう。
- 安置方法を提案してくれる葬儀社を選ぶ
- 事前に遺体との面会がどのくらいできるのかを確認する
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
安置方法を提案してくれる葬儀社を選ぶ
直葬はセレモニーを省略する分、火葬までの時間と空間をどのように過ごしたかが大切なポイントとなります。
自社の葬儀会館の安置は葬儀社にとって効率的なオペレーションができますので、「自社ホールへの誘導を進めますが、自宅での安置ができないわけではありません。近年は介護施設でご安置するケースもあります。
安置方法について最良の方法を提案してくれる葬儀社が良いでしょう。
事前に遺体との面会がどのくらいできるのかを確認する
直葬は、通常ご遺体との面会時間が長く、故人とゆっくりお別れできます。
しかし、安置場所によっては面会時間が制限されているため、どれぐらい面会できるか事前に確認しておきましょう。個別安置で面会が自由にできる安置室だと、費用も高くなります。また、火葬場では、スペースの関係で炉前でゆっくりお別れできないこともあります。
火葬場で時間が取れないようなら、火葬場へ移送する前にお別れの時間を取る必要があるでしょう。
直葬の葬儀社選びなら「安心葬儀」を活用しよう
「安心葬儀」は、直葬のプランを用意する葬儀社の中から、予算やサービスを比較して適切なプランをお選びいただけます。
直葬は最安プランで8.6万円からご提案しており、葬儀に関する情報も提供いたします。直葬をお考えの方はぜひご活用ください。
直葬に参列する場合のマナー
直葬はお通夜や告別式は行わないものの、葬儀であることに変わりはありません。一般的な葬儀のマナーに沿って参列する必要があります。
ここでは、直葬に参列する際のマナーをチェックしましょう。
服装
直葬に参列する際の服装は、男性は喪服もしくはブラックスーツを着用するのがマナーです。シャツは白で、黒いネクタイを付けるのが基本です。
女性は、ブラックフォーマルを着用するのがマナーで、光沢のある素材は避けてください。アクセサリーは結婚指輪以外は着用しないのが無難です。
香典
直葬は、身内だけの参列も多いため、香典が持参されないこともあります。事前に香典辞退の意向を伝えられている場合、持参する必要はありません。
また、香典を渡す場合は、受付などもないので、遺族に直接渡してください。



まとめ
直葬は、通夜や告別式を行わない火葬のみの葬儀です。最小限の遺体対応のみであるため、費用も一般的なお葬式より大幅に安くなります。遺族の精神的・身体的な負担も軽減できます。
しかし直葬では、参列できなかった故人と親しかった人への配慮(弔問・会葬対応)も必要ですし、葬儀費用の内訳についても、「多分安いであろう」という即断ではなく、事前に確認しておかないと後々のトラブルに発展することもあるので注意してください。
葬儀費用を抑えたい、シンプルな葬儀にしたいという人には、直葬が向いていますが、後悔しないためにも、メリットとデメリットをよく知っておきましょう。



葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。 時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社に...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。ギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。ギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。