家族や身内が亡くなったらすること|亡くなった時から四十九日までの流れを解説

身近な人が亡くなり、自分が葬儀の準備や手続きを進める立場になった際、突然のことで慌ててしまったり、経験不足で何をすればよいのか分からないという状態になるかもしれません。
やることがたくさんあるため混乱してしまうかもしれませんが、期限のあるもの、タイミングが大事なことも多く、効率良く対応することが大切です。
この記事では、万一のときに備えて、亡くなったらすることを時系列にまとめました。



家族や身内が亡くなったらまずすることとは?
家族や身内が亡くなったときにまずすることは、以下のとおりです。
【家族や身内が亡くなったらまずすることリスト】
- 死亡診断書・死体検案書を発行してもらう
- 「死亡届」の提出および「火葬許可申請」の手続き
- 家族や親戚に連絡する
- 葬儀社を決める
- 遺体の搬送や退院手続き
- 葬儀日程や内容を決定する
- 知人や近隣に連絡する
以下では、それぞれの手続きや対応について詳しく説明します。
死亡診断書・死体検案書を発行してもらう
近親者が亡くなったら、医師に死亡診断書を発行してもらいます。病院で亡くなった場合は、主治医や臨終に立ち会った医師に作成してもらうことになります。
治療中の病気が原因となって自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に作成してもらいます。ただし、特に持病もなく亡くなってしまって原因がよく分からないときは、遺体には手を触れずにすぐに警察に連絡してください。
こうした場合は、死亡診断書ではなく、検視や検案、必要があれば解剖を受けて死体検案書を作成してもらう必要があります。
死亡診断書や死体検案書は、人が亡くなった際に必要となる書類の一つです。死亡したことを証明する大切な書類で、死亡診断書を作成できるのは、医師や歯科医師に限られます。
死亡診断書がないと死亡届の手続きができず、火葬許可証の交付も受けられないため、火葬や埋葬を行うことができません。
死亡診断書は役所への死亡届の提出や保険金の請求の際に必要となります。保険会社が複数になるとその数だけ必要になります。死亡診断書は死亡届と一体になっていて、一度役所へ提出すると返却されることはないので、複数のコピーを必ず取っておくようにしましょう。
「死亡届」の提出および「火葬許可申請」の手続き
「死亡届」は、死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場に提出することが義務付けられています。国外で亡くなった場合、期限は3カ月以内です。
死亡届は死亡診断書と同じ用紙になっています。必要事項を記入して提出してください。提出できるのは、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の居住地のいずれかの役所です。原則として提出は24時間可能です。
なお、届出については同居の親族のほか、その他の同居者、亡くなった場所である家屋または土地の所有者(家主、地主)、もしくは家屋管理人、土地管理人に届出義務があります。また、 亡くなった方の同居していない親族や後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者がその資格を証明する登記事項証明書などの謄本を添付して届出をすることができます。
役所への届出については、葬儀社が使者として代行してくれます。死亡届の提出時には、「火葬許可申請」も同時に行います。
火葬許可証は、自治体によっては埋火葬許可証や火葬(埋葬)許可証などと呼ばれます。火葬許可証がないと火葬や埋葬ができないので、自身で行う際は忘れずに一緒に手続きを行いましょう。
また死亡届と埋火葬許可申請は、葬儀前に行っておくことが一般的です。
家族や親戚に連絡する
故人と関係のある方への連絡も亡くなった当日に、できるだけ速やかに行うべきです。
葬儀の日取りや会場も決まっていないことがほとんどですが、とりわけ離れた土地に住んでいる親戚や家族、病気治療中だったことを知らない人には、できるだけ早く亡くなった旨を伝えるようにしてください。
その他の親族や友人関係、職場などへは、葬儀の日程や場所などが決まってから連絡します。
関連記事

訃報の連絡方法を詳しく解説
家族を失った深い悲しみの中にいても、訃報の連絡は迅速かつ的確に行わなければなりません。 本記事では、訃報の連絡の優先順位やタイミング、連絡方法、連絡先、注意点などについて詳しく解説します。 ...
続きを読む
葬儀社を決める
家族や親戚への連絡と並行してすぐに進めなくてはならないのが、葬儀を依頼する葬儀社の決定です。選ぶ際は次の3点を基準に検討してください。
- 担当者の対応が誠実
- 見積書の内容が明確
- 希望する葬儀に対応可能かどうか
お急ぎで葬儀社をお探しでしたら当サイト「安心葬儀」の葬儀社紹介・相見積もりサービスがご利用いただけます。詳細は下記をご覧ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
遺体の搬送や退院手続き
遺体を病院に安置できるのは、数時間程度になることが普通です。このため、病院の会計を済ませて退院手続きをするとともに、遺体の安置場所に搬送する必要があります。
葬儀費用のプランに病院からの搬送費が含まれている場合もあるので、依頼する葬儀社が決まっていれば、同じ会社に搬送の手配を依頼するとよいでしょう。
葬儀の依頼先が決まっていない場合は、病院などで搬送対応の葬儀社を紹介してもらうこともあるようです。搬送代が別途掛かってはきますが、搬送のみをお願いして葬儀は別会社に依頼する、ということもできます。
自宅に安置する他、依頼する葬儀社が決まっている場合は、葬儀社の安置室を使用できるケースもあります。
葬儀日程や内容を決定する
依頼する葬儀社と打ち合わせを行って、通夜、葬儀の日程と内容を決めましょう。喪主や受付などの役割もこのときに決めます。
また、死亡診断書を担当者に渡して、次の項目で紹介している死亡届や火葬許可証の手続きを依頼することも可能です。
葬儀の日程の決め方についてはこちらの記事でも解説しています。
関連記事

葬儀の日程の決め方は?行なえない日はある?
自分が喪主の立場になった場合、葬儀の大まかな流れは知っていても、実際に日程を決めるとなると何を考慮したらいいのか分からない方が多いのではないでしょうか。 本記事では、葬儀の日程の決め方やその際...
続きを読む
知人や近隣に連絡する
葬儀スタイル、通夜、葬儀の日程、会場が決定したら、そのスタイルに合わせた範囲で、親族、知人や友人、仕事関係、近隣などへ連絡してください。
葬儀を執り行う
葬儀では、通夜や告別式が行われます。 まず通夜が行われ、その翌日に告別式が行われるのが一般的な流れです。
また、告別式の後は出棺・火葬が行われ、火葬後には遺骨を骨壷に収める「骨上げ」を行うといった流れになります。
なお、最近では葬儀と同じ日に七日法要を開催する「繰り上げ法要」が多い傾向にあります。
七日法要は本来、故人がなくなった日から7日目に行うのが通常ですが、遺族の高齢化や親戚が遠方に住んでいることなどを配慮し、葬儀当日にあわせて行うことも増えているのです。
繰り上げ法要には、遺族や親族が何度も集まる必要がなく、負担軽減や日程調整がしやすいといったメリットがあります。
葬儀費用の支払いや香典返しの手配
香典返しとは、葬儀や法要で受け取った香典のお礼として贈る品物のことで、お菓子やコーヒー、調味料、洗剤などの「消え物」が好まれます。
また、金券やカタログギフトなど参列者が自身で選ぶことのできるものでもよいでしょう。
贈る品物は受け取った香典の半額程度のものをお返しする「半返し」が一般的です。
なお、香典返しの準備は葬儀社に依頼すれば、代行してもらえることもあります。
金額に応じた品物の提案をしてくれるほか、のし・挨拶状の準備や配送手配まで一括で代行してくれるので、何を準備したらいいかわからない場合は相談してみましょう。
家族や身内が亡くなった時に必要な公的手続き
家族や身内が亡くなった時に必要な公的手続きは、以下のとおりです。
【家族や身内が亡くなった時に必要な公的手続きリスト】
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の提出
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 厚生年金の受給停止
- 国民健康保険の資格喪失届の提出
- 後期高齢者医療の資格喪失届の提出
- 介護保険の資格喪失届の提出
- 国民年金の受給停止
- 住民票の世帯主変更届、児童扶養手当認定請求
- 復氏届の提出
- 姻族関係終了届の提出
- シルバーパスの返却
- 高齢者福祉サービス
- 身体障がい者手帳や愛の手帳の返却
家族や身内が亡くなった時に必要な公的手続きには、期限が定められているものもあります。期限に遅れてしまうと、余計な手続きや罰金が課される可能性もあるので、迅速に対応することが必要です。
それぞれの手続きについて、以下で詳しく解説します。
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の提出(資格を喪失した日から5日以内)
健康保険・厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、資格喪失届の提出が必要です。 提出期限は資格を喪失した日から5日です。なお、故人が厚生年金加入者の場合は、会社が手続きを行います。
会社から健康保険証の返却を依頼される場合があるので、速やかに返却をしましょう。
雇用保険受給資格者証の返還(死亡から1カ月以内)
雇用保険の受給資格者が死亡した場合、「雇用保険受給資格者証」をハローワークに返却する必要があります。手続きの期限は死亡から1カ月以内です。
厚生年金の受給停止(死亡から10日以内)
厚生年金の受給者が死亡した場合、受給停止手続きを行う必要があります。
手続きの期限は死亡から10日以内です。年金事務所に書類を持ち込むか、郵送で送ることで申請できます。
なお、未受給の年金は遺族が受け取るよう手続きすることも可能です。
国民健康保険の資格喪失届の提出(死亡から14日以内)
国民健康保険の加入者が死亡した場合、資格喪失届を提出する必要があります。
手続きの期限は死亡から14日以内で、市区町村役場の担当部署に提出します。
後期高齢者医療の資格喪失届の提出(死亡から14日以内)
後期高齢者医療制度の加入者が死亡した場合、資格喪失届を提出する必要があります。
手続きの期限は死亡から14日以内で、市区町村役場の担当部署に提出します。
介護保険の資格喪失届の提出(死亡から14日以内)
介護保険の加入者が死亡した場合、資格喪失届の提出が必要です。また、未使用の保険証も返却する必要があります。
手続きの期限は死亡から14日以内で、市区町村役場の担当部署に提出します。
国民年金の受給停止(死亡から14日以内)
国民年金の受給者が死亡した場合、受給停止の手続きが必要になります。
手続きの期限は死亡から14日以内で、市区町村役場の担当部署に提出します。
なお、未受給の年金は遺族が受け取るよう手続きすることも可能です。
住民票の世帯主変更届、児童扶養手当認定請求(死亡日から14日以内)
世帯主が死亡した場合、世帯主変更の届出を市区町村役場の担当部署に提出します。
また、児童扶養手当を受ける場合は、死亡から14日以内に認定請求を行う必要があります。
復氏届(期限なし)
婚姻時に配偶者の姓を名乗っていた人が、配偶者の死亡後に元の姓に戻す場合、復氏届を市町村役場の担当部署に提出する必要があります。期限は特に設けられていません。
復氏届を提出すると死亡した配偶者の戸籍から抜け、新たに戸籍を作るか、結婚前の戸籍に戻るか選ぶことができます。
姻族関係終了届(期限なし)
配偶者が死亡した後、姻族関係を終了させる場合は姻族関係終了届を市町村役場の担当部署に提出する必要があります。期限は特に設けられていません。
姻族関係終了届が受理されると、配偶者の両親(義父母)や兄弟姉妹(義兄弟姉妹)などの親族との関係を法律的に解消することができます。なお、子どもとの親族関係には影響しません。
シルバーパスの返却(速やかに)
シルバーパスの使用者が死亡した場合、シルバーパスを返却する必要があります。
返却先は市区町村の窓口や担当部署です。期限は設けられていませんが、速やかに返却することが推奨されています。
高齢者福祉サービス(速やかに)
高齢者向けの福祉サービスを受けていた人が死亡した場合、利用していたサービスを停止する必要があります。
なお、手続きの期限は利用サービスによって異なります。トラブルを避けるため、速やかに手続きを行うとよいでしょう。
身体障がい者手帳や愛の手帳の返却(速やかに)
身体障がい者手帳や愛の手帳の所有者が死亡した場合、手帳を返却する必要があります。
返却先は市町村役場の担当部署です。期限は定められていませんが、できるだけ速やかに返却しましょう。



家族や身内が亡くなった時に必要な公共サービスに関する手続き
家族や身内が亡くなった時に必要な公共サービスに関する手続きは、以下のとおりです。
【家族や身内が亡くなった時に必要な公共サービスに関する手続きリスト】
- 電話の継承または解約
- 運転免許証の返納
- 賃貸住宅の解約または名義変更
- 子の氏変更許可申請
- 死亡退職届、死亡退職金・最終給与の受け取り
それぞれの手続きについて、以下で詳しく解説していきます。
電気、ガス、水道、NHK、インターネットなどの名義変更または利用停止(期限なし)
各サービスの名義変更や利用停止の手続きは、カスタマーセンターやホームページから行います。
名義変更を行う場合は、故人の死亡届や戸籍謄本が必要になる場合もあるので、事前に準備しましょう。
なお、手続きの期限は法律上定められていませんが、引き落とし時のトラブルを避けるために速やかに行うのが望ましいとされています。
電話の承継または解約(期限なし)
固定電話の承継や携帯電話の解約の手続きは、通信事業者に連絡して行います。
手続きの期限は定められていませんが、契約者が死亡した場合、自動的に契約が解除される場合もあります。電話を承継する場合は速やかに手続きを行いましょう。
運転免許証の返納(期限なし)
運転免許証の返納の手続きは、警察署や運転免許センターで行います。手続きには、死亡証明書と戸籍謄本が必要になるので、事前に準備しましょう。
期限は定められていませんが、速やかに返納することが推奨されています。
賃貸住宅の解約または名義変更(期限は賃貸契約による)
故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、契約の解除または名義変更を行う必要があります。
手続きは不動産会社や大家に連絡して行いますが、死亡証明書や戸籍謄本が必要になる場合もあるので、事前に準備しましょう。
期限は契約内容によって異なりますが、基本的に契約書に記載の退去予告期間に従うことになります。
一般的には、退去の1カ月前までに手続きを行うことが求められるケースが多いです。
子の氏変更許可申請(死亡から1年以内)
子の氏の変更許可申請は、家庭裁判所に申請して行う必要があります。
申請書には戸籍謄本や死亡届、申立人の住民票を添付します。また、追加書類が必要になる場合もあるので、事前に家庭裁判所に問い合わせておきましょう。
手続きの期限は、死亡から1年以内です。期限を超過すると手続きができなく可能性がありるので、早めの対応を心がけましょう。
死亡退職届、死亡退職金・最終給与の受け取り(死亡から5年以内)
勤務先へは、死亡通知書を送付して死亡退職届・社員証を提出します。
退職金や最終給与の受け取りには死亡証明書や、相続を証明する書類が必要になるので事前に準備しましょう。
退職金や最終給与を遺族が請求できる期間は5年と定められており、期限を過ぎると時効が成立するので、請求できなくなる可能性があります。早めの対応を心がけましょう。
家族や身内が亡くなった時に必要な相続・お金に関する手続き
家族や身内が亡くなった時に必要な相続・お金に関する手続きは、以下のとおりです。
【家族や身内が亡くなった時に必要な相続・お金に関する手続き】
- 相続手続き
- 埋葬料の請求
- 遺族年金の受給申請
- 所得税準確定申告・納税
- 不動産の名義変更登記
- 相続税の申告
- 高額医療費の請求
- 生命保険金の請求
- 預金、株式等の名義変更
- クレジットカードの解約
期限が決まっているものが多いほか、速やかな手続きを求められることもあるのでしっかりと確認しましょう。
それぞれの手続きについて、詳しく解説します。
相続手続き(一部期限あり)
まずは、相続手続きのために法定相続人と相続財産を確定します。
法定相続人は、戸籍謄本や住民票を使って確認します。行方不明や音信不通の親族がいる場合は、弁護士などに依頼して相続人調査を行ってもらうのもよいでしょう。
相続財産は、被相続人が所持していた預金・不動産・車などのプラスの財産から、借金やローンなどのマイナスの財産まで調べます。相続財産の調査が漏れていると、後々相続人間でトラブルになる可能性もあるので、必要に応じて専門家のサポートを得ましょう。
次に、相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」が必要です。遺産分割協議では、遺産の分割方法などについて相続人全員が同意することが必須ですが、折り合いがつかず家庭裁判所に調停や審判を求めるケースもあります。
特に、遺言書で一部の相続人や相続人以外の人への相続が指定されている場合はトラブルになりやすいので、事前に弁護士に相談するなどしておくとよいでしょう。
なお、遺言書がある場合は遺言書の内容に従って相続手続きが進められますが、遺言書がない場合は法定相続に則って分割されます。
また、相続放棄や限定承認をする場合は、亡くなった方の相続人と知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
埋葬料の請求(2年以内)
埋葬料の請求は、申請期限は葬儀を執り行った翌日から2年以内に行う必要があります。
故人が加入していた健康保険組合または社会保険事務所に対して申請します。埋葬にかかった費用がわかる書類や死亡診断書が必要になるので、事前に準備しましょう。
遺族年金の受給申請(原則亡くなった日の翌日から5年以内)
遺族年金の受給申請は、亡くなった翌日から5年以内に行う必要があります。
まず市区町村に死亡届を提出し、その後年金事務所に遺族年金の申請をするといった流れです。
申請には死亡診断書・戸籍謄本・住民票・請求者の収入を証明する書類などが必要になるので、事前に準備しましょう
所得税準確定申告・納税(4カ月以内)
納税者が死亡した場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をする必要があります。
申告には、源泉徴収票・医療費控除や寄付金控除などの書類・戸籍謄本・住民票が必要になるので、事前に準備しましょう。
不動産の名義変更登記
不動産の相続が決定した場合は、法務局で名義変更の申請を行います。
2024年6月以降は、不動産を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されています。期限内に手続きを行わないと、ペナルティが課せられることもあるので注意してください。
また、申請には戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・登記簿謄本が必要になるので、準備しましょう。
相続税の申告(相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内)
相続税の申告・納付は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
申告先は税務署で、財産目録・戸籍謄本・遺産分割協議書・評価証明書などが必要になります。事前に準備しましょう。
高額医療費の請求(診療を受けた月の翌月の初日から2年以内)
故人の医療費の自己負担額が高額になった場合、高額医療費の請求をすることができます。申請期限は診療を受けた月の翌月の初日から2年以内です。
申請には領収書・口座情報・故人の保険証が必要になるので、事前に準備しましょう。
生命保険金の請求(権利発生の翌日から3年以内)
生命保険金の請求は、権利発生の翌日から3年以内に行う必要があります。
請求には死亡診断書・戸籍謄本・保険証券などが必要です。保険会社によって必要書類は異なる可能性があるので、問い合わせのうえ準備しましょう。
預金、株式等の名義変更(相続確定後速やかに)
故人の預金や株式等の名義変更の手続きは、遺産分割協議が終わった後に行います。
銀行や証券会社に戸籍謄本・遺産分割協議書などを提出する必要があるので、事前に問い合わせて確認しましょう。
なお、申請期限は設けられていませんが、トラブルを避けるために相続確定後速やかに行うことが推奨されます。
クレジットカードの解約(相続確定後速やかに)
故人のクレジットカードは、相続確定後にカード会社に連絡して解約手続きを行います。
死亡証明書や戸籍謄本が必要になる場合もあるので、問い合わせて確認してください。
なお、申請期限は設けられていませんが、未払いの債務などは相続遺産から支払う必要があるため、相続確定後速やかに手続きを進めるのが望ましいでしょう。



家族や身内の葬儀後にやること
家族や身内の葬儀後には以下のようなことをやる必要があります。
- 四十九日法要を行う
- お仏壇やお墓を準備する
- 新盆法要を行う
- 一周忌法要を行う
それぞれ解説していきます。
四十九日法要を行う
仏教では成仏するまでにかかる期間が49日間とされており、その節目に行う法要が「四十九日法要」です。故人が無事に成仏できることを願い、親戚や故人と親しかった友人などが招かれます。
四十九日法要が済むと、故人の魂は浄土へ旅立つとされ、遺族は通常の生活に戻ることから「忌明け法要」とも呼ばれます。四十九日法要が済んだ後は、定められた年に追善供養の法要を行います。
開催のためには、事前に僧侶や会場の手配を行い、会食などの準備も必要です。準備する時間が取れないなど、困ったことがあれば葬儀を担当した葬儀社に相談するとよいでしょう。
また、お仏壇の準備もこの時期までに済ませておくのがおすすめです。
お仏壇やお墓を準備する
四十九日法要までに、お仏壇の準備をしておく必要があります。
仏壇は仏具店や仏壇専門店で購入します。設置スペースや宗派を考慮したうえで仏壇を選び、位牌や仏具も揃えておきましょう。
仏壇がある場合は、本位牌のみを新たに購入します。文字を入れて四十九日法要の際に「白木位牌」「本位牌」を持参し、白木位牌から本位牌に魂を移し替えてもらいます。
すでにお墓がある場合、地域によっては四十九日法要のときに納骨するケースもあります。 納骨をする場合も、墓石に刻む文字が間に合うように注文しておきましょう。
新盆法要を行う
新盆は、故人が亡くなってから初めて迎える盆のことです。 故人を迎えるために、お盆に向けて仏壇の掃除・飾りつけを行います。
また、通常より多くの親族や関係者が集まることも多いので、会食の手配や返礼品の準備が必要なケースも。
また、供養のための読経を僧侶に依頼するのが一般的なので、事前に相談しておきましょう。
一周忌法要を行う
一周忌法要は、故人が亡くなってから1年後に行う法要です。故人を偲ぶ重要な節目とされており、多くの親族や友人が集まり、僧侶を招いて読経を行うのが一般的です。
日程の調整や会場の確保は、僧侶と相談して事前に決めます。日程や会場が決まったら、親族や故人の友人などの招待状を送り、引き出物の準備をしましょう。
また、仏壇の清掃や仏具を整えることも忘れないでください。
【一覧】家族が亡くなったらすることリスト
家族がなくなったらすることを一覧でまとめました。手続きや準備に抜け漏れがないよう、ぜひ活用してください。
まずすること | □ 死亡診断書・死体検案書を発行してもらう □ 「死亡届」の提出および「火葬許可申請」の手続き □ 家族や親戚に連絡する □ 葬儀社を決める □ 遺体の搬送や退院手続き □ 葬儀日程や内容を決定する □ 知人や近隣に連絡する |
公的手続き | □ 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の提出 □ 雇用保険受給資格者証の返還 □ 厚生年金の受給停止 □ 国民健康保険の資格喪失届の提出 □ 後期高齢者医療の資格喪失届の提出 □ 介護保険の資格喪失届の提出 □ 国民年金の受給停止 □ 住民票の世帯主変更届、児童扶養手当認定請求 □ 復氏届の提出 □ 姻族関係終了届の提出 □ シルバーパスの返却 □ 高齢者福祉サービス □ 身体障がい者手帳や愛の手帳の返却 |
公共サービスに関する手続き | □ 電話の継承または解約 □ 運転免許証の返納 □ 賃貸住宅の解約または名義変更 □ 子の氏変更許可申請 □ 死亡退職届、死亡退職金・最終給与の受け取り |
相続・お金に関する手続き | □ 相続手続き □ 埋葬料の請求 □ 遺族年金の受給申請 □ 所得税準確定申告・納税 □ 不動産の名義変更登記 □ 相続税の申告 □ 高額医療費の請求 □ 生命保険金の請求 □ 預金、株式等の名義変更 □ クレジットカードの解約 |



まとめ
近親者が亡くなった際に、行わなければならないことは本当にたくさんあります。
特に役所などで行う手続きは種類が多く、期限が定められていることがほとんどなので、チェックリスト形式としました。大事な手続きを忘れたり、タイミングを逃したりしないように、備忘録として役立てください。
大切な人を失った悲しみを抱えながら、さまざまなことを処理するのは大変ですが、故人を安らかに送るためにも、心をしっかり持って対応しましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。










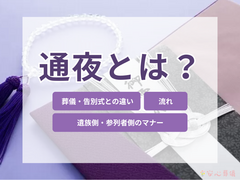
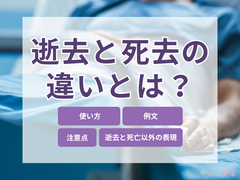
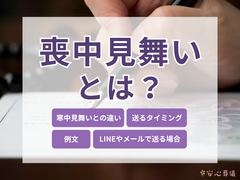
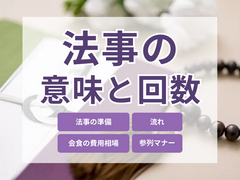
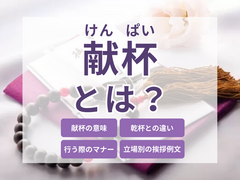
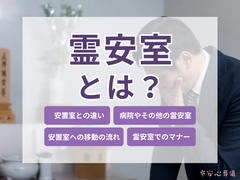
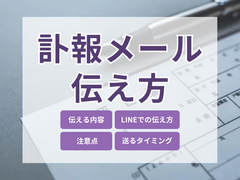

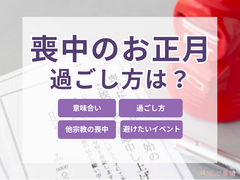
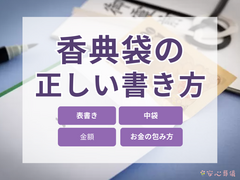
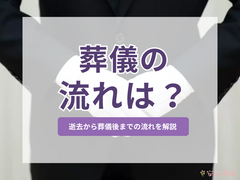

近年はセレモニーをしない火葬式を選ぶ人が増え、火葬までの間の過ごし方が大切になっています。ラストメイクで整えたり、納棺の儀をゆっくりするなど、安置の期間にポイントをおいた葬儀プランも増えています。