骨葬とは?葬儀の流れやメリット・デメリット、火葬を先に行う理由

葬儀にはさまざまなスタイルがありますが、そのうちの一つである「骨葬」というものを知っていますか?
通常の葬儀では、通夜や葬儀告別式を終えてから、火葬場へ出棺し、故人の遺体を火葬します。
骨葬と呼ばれる葬儀は、先に火葬をして、その後に葬儀告別式を執り行うスタイルです。
「火葬の後に葬儀を行う」と聞いて驚く方もいるかもしれませんが、全国を広く見渡すと、骨葬が当たり前に行われている地域も数多くあります。また、何かしらの事情があって喪主が骨葬を選択するというケースもあります。
そんな骨葬とは一体どのような流れで進んでいくのでしょうか。この記事では骨葬の意味、マナーや流れなどについて、分かりやすく紹介します。



骨葬とは
骨葬(こつそう)とは、遺体ではなく、遺骨を祭祀対象として行う葬儀式のことです。お葬式の葬儀・告別式に先立つ形で火葬を済ませます。
通常の葬儀では、祭壇の前や中に組み込む形で、故人が納められた棺を安置しますが、骨葬では祭壇の中央に遺骨を安置し、式を営みます。
全国的には通夜の翌日に葬儀・告別式が行われ、その後火葬場に赴いて荼毘に付すという地域が多数ですが、北海道、東北地方、関東、九州などの地域の一部では、地域の慣習としていまでも骨葬を行っているところもあります。特に東北地方では多く見られるようです。
「骨葬」とは言いますが、地域慣例によってさまざまで、通夜の前に火葬を行う場合もありますが、一般的な「骨葬」は、通夜は通常通り棺を前にして行い、翌日の午前中に火葬、午後に骨葬を行うという慣例が多いようです。
葬儀の前に火葬を行うことを「前火葬(まえかそう)」、葬儀の後に火葬を行うことを「後火葬(あとかそう)」と呼びます。
気になるのは参列者としてのマナーですが、参列の際の服装や香典の額は、「骨葬」の場合も一般的な葬儀とで違いはありません。
骨葬が行われる6つのケースとは?
骨葬が行われる主な6つのケースとして、次のような場合が挙げられます。
地域の風習に基づく場合
その地域で慣習となっている場合、その慣例に沿って骨葬で行います。
葬儀場所と離れた場所で亡くなった場合
遠方で亡くなった人の遺体を先に火葬をして、後日遺骨を持ち帰って葬儀をするケースが多く、こうした場合も「骨葬」になります。
例えば、地方から上京した人が都内で亡くなったとします。遺族は故人を連れ帰って、故郷で葬儀を行いたいのですが、遺体の搬送費が高額になるなどの理由のため、都内の火葬場で先に火葬するのです。
海外で亡くなった場合
海外で亡くなった場合も同様で、遺体の状態で帰国するケースもありますが、費用や法的な問題により、遺骨で帰国した後に骨葬を行う場合もあります。
感染症で亡くなった場合
エボラ出血熱、ペストなど1類感染症で亡くなった場合には、感染拡大防止の観点から死亡後24時間以内に火葬するものとされていることもあり、火葬後の葬儀が基本です。
事件や事故で亡くなるなど、遺体の損傷などが著しい場合
事件や事故で亡くなられた場合には、警察による検死や解剖所見などで遺体そのものが返却されるのに日時がかかったり、また死後経過や損傷などで、遺体で葬儀を行うのが困難な場合もあります。そういったケースでは先に火葬を行い、骨葬にします。
お別れの会や社葬などの場合
社葬・団体葬などを行う場合、本葬に先立って「密葬」という形でご遺体葬を済ませ、遺骨の状態で後日「お別れの会」「偲ぶ会」と称する社葬・団体葬が行われることがあります。
また、芸能人などの著名な方が亡くなられた場合は、報道による混乱を避けるため、まずは親族のみで密葬を執り行い、その後、ある程度の期間を置いてから、故人の友人・関係者・ファンなどに向けた「お別れの会」や「偲ぶ会」が広く開催されます。この際は、骨葬の形式がとられることが多いです。
このように、著名人の場合は私的な「送る儀式」と公的な「偲ぶ儀式」を分けて執り行うことで、両方の意義を大切にした葬儀を実現しています。



骨葬の流れとは
一般的な骨葬の流れは、以下の通りです。
- 臨終
- 安置
- 打ち合わせ
- 納棺
- 通夜式
- 火葬
- 葬儀告別式
- 精進落とし
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
臨終
医師の死亡確認を受け、死亡診断書を受け取ったら、速やかに病院などの施設から遺体を自宅や葬儀社などの安置先へ搬送しなければなりません。
葬儀社を事前に決めている場合は、速やかに連絡をして、遺体の搬送を手配しましょう。
葬儀社を事前に決めていなかった場合は、速やかに葬儀社を決めて搬送を手配する必要があります。または、病院から紹介される葬儀社に搬送のみを任せることも可能です。
なお、病院で亡くなった場合、霊安室に安置しておく時間は3時間〜24時間以内が理想的とされています。
安置
安置・保管先は、自宅や病院の霊安室になります。
霊安室では気にする必要はありませんが、自宅保管の場合はエアコンや保冷剤・ドライアイスなどによる温度管理が必要になります。
また、遺体に損傷が見られる場合は、エンバーミングなどによる防腐処置や復顔施術が行われることもあります。
安置後、仏式であれば枕飾りの祭壇を飾り、集まっている家族や親族で線香を手向けることもあります。このタイミングで、今後の葬儀の進め方について家族で話し合いを始めるとよいでしょう。
打ち合わせ
葬儀社のスタッフと共に、骨葬の具体的な内容を決めていきます。
主な検討項目は、骨葬を行う場所・日程・宗派・参列予定人数です。
また、祭壇や棺などの葬祭用品を選ぶほか料理の内容や返礼品の種類なども決めていきます。
この段階で予算についても明確にし、無理のない範囲で執り行えるよう調整しておくと良いでしょう。
納棺
納棺式は家族や親族などの身内だけで行われます。
湯灌で故人の身体を丁寧に清め、死装束に着替えて旅支度を整えます。位牌に戒名を書き入れ、思い出の品や手紙などと一緒に、丁寧に棺に納めます。
場合によっては、納棺した後すぐに火葬を行い、通夜からお骨での対応となることもあります。(ただし、通常は死後24時間以内は火葬できません)。
通夜式
僧侶による読経が行われ、その後参列者が順番に焼香を行うのが一般的な流れです。
また、式の後には「通夜振る舞い」と呼ばれる会食の時間が設けられます。参列者への感謝の意を表すとともに、故人を偲ぶ機会ともなります。
火葬
通夜の翌日、家族や親族を中心に近しい人が集まり、僧侶の読経や参列者の焼香がなされた後、棺の蓋を開けてお花を入れるなど、お別れの儀を行います。
その後、ご遺体を霊柩車に棺を乗せて火葬場へと出棺します。
火葬時間は地方によってさまざまですが、炉前で再びお別れや焼香をすることもあり、通常は1〜2時間ほどかかると思っておきましょう。
拾骨も地域慣習などに基づいて行われますが、一般的には、火葬後はご遺族によって骨上げを行い、骨壺に収めて持ち帰ります。
なお、通夜を行わない一日葬の形式で骨葬を行う場合は、葬儀告別式の前日や当日の朝に火葬を行うのが一般的です。
葬儀告別式
火葬が終わると、火葬場から葬儀・告別式を行う会場に移動します。会場では、遺骨は祭壇中央に安置されます。
葬儀・告別式では、僧侶の読経に続いて、参列者が順次焼香を行います。式中に弔辞や弔電などの奉読をすることもあります。
最後は、喪主・遺族による会葬御礼の挨拶が行われて閉式です。
なお、告別式では参列者への案内や接待も重要な要素となるため、会葬礼状や香典返しなどの準備も怠りなく行う必要があります。
精進落とし
葬儀告別式後は、本来忌明けに行われる精進落としを葬儀の慰労を兼ねて執り行います。
精進落としは、参列者との会食を通じて故人を偲びながら感謝の意を伝える機会となります。
精進落としの場では、これまでの労をねぎらう「献杯」とともに、今後の法要などについても話し合われることが多いです。
骨葬のメリットは?火葬を先に行う理由
故人や参列者に失礼がないように、また遺族として納得のできる葬儀を行うためにも、骨葬のメリットとデメリットの両面を把握しておくことが大切です。
ご遺体の状態を気にせずに済む
通常の葬儀では、お棺の中のご遺体の状態を維持するためにさまざまな配慮や対応が必要となります。しかし、骨葬では先に火葬を済ませてしまうため、ご遺体の状態を気にせずに葬儀を執り行えます。
特に、事件や事故による損傷がある場合や、病気の治療で外見に大きな変化がある場合は、火葬を先に済ませておくことで参列者の精神的な負担を軽減することが可能です。
また、気温の高い時期の葬儀では温度管理に特に気を使いますが、先に火葬を済ませておけば、ご遺体の状態が悪化することを気にしなくて良くなります。
火葬を先に済ませることで、ご遺体の保管や管理に関する心配ごとが減るので、遺族は葬儀の準備に専念することが可能です。
また、生前のイメージと異なるご遺体と対面しないことで「元気だった頃の思い出とともに故人を偲ぶことができた」という声もあります。
長距離寝台車代などの費用負担を軽減できる
先に火葬を済ませて遺骨を持ち帰り「骨葬」することで、寝台車などの搬送料金の削減ができます。
特に、家族が遠隔地で死亡した場合などで長距離の搬送が必要になると、寝台車代だけで数十万円の費用がかかることも珍しくありません。
また、航空機での移動の場合、ご遺体は貨物室に入りますが、遺骨の場合は機内(客室)に一緒に手荷物として搭乗することができます。費用面でも航空機での搬送費用が軽減できます。



骨葬のデメリットと注意点
骨葬は、一般的な葬儀とは異なる流れで執り行われます。
骨葬について詳しく知らない参列者や関係者もいるので、通常の葬儀形式とは異なる配慮が必要になるでしょう。
このように、骨葬にはいくつかのデメリットや注意点があります。それぞれのデメリットについて、以下で詳しく見ていきましょう。
故人と最期に対面できない方が出てくる
骨葬を選択した場合、火葬は身内のみで執り行われるのが一般的です。
そのため、親戚や故人と親しかった方々に対して故人との最期の対面の時間を設けられないケースがあります。
遠方に住む親族や、仕事の都合ですぐに駆けつけられない方にとって、故人との最後の別れの機会を逃してしまうことは、大きな心残りとなる可能性があります。
実際に、「最期にお顔を見ることができなかった」という悔恨の言葉を聞くこともあるので配慮が必要です。
訃報連絡の際には、事前に火葬の日時や「骨葬」であることを伝えて理解してもらえるようにしましょう。また、火葬前に対面ができない場合も、その旨を丁寧に説明する必要があります。
骨葬に参列する場合のマナー
上でも少し触れていますが、骨葬であっても、参列時のマナーは一般的な葬儀と変わりありません。
ただし、一般的なマナー以外で気を付けたい点があります。それは、遺族に対して「なぜ骨葬で行うのか」と露骨に尋ねるのは避けることです。
なぜなら、感染症や事故などが原因となり、遺族の希望ではなく、やむを得ず骨葬を選択するケースもあるからです。骨葬の理由を尋ねることが死因を詮索することにつながって、遺族の心情を傷付けてしまうこともあります。
関連記事

葬儀に参列する際のマナーとは?服装や香典に数珠などの基本も紹介します
お葬式には、さまざまなマナーが存在します。亡き人を偲び、遺された家族と悲しみを分かち合うという同じ目的のために、たくさんの人々が式場に集います。だからこそ、そこでは個性の表現を慎み、周りの人と同...
続きを読む



最後に
今回は骨葬の意味、マナーや流れなどについて解説しました。
骨葬は、葬儀に先立って火葬を行い、遺骨を安置して行う葬儀スタイルのことです。地域性やさまざまな事情により骨葬が選択されるケースは一定数あります。
日本全体では少数派となる骨葬。「最期に故人の顔を見ることができなかった」などのトラブルを発生させないためにも、骨葬を行う場合には火葬のタイミングについて充分な案内を行うことが大切です。
骨葬を検討している方は、この記事の内容を参考にしてください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。










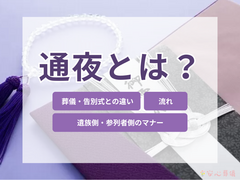
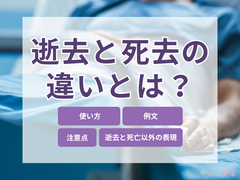
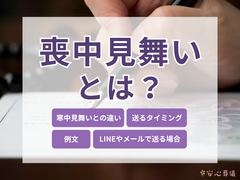
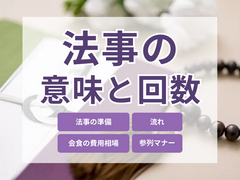
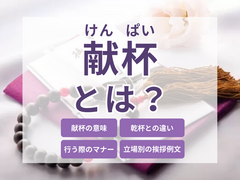
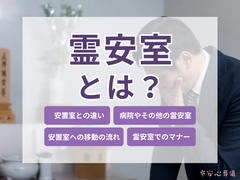
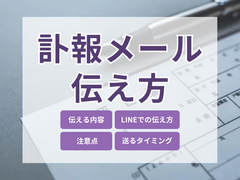

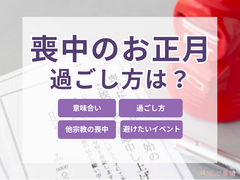
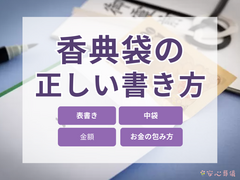
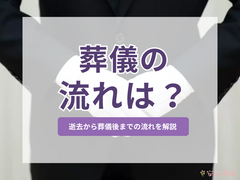

先に火葬を済ませて行う葬儀のことを「骨葬」といいますが、「前火葬」と表現する地域が多いようです。「前火葬」は全国的には1/3程度の地域にみられるといわれています。