会葬御礼とは?その意味やお礼状の文例も紹介

葬儀に会葬・参列してくれた方に渡す返礼品とお礼状を総称して「会葬御礼」と呼びます。
わざわざ足を運んでくれたことに感謝の気持ちを伝えて品物を渡します。「香典返し」と似ている部分があるので間違えないように気を付けましょう。
今回の記事では、会葬御礼にお勧めの品物やマナー、礼状の文面の書き方、香典返しとの違いなどを紹介します。
会葬御礼を準備する必要がある方は参考にしてください。



会葬御礼とは
まず、会葬御礼の基本的な知識を紹介します。ポイントをしっかり押さえていきましょう。
会葬者へ渡す品物
会葬者へ感謝の気持ちを込めたお礼状に返礼品を添えて、香典の授受に関係なく「会葬御礼」を渡します。
本来の会葬御礼は、通夜弔問と翌日の「式」(葬儀・告別式)には、それぞれ別の仕様で渡してきました。
地域にもよりますが、通夜の弔問に対してはお酒(小瓶)や和菓子などを渡していた時代もあります。その折、翌日の式への会葬ができないという理由から、前倒しでお礼状を渡してしまうことが通例になり、通夜と式のどちらにも利用できるお礼状になりました。そこに添える品物も、通夜も式も同じものが使われています。
最近は、お礼状に添える品物もいろいろ多彩になり、時代によって変化しています。
会葬御礼の返礼品についての経緯をさかのぼると、ハンカチのような繊維製品、テレホンカードなどの少額の金券類、お茶やコーヒーなどの嗜好品などさまざまなものに変化し続けています。その品物は別名として、「粗供養品(そくようひん)」と呼ばれることもあります。
葬儀社かギフトショップで用意
品物の内容については、大体が葬儀社に依頼しますが、直接ギフトショップでそろえてもらうこともあります。通常は、予想される会葬者数より多めに用意しておきます。
葬儀社やギフトショップを利用する場合、余った場合の返品が可能かどうかを確認しておきましょう。打ち合わせ時にしっかり確認して依頼します。
また、故人の遺志や喪主の希望で、特定の品物を渡したい場合は、早めに準備が必要です。その際にも返品の不可を確認します。一般的に、和菓子などの生ものは原則依頼者の買取になります。
相場は500円~1500円
会葬御礼に添える品物の予算は、500円〜多くても1500円を目安に見ることができます。
あくまでも「寸志」(ちょっとしたお気持ち)として渡すものです。
会葬お礼状に添える粗供養品の時代的経緯
- 昭和時代:はがき・封筒・切手・半紙・ハンカチ(白無地ガーゼから色物やブランド)
- 平成時代:金券カード類(テレホンカードからクオカード・図書カード他)・真空パック 嗜好品(お茶・コーヒー・紅茶)・乾物類
- 令和時代:クッキー・あめ・一口羊羹・日常実用品(洗剤・入浴剤など)
日常生活での実用品や少量の嗜好品セットなどを中心に選び、かさばらないことも重要なポイントになっています。
「香典返し」と勘違いされることもあるので、あくまでも会葬御礼としてわかるような配慮が必要です(表書きやカードが入れるなど)。
会葬御礼の内容とは
会葬御礼の内容を紹介します。
白黒・黄白ののし紙をつけた品物
会葬御礼を自分で用意する場合は、一般的に白黒・黄白ののし紙をつけた品物を参列者に渡します。水引は、結び切りを選び、表書きには「御会葬御礼」と記入してください。
のし紙の表書きなどには、筆ペンを使って記入することができますが、地域によっては毛筆を使わなければなりません。気になる方は年長者の方に確認を取るようにしてください。
ただし、現代ではほとんどが業者に任せているので、よほど少人数か、あるいは特定の会葬者のみに渡す場合の知識として知っておいて下さい。
会葬礼状
会葬礼状とは、葬儀や通夜に参列してくれた人に感謝の気持ちを綴って贈るものです。
文章の中では、忌み言葉や重ね言葉、また葬儀施行の宗派によっては、「ご冥福」などの言葉を使用しないこともあります。(浄土真宗など)葬儀社に確認しましょう。
具体的に記入する内容は、故人の名前や命日、喪主との続柄、喪主または故人の住所や葬儀委員長、あるいは親族代表、友人代表なども記載することもあります。
ただし、最近は個人情報管理の観点から、住所などを載せない人もいます。これは香典返しと異なり、不特定な会葬者に一律に渡すものとして意識しておかなければなりません。
お礼の言葉などに、その人らしい一面を記載するなど、最近はオリジナリティな文面も多々あります。
また、テンプレートもいろいろあるので、自分で考えたい人は参考にするとよいでしょう。
お礼状には、遺族が参列者に対して、「ゆっくり挨拶ができない代わりに」という思いもあります。それが伝わるようにしておくことも大切です。
宗派により清め塩
一般的に、会葬礼状には、「お淨め・お清め」の「塩」の小袋をつける慣例があります。これは、会葬者が式場や火葬場から自宅へ帰る際、玄関先で自身に振りかけるもので、いまだにその慣習がみられます。塩を振りかけることにはいろいろな意味がありますが、「死への不浄感」を払う所作と云われています。ただ、浄土真宗などの宗義では、この慣例を行わないこともありますので、事前に葬儀社の方に相談しておくとよいでしょう。
宗派が浄土真宗だったとしても、一般会葬者はそれぞれ宗旨・宗派も異なり、その教義のしきたりを押し付けることはさけるべきでしょう。



会葬御礼を渡す際のマナーとは
会葬御礼を渡す際に押さえておきたいマナーを紹介します。
一般的には焼香後、帰るときに渡すケースが多い
受付で記帳後、式中の焼香が終わってその場から出たところで、葬儀社スタッフが渡します。
最近は受付時に渡すことも多い
受付での記帳後、香典の授受などの際に会葬御礼を手渡すこともよくあります。ポケットやハンドバッグに入るようなものであればよいですが、紙袋などでかさばるものを式場内に持ち込み、お焼香の際の手荷物になるようでは、少し配慮が足りないかもしれません。
式後、出棺後など、間に合わないで会場へ着いた人は、後片付けをしている葬儀社スタッフから、とりあえず会葬御礼を受け取り、後日香典などをお届けするようにしましょう。
よほど少人数であれば、遺族が直接渡すこともあるかもしれませんが、通常は葬儀社のスタッフや関係者のお手伝いの方が渡します。
渡す側の配慮として
会葬御礼を渡すときは、会葬へのお礼の言葉を添えて手渡しします。
「配る」ような態度ではいけませんし、無言で渡すのはマナーに反します。
例えば、「ご会葬ありがとうございました。どうぞお受け取りください」など、小声でも聞き取れるように伝えます。
郵送で後日渡すケースもある
遠方からや部・課単位で代表者のみが会葬されたような場合は、全員に手渡しができません。郵送・宅配などで送付するケースもありますが、日持ちがするものがある場合は、なるべく早く送るのが良いでしょう。
会葬御礼に添えるお勧めの品物三つ
会葬御礼にお勧めの品物を紹介します。
何を選ぶか迷っている方は、参考にしてください。
持ち運びやすいもの:ハンカチ・タオルなど
会葬御礼にお勧めの品物の一つ目は、「持ち運びやすいもの」です。
具体的には、ハンカチ・タオルなどが挙げられます。
帰りのときも軽くて荷物になりません。
会葬御礼では、よく選ばれることがある品物です。
ハンカチ・タオルには、「悲しみを拭い去る」という意味合いも込められています。
消えもの:石鹸・洗剤など生活用品
会葬御礼にお勧めの品物の二つ目は、「消えもの」です。
具体的には、石鹸・洗剤・入浴剤など小袋に入ったセットが挙げられます。
持ち帰る際の負担にならないように、できるだけ軽いものを選ぶとよいでしょう。
「悲しみが残らないように・また健康を祈って」との意味合いも込められています。
日持ちする食品・嗜好品:せんべい・クッキー・お茶・海苔など
会葬御礼にお勧めの品物の三つ目は、「日持ちする食品類」です。
具体的には、せんべい・クッキー・お茶・海苔などが挙げられます。
食べて失くなるものは、扱いに困らないという側面があります。
基本的には会葬お礼状のサイズ(はがき大等)に準じたパッケージがお勧めです。
厚みはさまざまありますが、原則的には男性の背広のポケットに収まる大きさが最適です。
コーヒーや日本茶などもスティック状のものや真空パックしたものもあり、いろいろな組み合わせの粗供養品があります。
故人の遺志、遺族の希望、あるいは参列者の好みに合わせた品物を選ぶのもお勧めです。



会葬御礼の品物を選ぶコツ四つ
会葬御礼の品物を選ぶコツを紹介します。
会葬御礼選びに失敗したくないという方は、参考にしてください。
好みが分かれる品物は避けて選ぶ
会葬御礼の品物を選ぶコツの一つ目は、好みが分かれるものはできるだけ避けるようにしてください。
具体的には、コーヒーなどの嗜好品が挙げられます。
代わりにお茶を選ぶのがよいでしょう。
香りがある洗剤や石鹸も好みが分かれることがあるので気を付けてください。
参列者の世代に合わせて選ぶ
会葬御礼の品物を選ぶコツの二つ目は、参列者の世代に合わせることです。
例えば、参列者に高齢者が多いときは、持ち運びに便利なお茶・海苔・ハンカチなどの品物が人気が高いです。
子供が多いときは、菓子類を選ぶと喜ばれやすいです。
どのような人が参列するのか、今一度振り返ってみると、自ずと喜ばれやすい品物も分かるでしょう。
小学校の教師が逝去の際、会葬してくれた子供たちにノートを配った事例があります。
軽い品物を選ぶ
会葬御礼の品物を選ぶコツの三つ目は、軽い品物を選ぶことです。
帰りの手荷物にならないメリットがあります。
具体的には、ハンカチ・タオル、海苔などが挙げられます。
また食べ物でも、重い品物もあります。同時に賞味期限などの制約もあります。
持ち運びの場面も考慮した上で選ぶようにしてください。
葬儀社のスタッフに相談をして選ぶ
品物選びに迷ったときは、葬儀社のスタッフに相談すると、有益なアドバイスが得られることがあります。
よく選ばれているものを教えてくれることがあります。
会葬御礼の品物は、香典返しとは異なるということをしっかりと理解して、最終的には、遺族・親族で話し合って会葬御礼の品物を選ぶようにしてください。
会葬礼状を書くときのマナーとは
続いて、会葬礼状を書くときの一般的なマナーを紹介します。
書式や書き方に決まりはありませんが、常識的なマナーはありますので、その点を押さえておいてください。
文中に句読点は使わない
会葬礼状を書くときは、文中に句読点は使いません。
改行やスペースなどを工夫して読みやすくすることが大切です。
文中に句読点を使わない理由は、俗信ですが、「縁切り」を連想するなど、験を担ぐ習慣から来たものと言われています。結婚式の招待状などの慶事でも使わないこともあります。
時候の挨拶は使わない
会葬礼状では、時候の挨拶は使わずに省略します。
「拝啓」と「敬具」については、書いても書かなくても、どちらでも構いません。
重ね言葉・忌み言葉は使わない
葬儀の場面では、挨拶としても重ね言葉・忌み言葉を使わないのがマナーです。
重ね言葉とは「重ね重ね」「わざわざ」というように同じ言葉を繰り返す言葉です。
忌み言葉とは「枯れる」「消える」「散る」「絶える」など、「死」や不幸が続くことを連想させる言葉を指します。
会葬礼状の文面でも使わないようにしましょう。
薄墨がよいという慣習もある
会葬礼状や香典返しにつける奉書などは、薄墨が丁寧と言われています。これは「悲しみの涙で墨が薄まってしまった」という情感を表した繊細な感性表現です。
自分で手書きする場合には、このような慣習も踏まえられますが、一般的には印刷になるので、奉書などの場合は「薄墨仕様」を指定してもよいでしょう。ただし、会葬礼状ははっきりと読みやすくしておいた方がよいと思います。
会葬礼状の定型文例とは
一般葬における、会葬礼状の文例を紹介します。
「亡父 ◯◯◯◯の通夜 葬儀に際しご多忙中にも関わらず参列いただき
また御鄭重なご香料を賜り謹んで御礼申し上げます
本来であれば拝趨のうえ御礼申し上げるべきところ
略儀となりますが書中にて御挨拶申し上げます
◯年◯月◯日
住所
喪主
外 親戚一同」
普段使い慣れない言葉がいろいろあります。「遠路態々」、あるいは「辱い」(かたじけない)などの文面を定型にしているところもありますが、現代的には、なるべく平易に書いた方が分かりやすく感じます。
また、家族葬などにおいては、「父はお迎えが来る直前まで、趣味の読書で和やかに過ごしておりました。」などのオリジナルのエピソードを含めることもあります。
会葬礼状は葬儀社が用意するケースが多い
会葬礼状は、葬儀社が定型文を用意するケースが多いです。
遺族が一から文面を考えて用意するものではありません。
遺族の気持ちを文面にしたものをコピーして配布しても構いません。



会葬御礼と香典返しの違いとは
最後に、会葬御礼と香典返しとの違いを紹介します。
香典返し
香典返しは通常、香典を受け取った方に対して、四十九日忌法要の後に贈る返礼品で、忌中明けの社会復帰をもとに、日常の贈答慣習にのっとって行われるものです。その名の通り受け取った香典の金額に対応して、お手紙と返礼品を添えてお送りします。お礼状には、忌中明けの報や納骨などの報告として、この弔事を滞りなく終えたことを伝える意味合いも込められています。
一方、会葬御礼は、通夜や式への弔問・会葬に対するお礼状とそれに添えられた「粗供養品」を、施行会場で渡すものです。
故人を供養する場面でのお礼という似ている部分から、同じものとして覚える方もいますが、まったく別物となるので、間違わないように気を付けましょう。
なお、最近では「当日返し」という慣例を葬儀社が提案して、通夜や式当日に会葬お礼と主に香典返しも渡してしまうケースが増えてきました。これは安直な方法かもしれませんが、充分に考慮すべき現代風潮の様式です。また金銭的な無駄も多く見受けられます。
香典返しのしきたりは「半返し」?
香典返しの金額相場は、受け取った香典の半額に当たる品物をお返しするものとされてきました。これは結婚式のご祝儀を「倍返し」に見立てた慣例です。もともとの香典は、葬儀施行への支援を地域共同で行うために食料の提供や労力の供出がなされ、互酬性を持った地域の相互支援でした。ですから「お返し」はありません。それが現金の授受に代わり、一般的な贈答慣例と連動して、返礼を促すようになったものと言われています。ある高名なマナーの大家の著作から、「半返し」という相場が普及したという説もあります。
実務的には、例えば1万円の香典に対して、送料も含めて3000円以内が相場です。それ以上になると「何のための支援か」という意味が霧散します。近親からの多額の香典は、まさに葬祭費用の支援のためのお包みです。もちろん金額に沿った返礼は必要ですが、半返しという通例はまったく意味がありません。
近年の葬儀ではその場で渡す「即日返し(当日返し)」もある
香典返しは四十九日の法要の後に渡す品物ですが、近年の葬儀では、香典を受け取ったその場で返す「即日返し」をするケースも増えています。
受け取った香典の金額に合わせた品物を渡すことになります。
また、故人との付き合いの深さによっても渡す品物は変わることがあります。
これはその場で香典金額を確かめて、仕分けした返礼品をその場で渡すなど、慌ただしさを感じますし、間違いも起こります。簡潔さはありますが、「簡略・安易」と見受けることもあります。また会葬者それぞれに、返礼品の差異が目立つこともあり、気になります。
場合によっては、手渡すときに会葬御礼と間違われることもあります。
香典のお返しであることを一言添えるようにしてください。
まとめ
会葬御礼とは、葬儀や通夜に参列してくれた人へ感謝の気持ちを込めて渡す品物です。
相場は500円〜1500円で、葬儀社かギフトショップに依頼すると用意できます。
お勧めの品物は「持ち運びやすいもの」か「消えもの」か「日持ちするもの」で、好みが分かれるような品物は避けた方が無難です。
会葬礼状を書くときのマナーは、重ね言葉・忌み言葉は使わないことです。
また、葬儀社が定型文を用意するケースが多いです。
香典返しは四十九日忌法要の後に渡す品物です。会葬御礼とは意味が違いますので混同しないようにしましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。










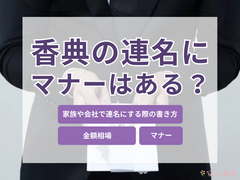










元来地域の相互扶助で行ってきた葬式は、会葬の御礼として、飲食接待でのもてなしで済ましてきました。葬儀社主導の時代になり、贈答慣例が結びつけられ「粗供養品」や「香典返し」の「返礼ギフト」が派生しました。