告別式とは?式の流れやマナーなどを紹介

一般的なお葬式は、前日の通夜、当日の葬儀・告別式と2日間にわたって行われます。この2日目に行われる葬儀と告別式とは、一体どのような違いがあるのでしょうか。中でも告別式の詳しい意味を知っている方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、告別式について、「葬儀との違い」という観点から、意味、式の流れ、マナーなどについて解説します。



告別式の意味とは
告別式とは、その言葉が示すように、故人とのお別れのために、遺族、友人や知人、近隣の方々や会社の人たちが参集する式のことです。そこでは、焼香や献花などの作法で拝礼をしてその死を悼みます。
現在ではほとんど見られなくなりましたが、古くは葬儀が終了した後に、親族や近隣の人々が列を組んで遺体を埋葬地や焼き場まで運ぶ「野辺送り」が広く行われていました。遺族や親族だけではなく、共同体の住民として、故人や遺族との社会的つながりのあった人たちも、野辺送りを通じて弔いに参加したのです。
近現代に入って、都市を中心に近代的な火葬場が普及したことで、伝統的な野辺送りは消滅しました。加えて、葬儀の習俗や宗教的な祭司との対応が合一して、「式典」としての告別式がお葬式に一体化され始めてきました。そのため、通夜の弔問が、「会葬」の前倒しでの場となり、葬儀式場など斎場施設の拡充とともにお葬式の形態が大きく移り変わることになりました。
告別式は、本来持っていた「生前に関係のあった人たちが故人との最期の別れを惜しむ」という意味だけではなく、社会的な節目となる「式典」(セレモニー)として、現代的な意味を合わせ持つようになりました。
告別式を含む葬儀の全体の流れについてはこちらの記事もご参照ください。
関連記事

偲ぶ会の意味とは?一般的な形式についても紹介します
これまでの「偲ぶ会」は、著名人や企業の重鎮が亡くなった場合などに営まれることが一般的でした。しかし近年では、一般の方が亡くなった場合にも偲ぶ会を営むケースが増えています。 ですが、会の意味や一...
続きを読む
告別式の流れとは
お葬式での告別式(仏式の場合)の流れを確認しておきましょう。
開始式10分前には着席
一般的には、葬儀と告別式は同時進行で営まれます。
葬儀・告別式開始の10分前には式場に集合し、着席して僧侶の入場を待ちましょう。
開式の辞
司会者が式の開式の辞を述べます。まずは、宗教儀式である葬儀が始まります。
葬儀
流れの詳細は下記の記事をご参照ください。
関連記事
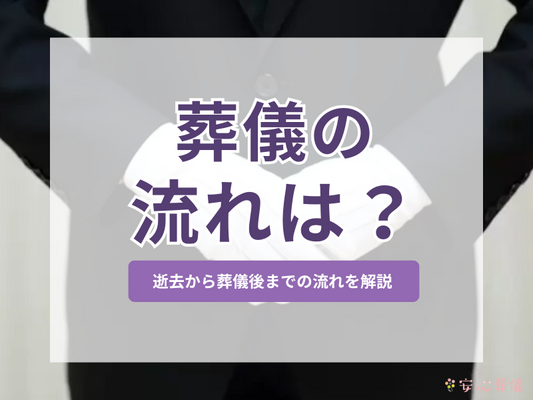
葬儀の流れを解説|葬儀を行う前から葬儀後まで
本記事のポイント臨終時は亡くなられた場所によって対応が異なる病院で亡くなられた際は、速やかにご遺体を別の場所に安置する必要がある葬儀社には葬儀だけでなくご遺体の搬送や安置も依頼するのが一般的遺族...
続きを読む
焼香
葬儀社などの案内で、読経中に焼香を行います。
仏式葬儀では、導師の焼香後、遺族・近親者の焼香が優先されます。一般会葬の礼拝はそれ以降になります。
焼香は、導師→喪主→遺族→親族→一般会葬者(式場内着席者)→式場外待機の一般会葬者という順番になります。これは、司会者からも案内があります。
僧侶退場
焼香が終わった時点で、葬儀・告別式の僧侶が退場します。
弔電拝読
弔電とは、参列できなかった方から故人へのお悔やみを伝えるために送られる電報です。
もらった弔電の一部を紹介し、司会者が読み上げます。
その後、司会者から故人の略歴や生前のエピソードなどが紹介される場合もあります。
お別れの儀
出棺の前に、「お別れの儀」または「お花入れの儀」が行われます。遺族や親族を中心に、祭壇の花や供花などを棺の中に手向けながら、故人と最期のお別れをします。故人の顔の周りを中心にできれば足元の方にもお花を入れます。
釘打ち
これまでは、伝統的な「封印儀礼」の一として、棺の蓋を閉めた後に釘打ちをして、喪主や遺族も石などで打ち付けるしぐさをしていましたが、最近では地方でもほとんど見られなくなりました。。また宗旨によっては最初からしないところもあります。
喪主挨拶
喪主が会葬者に対して挨拶をします。喪主に代わり遺族代表が挨拶するケースもあります。
閉式の辞
司会者が閉式の辞を述べます。葬儀・告別式が終了となります。
出棺
近親者や縁故者によって棺を霊柩車へ運び、乗せます。弔笛(クラクション)を鳴らした後、火葬場へ向かいます。親族はマイクロバスなど所定の車に乗車し、火葬場に同行します。それ以外の会葬者は合掌にて出棺を見送ります。
火葬
火葬場に到着後、係員の指示で火葬炉まで運ばれて、遺体を荼毘(だび)に付します。
骨上げ
火葬された遺骨を骨壷に収めることを「お骨上げ」または「拾骨(収骨)」といいます。この時にも、遺骨をつまむ箸づかいや互いにはさみ合うなど、習俗的な慣例がいくつかあります。「はしわたし」から連想されるのは、あの世へいざなうというような意味もあります。
還骨法要
還骨法要とは、自宅などにしつらえた後飾り段に遺骨を安置し、遺影や位牌を並べて営む法要のことです。場合によっては初七日忌法要と併せて行うことも多くあります。僧侶の読経の最中に焼香をしてあらためて追悼の念を示します。
精進落とし
本来の「精進落とし」は忌明け(49日目)に行うものですが、現在では式後の締めくくりの会食になっています。遺族側から参列者に対して、故人になり代わって慰労や御礼の意味を込めて、おもてなしをします。
告別式の流れについては以下記事でも取り上げていますのでぜひご覧ください。
関連記事
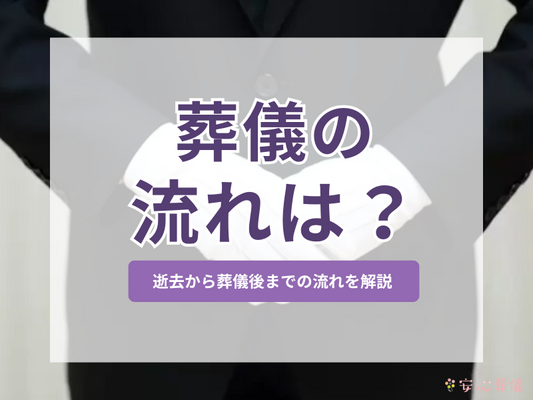
葬儀の流れを解説|葬儀を行う前から葬儀後まで
本記事のポイント臨終時は亡くなられた場所によって対応が異なる病院で亡くなられた際は、速やかにご遺体を別の場所に安置する必要がある葬儀社には葬儀だけでなくご遺体の搬送や安置も依頼するのが一般的遺族...
続きを読む



葬儀・告別式で準備すること
通夜を終えた後、喪主は葬儀社と翌日の葬儀・告別式の最終確認をします。具体的にどのようなことを確認し、準備しなければならないのでしょうか。
席次と焼香順の確認
式中での着席順や指名での焼香の場合は、その序列をあらためて確認します。着席参列者の回し焼香の場合、着席順になります。また、祭壇に進み出て正対して立礼で行う場合でも、やはり席次の順番で進み出ますので、充分に確認しておくことが大切です。
葬儀と告別式を明確に分けて行う場合には、葬儀後に遺族は、あらためて告別式の焼香台の両脇に立って、会葬者と向き合う形でお迎えします。着席の場合でも、喪主はやはり立礼で対応した方がより丁寧です。
弔辞の順番を決める
弔辞を承ることがあれば、その順番もしきたりや実例に通じた葬儀社の担当者と相談しながら決めます。
また、弔辞を読む人の席次も確認しておきます。
紹介する弔電とその順序を決める
多数の弔電が届いている場合には、時間的制約から、①全文を読み上げる弔電②電文省略の断りを入れて、名前・肩書のみ紹介する弔電③他多数として数量などをあげて一括する弔電に分類する必要があります。
弔電の送り主と故人との関係性により読み上げる順序は変わるので、葬儀社の担当者と相談しながら決めましょう。弔電は対外的な意味合い(社会的関係)で受け取るものです。顧客や取引先などを優先して拝読するものと言われています。
一般的には、議員(国会議員・市区町村の首長・各議員)・取引先・恩師・顧客など順で読み上げられます。親戚や遺族は後にすることも通例です。
喪主挨拶
出棺前には、参列・会葬者に対して喪主や親族代表が挨拶をします。どのような言葉を述べるのか文面をまとめておきましょう。
喪主挨拶のタイミングは、遺族として心情的につらい場面であることが多いです。言葉に詰まってしまうようであれば、あらかじめまとめておいた文面を読み上げても問題ありません。告別式の式典意義はこの挨拶にあります。通常は、逝去の経緯、生前のお礼、今後のお付き合いに際しての継続や支援のお願い、そして本日会葬してくれたことに対する感謝などを述べます。
火葬場への同行者を確定する
火葬場への移動手段(マイクロバス、ハイヤー、タクシーなど)の確保や、火葬場から戻ってから設けられる精進落としの席での料理の準備のためにも、同行者の人数を遺族側で正確に把握しておく必要があります。
車両と料理の数量などの手配自体は、葬儀社側が進めることが大半ですので、火葬場へ同行すると考えられる人には前もって確認を取って、確定人数を葬儀社側に伝えましょう。
僧侶へのお布施を用意する
僧侶に渡すお布施は、葬儀社へ支払う料金とは別に必要となります。お布施を渡すのは通夜または葬儀の当日が一般的ですが、儀式の前や終了後、あるいは事前にお寺へ挨拶に行くときに持参するなど、タイミングはさまざまです。
お布施は何らかの対価ではなく、財施(仏教の修行で行うべきとされる徳目の一つ)として行うというのが本来の考え方ですが、社会通念上は読経や戒名などへのお礼と考えられています。金額はお寺によって異なるため、同じ檀家の方に尋ねるか、お寺に直接確認してもよいでしょう。どうしても分からない場合、ある程度の相場もあるのが実情なので、葬儀社に相談して相応と思われる金額を準備しましょう。
弔電や供花の確認
受け取った弔電や供花を確認します。
後でお礼状を送るため、贈呈者の芳名などを記しておきましょう。
その他注意や心がけなど
着席参列者や一般会葬者に対して失礼がないように、席次や氏名・肩書、もらった弔電などをきちんと確認しておきます。また一般会葬者には焼香前の待機場所などへの誘導なども大切です。高齢者への対応も葬儀社に指示をしておきます。
開式直前に弔電や供花などが届くことも珍しくありませんので、取りこぼすことのないよう、開式の直前まで注意を払うようにしましょう。
告別式に参列する際のマナーとは
告別式に参列する側のマナーにはどういったものがあるのでしょうか。
服装のマナー
葬儀・告別式においては正喪服が本来とされている喪主とは異なり、一般参列者の場合は準喪服・略喪服で臨むのがマナーです。ただし近年では、喪主であっても準喪服や略喪服を着用することが一般的となっています。そのため一般参列者は喪主より正装の格式が上にならないよう、略喪服を選ぶのが無難でしょう。
女性の服装マナー
光沢のない生地の黒色アンサンブルやスーツに、足元は黒のストッキングというのが一般的です。
本来は殺生を連想する革製品は避け、携行するバッグは布製のものが理想的でしたが、昨今では、黒であれば皮革製でも許容されるようになっています。ただし、布製であれ皮革製であれ光沢感のある素材は不適切です。
靴も黒色で、できるだけ革製品は避け、光沢がなく華美でないものを選ぶようにしましょう。
ヒールは高すぎないものが最適です。また、斎場や式場内の床質にもよりますが、歩行での靴音なども読経中には気になるものです。コツコツと音が響くものの着用は避けましょう。
アクセサリーを身に着けるのであれば、真珠やジェットの一連ネックレスや同素材の控えめなイヤリングに限ります(常時身に着けていることが前提である結婚指輪についてはその限りではありません)。
2連や3連になっているアクセサリーは不幸が重なるという意味を表してしまうため着用は避けましょう。
髪型はショートやミディアムなどの短い髪であればそのままでも大丈夫ですが、肩より下の長さの場合は、耳よりも低い位置でシンプルにまとめておくのがよいでしょう。
束ねるときに使うゴムやピンも黒色のものを使用しましょう。派手な飾りやシュシュなどは使わないようにします。
葬儀で使うハンカチは白の無地かフォーマルの黒(レースなど)を使うようにします。
葬儀や告別式などでのメイクは、ナチュラルメイクが基本です。派手な色は避けて、ベージュ系などでメイクしましょう。
男性の服装マナー
ブラックスーツかダークスーツに白無地のワイシャツ、黒のネクタイ(結び方はプレーンノットでネクタイピンは地味なもの)、黒の靴下、黒の靴を合わせます。
上衣はシングル、ダブル、どちらでも構いませんがズボンの裾はシングルにするのがマナーです。スリーピーススーツは、おしゃれ着の印象を与える場合もあるため、なるべく避けた方が無難です。
なお、会社、団体の制服などがあれば、それを礼装として喪服として着用することもあります。学生はそれぞれの制服があればそれを着用します。
靴は黒で光沢のないシンプルな革靴を選びます。
男性は結婚指輪以外のアクセサリーは外し、派手な腕時計はマナー違反になるので外しましょう。
また整髪料を使う場合は、香りの強いワックスなどは避けるようにし、使用する場合は無香料でツヤ感の出ないものを使いましょう。
香典のマナー
結び切りの水引のかかった不祝儀袋を用意します。
香典を包む不祝儀袋のグレードは包む金額に見合ったものとし、包むのが1万円以下であれば本式の水引ではなく水引柄が印刷されている略式のもので充分です。
表書きは、仏式であれば「御香典」「御香料」「御霊前」「御仏前」などがありますが、宗派を問わず用いることのできる「御霊前」または「御香典」としておけば問題ありません。
一般的に「御仏前」は忌明け後の法要などの表書きとなります。
表書きを書く際は、薄墨というしきたりもありましたが、現代では廃れました。
香典を包んだ不祝儀袋はそのままではなく、袱紗に包んで持参するのが礼儀とされています。なお、通夜と告別式の両方に出る場合は、通夜の際に持参します。また、地域の慣例として、お見舞いや式後の法要・会席参加の場合に、別に包むこともあります(「寂し見舞」の風習)。
また、弔事で包むお札には新札を避けた方が無難という通例もあります。あらかじめ準備していたようで失礼に当たると考えられていることが理由です。新札の場合は、一度折り目をつけてから入れるようにしましょう。
数珠のマナー
宗派ごとに数珠は異なりますが、葬儀・告別式の宗派にあわせる必要はなく、自身が持っている数珠を持参して構いません。
数珠は焼香の直前に出すのではなく、葬儀を行っている間は基本的に左手に持っておくのがマナーです。
数珠の持ち方も宗派によりますが、一般的には左手にかけ、焼香時には両手に通して合掌します。
数珠は拝礼の仏具としてだけではなく、その人のお守りという意味もあります。できれば自分の数珠を一つは持つようにしましょう。



通夜と告別式はどちらに参列すべき?
いろいろな考え方がありますが、葬儀は本来、「葬送」と「儀礼」という二つのカテゴリーから成り立っています。「葬送」は遺体に対する習俗的な処方と実務(安置・納棺・火葬に関わる慣習的な手立て)、「儀礼」は主に宗教的作法にとっとり、故人の「たましい」に対して行われる処方となります。そのため、「通夜」は、「葬儀」の一環として組み入れられます。しかしながら、近現代になって、通夜は「故人と親しい人たちで営まれるもの」、翌日の式は、「一般的な会葬の場として対外的に行われるもの」という認識が共有されて来ました。
そして、葬儀・告別式に来られない人たちに対しての配慮から、「通夜弔問を会葬」とみなすようになり、いつしか、通夜が翌日の式の前夜祭としての位置付けとなりました。そして今では、通夜の方が圧倒的に「会葬」人数が増えているのも現実です。
結論的には、どちらに出向いても構いませんが、「告別」という意味を充分に心に留めて、出向かれるとよいでしょう。つまり自分と故人との社会的関係性の中で、決別を図るために会葬するという気持ちが大切です。
参列できない場合のマナー
できれば、簡単な理由などを記したお悔やみの手紙を送って、「ご容赦」をお願いします。また、弔意を伝える手段として、香典や供花などを送ってもよいでしょう。香典の場合は、代理者に託すか、現金書留で香典袋ごと送るようにします。
関連記事

葬式に行けない場合の弔意の伝え方とは?弔電や香典と後日の弔問について紹介します
親交の深かった友人やお世話になった先輩など、大切な方が亡くなった際には、できれば葬式に参列したいと思う人が多いのではないでしょうか。 しかし、葬儀の行われる場所が遠方だったり、どうしても外せな...
続きを読む
まとめ
遺族として、あるいは参列者として、いつかはその場に臨まなければならない告別式。普段参列する機会がないために積極的に調べることもなく、曖昧な理解しかしていない人も多くいると思います。
知っているつもりのことも含め、告別式の持つ意味、式全体の流れ、マナーなどを改めて確認し、正しい理解を得ることにより、穏やかな気持ち、落ち着いた心で見送りができるようにしておきましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。










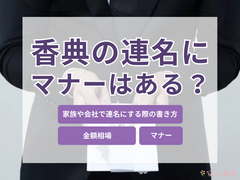










告別式は遺体や宗教とは関係のない世間的な対応。それを理解すればその人らしいお別れを実施することが可能です。内々で、と云うご時世。後で悔やむ人も多くいます。今後は是非新しい形の告別式を考えたいものです。