葬式での香典の相場や香典袋の書き方、マナーについてなど詳しく解説

社会に出るようになれば、葬式に参列する機会は多かれ少なかれ出てくるもので、そうした際に考えなくてはならないのが香典です。
本記事では、香典の意味合い、マナーと相場、渡し方や送り方について紹介します。



香典の意味と相場
そもそも香典とは、どういった意味合いを持つものなのでしょうか。
そして、故人との関係性により変わってくる香典の相場は、いくら程度なのでしょうか。
香典の意味
香典はかつて、”香を供える”という意味で「香奠」と書きました。そこから香を買うための金銭を渡すという意味に転じて、香典、香料、香資と呼ばれるようになりました。
香典は、「お供えするもの」という意味もありますが、実際には、「葬式という急な出費に直面する喪主を経済的に助ける」という、相互扶助の意味合いも持っています。
昔は、どこかの家で誰かが亡くなれば、地域の住民が総出で葬式を手伝ったり、食料を持ち寄ったりする慣習がありました。そうした食料や労力の提供が、香奠としての意味を持っていたとも言えます。
しかし今日では、近隣の人たちが葬儀の中で労働力として喪家を支える習慣は一般的ではなくなりつつあり、金銭面で援助する香典という形に変化し、地域社会における相互扶助の精神が残っていると言えるでしょう。
香典の相場
香典として包む金額は、故人との関係性により変わってきます。
地域や香典を出す人の年代によっても多少異なってきますが、おおむね次の通りです。
| 間柄 | 相場 |
|---|---|
| 親 | 5万円~10万円 |
| きょうだい | 3万円~5万円 |
| 祖父母 | 1万円~3万円 |
| おじ・おば | 1万円~3万円 |
| 友人・知人 | 5000円~1万円 |
| 恩師 | 5000円~1万円 |
| 近所の付き合い | 3000円~5000円 |
| 上司・同僚 | 5000円~1万円 |
| 上司・同僚の家族 | 5000円~1万円 |
基本的には相場を参考に
いくら包もうかと迷った際に「多めに包んでおけば間違いないだろう」という判断が通用するのは、結婚祝いなどの御祝儀の場合です。お祝い事ではありませんので、香典に奮発して包むという発想はありません。
相場に合わない金額は、逆に遺族の負担となってしまうことも考えられます。包む金額は、生前の故人との関わりの深さによっても多少変わりますが、いずれにしても一般的な相場や地域のならわしに準じるようにしましょう。
香典袋の選び方、入手方法
香典袋には、複数の種類があります。何を基準に選べばよいでしょうか。入手方法も確認しておきましょう。
宗教別に選ぶ
葬式がどの宗教にのっとって営まれるかにより、香典袋も異なります。
なお、香典とは香を供えるという意味から仏教の作法を思わせる用語ではありますが、基本的に宗派を問わず使用できる表現になります。
仏式の場合
無地または仏教を象徴する蓮の花の絵が描かれた香典袋に黒白、双白(左右とも白)または双銀(左右とも銀)の水引をかけたものが用いられます(関西地方や北陸地方などでは黄白の水引をかけたものが使われる場合もあります)。
仏式の香典袋の表書きには「御霊前」 「御香典」 「御佛前」といったものがありますが、「四十九日」以前か以降かで異なります。
故人がまだ成仏していないと考えられる四十九日前の段階では、その表書きを「御霊前」などとし、故人が成仏するとされる四十九日以降の法要の際などに渡すときの表書きは「御佛前」などとします。
例外は、死後すぐに成仏すると説く浄土真宗で、たとえ四十九日前であっても「御霊前」は用いずに「御佛前」または「御香典」などとするのが適当とされています。
禅宗(臨済宗・曹洞宗)も教義に浄土の概念がなく(=浄土に到達して成仏するまでの期間の概念がない)、「霊的存在を認めないことが宗旨の立場である」という考え方はあるものの「精霊に供養する心で営むことが大切」としていることから、「御霊前」という言葉が一般的に広く使われています。
葬儀への参列当日は基本的に四十九日より前になると考えられますが、宗派が不明な場合は「御香典」を選べば失礼はないでしょう。
神式の場合
無地の香典袋に黒白、双白(左右とも白)または双銀(左右とも銀)の水引をかけたものを用いるのが一般的です。
表書きは「御玉串料」 「御神前」などとしますが、「御霊前」も使えます。
無宗教、宗教や宗派が不明の場合
白無地の香典袋に黒白、双白(左右とも白)または双銀(左右とも銀)の水引をかけたものを用い、表書きは「御香典」としておくとよいでしょう。
包む金額に応じて選ぶ
香典袋には前述の宗教による違いに加え、水引が実際にかけられているものと水引の柄が印刷されているものとがあります。
水引がかけられている香典袋にもグレードの幅があり、選び方の基準は包む金額との釣り合いで、具体的にはおおむね次のようになります。
- 1万円以下: 水引柄がプリントされた略式の香典袋
- 1万円~2万円程度: プリントか、一般的な水引のかけられた香典袋
- 5万円以上:上質な和紙や双銀の水引が使われた高級感のある香典袋
香典は基本的に前もって準備するものではないですし、受け取った側が中身の確認作業を迅速に行わなければいけないという都合上、簡易的なものが好まれます。
地域によっては、香典袋を使用せず受付で会費として支払う形をとったり、領収書が出ることもあります。
香典袋の入手方法
大きめの文具店には、さまざまなグレードや各宗教向けの香典袋が取りそろえられていますし、仏式用の一般的なものであれば、スーパーやコンビニなどでも取り扱われています。
また、急いで駆け付けなくてはならない状況で用意が必要な類のものだからでしょう、新幹線ホームにあるキオスク(キヨスク)でも手に入れることができる場合があります。
同じような金封に、紅白の水引がついた御祝儀袋がありますが、こちらはお祝い事の際に使用する金封のことなので、購入の際に間違えないよう注意しましょう。



香典袋には何を書くか
香典袋に記入すべきことと、その書き方を確認しておきましょう。
表書き
宗教・宗派に応じて「御霊前」などの表書きを水引の上の部分に書きます。かつては筆文字がよいとされていましたが、現代ではサインペンで書いても許容範囲内です。
また、四十九日以前であれば「涙で墨がにじみました」という意味合いで薄墨(専用の薄墨筆ペンも販売されています)を使います。
表書きが印刷済みの香典袋では、薄墨調の濃さで印刷されていることがほとんどです。
ただし、地域によっては普通の墨を用いる場合もありますし、近年では表書き専用のスタンプもありますので、昔ほど厳格なマナーではなくなりつつあります。
表書きが印刷済みの香典袋も市販されていますが、薄墨調の濃さで印刷されている香典袋を見かけることが少なくなってきました。
氏名
香典を出す人の氏名(フルネーム)を、表書きの下部分に書きます。表書き同様に薄墨で書くのが正式です。
夫婦で香典を出す場合、一般的には夫の氏名のみを書きます。これは、冠婚葬祭において家(世帯)単位でやり取りを行っていた昔の家制度の名残です。
ただし、夫と妻のどちらとも故人や遺族と面識があるなどの関係性により、夫婦連名でというケースもあります。このような場合は、夫の氏名を書いた後、その左隣りに妻の名前のみを記載します。
また、同僚などが連名で香典を出す場合には、人数が3名以内であれば各自の氏名を向かって右から順に目上の人物から書きます。上下関係がなければ右から五十音順で記入するとよいでしょう。4名以上の場合は代表者の氏名を中央に書き、その左隣に「外一同」と書きます。別紙に全員の氏名を書いて中に入れます。
会社名や団体名は、一番右側へ記載しましょう。人数が多い場合には「社員一同」などとし、中に全員の氏名を一覧にしたものを入れます。
香典を連名にする場合のマナーについては以下の記事をご参照ください。
関連記事
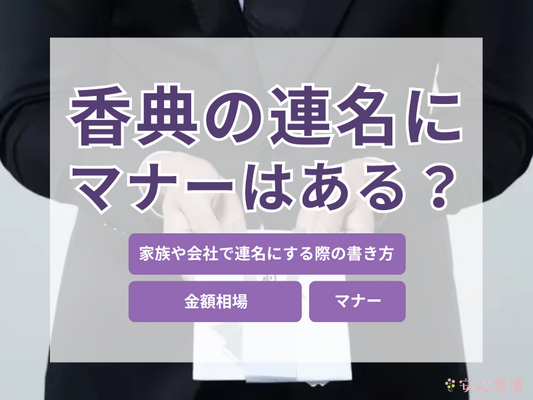
香典を連名にする場合のマナーとは?家族や会社から送る場合の書き方を解説
本記事の結論香典を連名で出すケースには主に①団体で用意する場合②夫婦・家族で用意する場合がある団体の場合、個人で香典を包むより連名にしたほうが遺族側の香典整理や記帳の手間を減らせるため、遺族側に...
続きを読む
住所、金額
香典を出す人の住所と、包んだ金額を書きます。
これは、葬式後に香典返しや礼状などの手配をすることになる喪主が必要とする情報です。
したがって、表立って見える場所ではなく中袋に書きます(中袋のないタイプの香典袋の場合は裏面に記入)。
金額については通常の漢数字の代わりに「壱、弐、参」などの大字(だいじ)を用いるのが正式とされますが、近年では通用字体の漢数字で書かれるケースも増えている傾向です。また、金額の最初には「金」をつけます。
なお、香典袋の表には薄墨で書くのが基本ですが、中袋に関してはサインペンでも構いません。
香典の渡し方
葬式に参列する際に持参する場合は、参列前に受付での記帳とともに係の人に手渡します。
通夜と告別式両方に参列するケースでは、通夜の際に受付にて渡し、告別式では通夜の際に渡した旨を受付係に伝えることが一般的です。
葬儀に持参するふくさの包み方やふさわしい色については以下の記事をご覧ください。
関連記事

葬式やお通夜でのふくさの包み方とは?ふさわしい色などの選び方も紹介します
葬儀に香典を持参する際、「袱紗(ふくさ)」に包んで持参するのが基本です。 袱紗の存在はなんとなく知ってはいるものの、袱紗の包み方や適した色、マナーなど、詳しくは知らないという方もいるのではない...
続きを読む
葬式に参列できない場合は、後日、現金書留で郵送することができます。その際は、手紙を添えるようにしましょう。また、葬儀終了後に初めて遺族と顔を合わせる際に手渡すのもお勧めです。
香典を郵送する際のマナーについては以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事
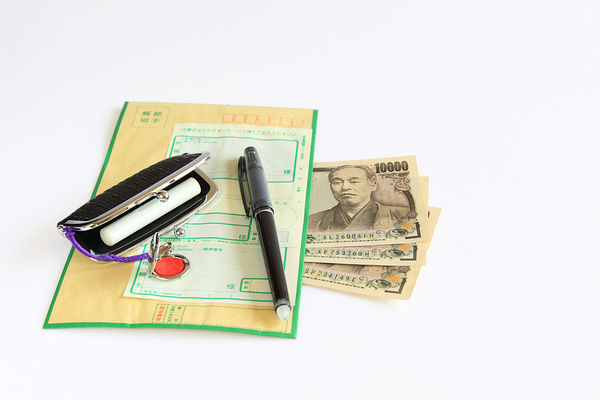
香典を郵送する際のマナーとは?添える手紙の文例も紹介します
一般的なマナーとして、葬儀に参列するときには香典を持参します。しかし、何かしらの事情で葬儀に参列できないこともあるでしょう。 葬儀に参列できないが香典は渡したいという場合、いくつかの対応方法が...
続きを読む



その他の香典のマナー
香典を用意する際には、上記の他にも気を付けるべき点があります。
あまり神経質になりすぎる必要はありませんが、ここで最低限のマナーを紹介します。
新札は避ける
あまりに汚れたお札は避けるべきですが、新札も「不幸を予期して用意していたようである」という理由から避けるべきとされています。
手元に新札しかない場合には、折り目をつけて「まっさらな新札ではありませんよ」と示す慣習があります。
お札の向きに気を配るべきか
人物像がすぐに見える向きでお札を入れる、あるいはその逆など、香典のお札の向きには諸説あるので、あまりこだわっても仕方がありません。
気を付けるのは、お札が2枚以上になったときに全てのお札の向きをそろえるという点です。
お札の枚数や金額に気を付ける
香典に限りませんが、「死」を連想させる4(四)枚や「苦」を連想させる9(九)枚となることは避け、4や9の付く金額も避けるようにします。
割り切れる偶数枚数や偶数の金額は「切れる」「別れる」などに通じるとして、基本的には避けるべきとされているので、奇数枚数となるように心掛けます。
最近では1万円では少なく、3万円では多いという場合に、間をとって2万円を包んでも問題ないという認識が一般的になりつつありますが、地域の考え方や相手によっては抵抗のある方もいるかもしれません。お札の枚数を奇数にするか、こだわる理由がなければ奇数の金額で包むのが無難でしょう。
香典の正しい包み方について以下の記事で取り上げていますのであわせてご覧ください。
関連記事
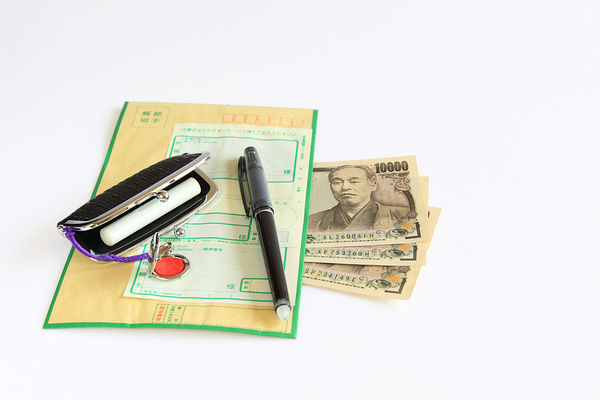
香典を郵送する際のマナーとは?添える手紙の文例も紹介します
一般的なマナーとして、葬儀に参列するときには香典を持参します。しかし、何かしらの事情で葬儀に参列できないこともあるでしょう。 葬儀に参列できないが香典は渡したいという場合、いくつかの対応方法が...
続きを読む
葬儀に参加できない場合の香典の対応とは
やむを得ず葬儀に参加できない場合は、まずはその旨を遺族に伝えましょう。その上で別の方法で弔意を表します。
他の参列者に香典を託す
自身が葬儀に参列できない場合、他の人に香典を託すことも可能です。もし同じ葬儀に参列する友人や会社の同僚がいるようなら、この方法を使うのがよいでしょう。
預かってもらう香典袋には、自分の住所・名前・香典の金額を書いておくと後から遺族が確認しやすいです。
郵送で香典を託す
香典は、郵送することもできます。
ただし、香典を郵送する際は香典袋をさらに現金書留封筒に入れて送る必要があります。
現金を入れた香典袋をそのまま送ることは、法律で禁止されています。くれぐれも普通郵便で香典を送らないように注意しましょう。
郵送する場合は、一言お悔やみの手紙を添えるとより丁寧です。
関連記事
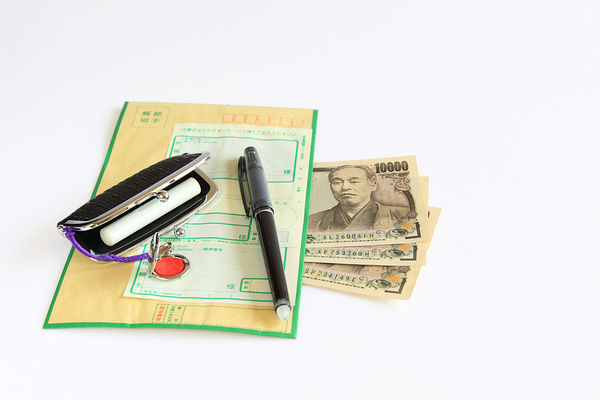
香典を郵送する際のマナーとは?添える手紙の文例も紹介します
一般的なマナーとして、葬儀に参列するときには香典を持参します。しかし、何かしらの事情で葬儀に参列できないこともあるでしょう。 葬儀に参列できないが香典は渡したいという場合、いくつかの対応方法が...
続きを読む
香典以外の方法で弔意を示すこともできる
香典以外で弔意を示す方法としては、「弔電を送る」「供花を送る」などがあります。
いずれの方法も葬儀の時間を確認した上で、葬儀に間に合うように手配します。供花は葬儀社によっては持ち込みができないところがあるので、事前に葬儀会場に相談しておくのがよいでしょう。
関連記事

葬式に行けない場合の弔意の伝え方とは?弔電や香典と後日の弔問について紹介します
親交の深かった友人やお世話になった先輩など、大切な方が亡くなった際には、できれば葬式に参列したいと思う人が多いのではないでしょうか。 しかし、葬儀の行われる場所が遠方だったり、どうしても外せな...
続きを読む



まとめ
香典には、故人へのお供えという意味の他に、葬式という急な出費を相互扶助の観点から援助するという意味合いもあり、包む金額は、故人との関係性により変わってきます。
加えて、香典袋の表書きは宗教や時期により異なる上に、香典袋には複数の種類があるので、宗教や包む金額に応じて適切なものを選ぶようにしましょう。
宗教・宗派が不明の場合には、白無地に白黒、双白、双銀いずれかの水引がかけられたものを用い、表書きを「御香典」とするのが無難です。
香典を渡すことになる方は、大切な人を亡くして心身ともに大変なときです。適切な作法でお悔やみの気持ちを伝えられるように、香典のマナーを知っておいてください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。










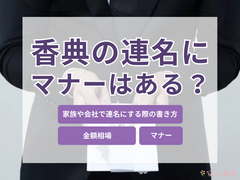










香典袋に掛けられている水引は、遣隋使が持って帰ってきた中国から天皇家への贈り物に麻の紐が掛けられていたことから、大切なものに紐を掛けるという文化が育まれたそうです。江戸時代は武家の間で、明治になると一般にも水引の礼法が広まるようになりました。