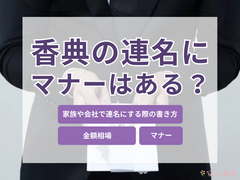葬儀での写真撮影はできる!マナーを解説

葬儀の際に、「写真撮影ができるのか」と気になりませんか?
参列できない方に、写真を送りたいと感じる方もいるでしょう。
結論から言えば、撮影は可能です。
しかし、マナーを押さえておく必要はあります。
今回の記事では、葬儀での写真撮影について、撮影をする意味やマナーなどを紹介します。
葬儀での写真の撮影が不謹慎ではないかと気になる方は、この記事を参考にしてください。



葬儀での写真撮影とはなにか
葬儀で写真を撮影することは、基本的に問題はありません。
しかし、自分勝手に撮影することはできません。
撮影の可否を、ケースごとに見ていきましょう。
葬儀社に依頼しカメラマンに撮影してもらう
葬儀社に写真撮影を事前に依頼しておくと、カメラマンに撮影してもらうことができます。
葬儀で集合写真を撮る場合は、プロのカメラマンが撮影するケースが多くなります。
プロのカメラマンに頼むと、写真が期待通りの仕上がりになることが多いだけでなく、会場の様子なども併せて撮影してもらえます。
「絶対に撮影を失敗したくない」という方こそ、プロのカメラマンに依頼するようにしてください。
なお、カメラマンへの依頼は、葬儀社に相談して手配するのがお勧めです。
葬儀中は撮影するタイミングや立ち位置の判断が難しく、また宗教者の意向で儀式中の撮影不可となることもあります。宗教宗派によっては、写真撮影が禁じられている箇所もあります。
葬儀社を通じてカメラマンを手配すると、葬儀会場での撮影に慣れたカメラマンが入るというだけでなく、葬儀の進行や動線、注意事項などの打合せをすべて任せることができるというメリットがあります。
逆に考えると、個人でカメラマンに依頼した場合は、葬儀当日にそれらの点について確認を行い、会場側や葬儀社と細かく打合せをする必要があります。
親族・参列者が撮影するときは注意が必要
親族・参列者が写真撮影をする場合は、遺族や葬儀社に許可を取る必要があります。自分勝手に撮影することはマナー違反です。宗教者が儀式中の撮影を禁じている場合もあります。
許可を得た場合でも、会場内で騒がしくするなどの空気の読まない行動は慎むようにしてください。
特に、最期のお別れの時間で横から勝手に撮影してしまうと、遺族の方々に不快な思いをさせてしまうかもしれません。
葬儀において「やってもよいのか?」と思うことは、自分勝手に行わず、事前に許可を取るようにしてください。
葬儀で写真撮影をする理由は?
葬儀で写真撮影をする理由を紹介します。
事情は人それぞれですが、具体的な理由は以下のことが多いようです。
葬儀の記録をするため
理由の一つ目は、当日の会場の様子や雰囲気を記録するためです。
やむをえず参列できない方に見せると、葬儀の雰囲気を知ってもらえます。
葬儀当日は、対応しなければいけないことが多く、見落としが出てくる場合もあります。
供物や供花も写真に収めておくと、どのような人がどんなものを贈ってくれたのかなどの振り返りにも役立ちます。
故人との最後の思い出になるから
二つ目の理由は、写真が故人との最期の思い出になるからです。
写真にすると、記憶だけでなくもの(データ)として遺すことができます。
葬儀の状況を後で「見返したい」と思っても、写真を遺しておかないとできません。
最期のお別れになるので、せめて写真を遺しておきたいと考えるのも自然な気持ちでしょう。
ただし、故人が写り込むような状況では、必ず遺族の許可を得てから撮影するようにしましょう。
参列者の把握ができる
三つ目の理由は、誰が参列したのかを把握するためです。
物理的な記録として遺しておくと、曖昧な記憶に頼らなくて済みます。
お礼状の手配や香典返しの準備でも役に立ちます。
芳名帳での確認は「書き漏れ」が出てくる可能性があるので、写真で遺しておくとより正確です。



葬儀社のカメラマンによる写真撮影
プロのカメラマンに葬儀の撮影を依頼する場合の流れを紹介します。
依頼した場合、どのような場面で撮影することが多いのでしょうか。
祭壇前にて集合写真を撮影する
撮影場面の一つ目は、祭壇前にみんなで集まり、集合写真を撮ることです。
参列者や会場の雰囲気を写真に収めることができます。
また、葬儀は遠方に住む親族も参加するため、親戚が一同に集まる貴重な機会になることが多く、思い出の写真として残すことができます。
プロのカメラマンに頼むので、目を閉じていたりブレていたりなどの失敗が少なくなります。
後日、写真を見ながら思い出を振り返ることができます。
葬儀中の写真を撮影する場合もある
二つ目の撮影場面は、「葬儀中」です。
大体の流れを押さえる上でも役に立ちます。
プロが撮るので、自然な表情を引き出したり、式の邪魔にならずに撮影してくれます。
個人で撮る場合、慣れていないので失敗も多く、配慮なく動いてしまって雰囲気も壊しやすいです。
また、焼香やお別れの場面など、親族や参列者が故人に集中するような場面も撮影しておいてもらえます。
葬儀中の写真を撮るケースでは、故人と縁がある方が式に参列できないときに依頼することが多いようです。
親族・参列者による写真撮影
個人が撮影する方法を紹介します。
いくつか気を付けないといけない点があるので、しっかり押さえていきましょう。
必ず遺族・葬儀社・宗教者に撮影許可を取ろう
トラブルを避けるために、必ず遺族・葬儀社・宗教者に撮影許可を取るようにしてください。
自分勝手に撮影してしまうと、注意を受けたり雰囲気を悪くすることがあります。
隅の方で行ったとしても、目立ちやすくなります。
写真撮影は不快な思いをさせることもあるので、その点を心得ておきましょう。
許可をもらっておくと、撮影していても堂々とした対応ができます。
撮影禁止の葬儀もあるため注意
撮影禁止にしている葬儀もあるので注意してください。
許可を取ろうとしても断られることがあります。
その場合は、いかなる理由があっても相手方の指示に従うようにしてください。
撮影禁止にしている理由については、あらゆるトラブルを避けるためと言えます。
禁止であることは大々的に伝えてなくても、注意書きなどに記載されていることもあります。
撮影をする場合は遺族の気持ち配慮する
葬儀の撮影をするときは、何よりも遺族の気持ちに配慮しましょう。
写真撮影が禁止されていない場合でも、人によってはあまり喜ばしい行動には思われません。
撮影の許可が、遺族が渋々の反応のときは、撮らない方がよいかもしれません。
空気を読むことが大切です。
葬儀の写真は特に、人によって考え方にさまざまな違いがあり、写真撮影にはマイナス意見を持つ人もいます。
自分が遺族側だったら、どのような意見を持つか、今一度考えるようにしましょう。



葬儀の写真撮影のマナー六つ
葬儀での撮影で押さえておきたいマナーを紹介します。
周りの迷惑にならないように気を付けてください。
無断で故人を撮影するのはNG
断りもなく無断で故人を撮影するのは控えてください。
遺族に失礼な行為で、会場の雰囲気も悪くなります。
葬儀での故人の姿が写真に遺ることを、あまり好ましく思わない方もいます。
故人と親しかった人であっても、遺族に断りを入れてから写真を撮るようにしてください。
祭壇に背中を向けて撮影するのはNG
祭壇に背中を向けて撮影する行為もマナー違反です。
故人を冒涜する行為とみなされることがあります。
撮影に夢中になってしまうと、祭壇に背中を向けてしまう方もいるかもしれません。
立ち位置に気を付けた上で、撮影するようにしてください。
読経・焼香の邪魔にならないようにする
写真を撮る場合、読経・焼香の邪魔にならないように気を付けてください。
葬儀の進行を妨げる行為とみなされます。
読経・焼香は撮影のベストタイミングとは言えません。また、視野に入るだけで気がそがれてしまうことがあるため、できるだけ避けることが望ましいです。
宗教者によっては、儀式中の撮影を禁じている場合もあるので、事前に必ず確認しましょう。
シャッター音は鳴らさない
シャッター音も鳴らさないように気を付けてください。
最期のお別れのときなどは、雰囲気が悪くなることがあります。
マナーモードにしたつもりでも、予想に反して音が鳴ってしまうこともあります。
そのため、一度試しに写真を撮っておくことが大切です。
撮影を行う場合、最低限のマナーを守りましょう。
フラッシュの使用を控える
フラッシュも控えてください。
葬式場は薄暗いことが多く、目立ちやすいです。
特に年長者の方から好ましく思われません。
フラッシュをオフにしたつもりでも予想に反して光ってしまうこともあります。
そのため、一度試しに写真を撮っておきましょう。
SNSへの掲載は控える
撮影した写真をSNSに載せることは控えてください。
「不謹慎」「マナーが悪い」と思われることがあります。
この場合は、参列者の許可を取らないことも多く、反感を買いやすいです。
写真は個人で楽しむものとして、外へは発信しないようにしてください。
まとめ
葬儀で写真撮影を行うことは可能です。
しかし、遺族・葬儀社・宗教者に撮影許可を必ず取る必要があります。
写真撮影をする理由としては、「葬儀の記録を残すため」「故人との最後の思い出になるから」「参列者の把握」が挙げられます。
マナーは六つあります。
無断で故人を撮ったり、祭壇に背中を向けたりするのはNGです。
読経・焼香の邪魔にならないようにしてください。
シャッター音は鳴らさず、フラッシュは控えて、写真はSNSに載せないようにしましょう。
個人以外にも、葬儀社に依頼しカメラマンに撮影してもらう方法もあります。
マナーを守った上で写真撮影を行うようにしましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。