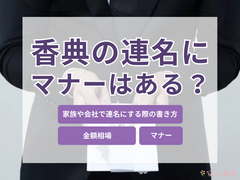陰膳とは?配置・マナーを解説

陰膳(かげぜん)は旅に出かけてその場にいない人のために用意する食事です。
無事を祈る作法ではありますが、現代では死者を偲ぶために行われることが増えました。
陰膳は、どのような手順で行うのが適切なマナーとなるのでしょうか。
今回の記事では、陰膳について、盛る料理や置き方、マナーなどを解説していきます。
陰膳のお供えを考えている方は参考にしてください。



陰膳とは?二つの意味を解説
まず、陰膳について解説していきます。
二つの意味を持つ言葉でもあるので、それぞれ紹介します。
浄土にたどり着くまでの食事
陰膳は亡くなった人が浄土にたどり着くまでの食事としての意味があります。
飢えることなく、無事にあの世に行けるようにという遺族の気持ちが込められています。
仏になる前の霊のために用意する食事であることから「霊供膳(りょうぐぜん)」と呼ばれることもあります。
お盆でも仏壇に食事をお供えすることがありますが、同じように故人を想い、供養するための作法と言えるでしょう。
現代において陰膳は、こちらの意味で捉えられていることが多くなっています。
遠方の家族の無事を祈る食事
一方で陰膳には、旅や戦争などで遠方にいる家族の無事を祈るための食事としての意味もあります。
事故に遭うことなく、無事に帰ってきてほしいという祈りを込めます。
特に戦時中は、多くの家庭で遠方にいる家族を思い陰膳が行われてきました。
しかし現代は、離れていてもさまざまなツールで安否の確認が容易にできるので、この意味合いでの陰膳は減っています。
陰膳の器と配置
ここでは、陰膳で使用する器と配置について紹介します。
作法を踏まえた上で用意していきましょう。
陰膳で使う器の種類
陰膳は、どのような器を使うのでしょうか。
ここでは、器の名称や材質について紹介します。
器の名称
陰膳で使う器の名称は、仏膳椀です。「ぶつぜんわん」と読みます。
主に、食器が五つとお箸一膳が並ぶ形になります。
ご飯用の食器として使われるのが「親椀」。
汁物の食器として使われるのが「汁椀」。
香の物(漬物)を置く食器として使われるのが「高坏」です。
さらに、煮物・和え物用として使われるのが「平椀」。
煮豆や和え物用として使われるのが「壺椀」です。
普段お供えしている湯呑みや茶碗などとは区別した上での紹介になります。
器の名称を覚えて陰膳を用意していきましょう。
器の材質
陰膳の器の材質には、特に決まったものが使用されるわけではありません。
プラスチックから漆塗りのものまで、多様な材質の器が確認できます。
陰膳の器としてセット販売しているものならば、一つずつ購入しなくてよいので簡単に陰膳の器をそろえることができますし、色も総朱のものや外側が黒・内側が朱のものがあるので、好みで購入することができます。
漆塗りと比べて手入れが簡単なプラスチック製のものが選ばれることが多く、陰膳を毎日行う方は、扱いやすさを重視して器を選ぶのがよいでしょう。
選ぶ材質により無礼に当たることはないので、好きなものを使いましょう。
ただし、漆塗りの器を購入するのならば、高い温度と乾燥に弱いので丁寧に扱う必要があります。
陰膳の配置
陰膳の配置については決まりがあるので、しっかり守ることが大切です。
基本的な配置は以下となりますので、参考にしてください。
なお、ここでの左右や手前・奥については、お膳を食する故人側から見た向きになります。
- 「親椀」→「膳の左手前に置く」
- 「汁椀」→「膳の右手前に置く」
- 「高坏」→「膳の真ん中に置く」
- 「平椀」→「膳の左奥に置く」
- 「壷椀」→「膳の右奥に置く」
イメージとしてはサイコロの5の数字の配置で、器を決められた場所に置くようにしてください。
手前の親碗と汁椀の置き方はいずれの宗派でも共通ですが、高坏・平椀・壷椀については宗派ごとに違いがあります。
箸は故人側から見て一番手前に置きます。なお、ご飯に箸を立てるのは葬儀の時の作法になるので注意しましょう。



陰膳に使う料理とは
ここでは、陰膳に使う料理について紹介します。
盛る料理についてはマナーがあるのでしょうか。
陰膳には精進料理を使う
陰膳は、仏教の教えに従って精進料理を使うのが一般的です。
しかし、特に明確な決まりは設けられていません。
そのため、私たちが普段食べている料理をお供えすることもできます。
なお、故人が好きだったものを中心に陰膳に使う料理を決める方もいます。
凝ったものを作る必要はなく、野菜中心の普段の料理を意識してみてください。
陰膳で避けた方がよい食材は?
陰膳で避けた方がよい食材は殺生を連想させるものです。
仏教では生き物を殺すことをタブーとしていることから、牛肉、鶏肉、豚肉、魚、卵といったものは避けられる傾向があります。
獣・魚・鳥といった動物性の食材は、仏教の思想において避けるべき「三厭」と呼ばれています。
また、五葷(ごくん)と呼ばれるものも、できるだけ避けた方がよい食材です。
臭いや刺激が強い食材を指す言葉で、主に、らっきょう、ニンニクなどが挙げられます。
仏教の思想で三厭(さんえん)と並ぶ「禁葷食(きんくんしょく)」の食材として、精進料理では避けるべきとされています。
毎日陰膳を行うと、家族が食べるものと同じ料理を出さざるを得ない場合もあります。
最低限のマナーを押さえた上で、自分に合った方法で陰膳を行っていきましょう。
陰膳の置き方と期間
ここでは、陰膳の置き方と期間について紹介します。
陰膳は祭壇に向けて置く
陰膳は祭壇の方に向けて置くようにしましょう。
自分の向きとは反対に置くことを意識すると、間違えません。
故人が料理を食べることを考えた時、一番奥に箸を置く形になります。
陰膳の置き方は、間違える方が多いので、しっかり理解しておきましょう。
会食・仏壇では位牌・遺影と一緒に置く
陰膳は、会食の席での故人用の食事や仏壇のお供えとして用いられますが、位牌・遺影の前に一緒に置くようにしましょう。
また、陰膳を置く配置は位牌・遺影の前です。
移動を行ったりする際は、混乱することがあるので間違えないように注意してください。
なお、会食の場では故人が上座となるので陰膳から配膳をすることになりますが、地域によっても作法は異なりますので、不安な方は一度確認してください。
陰膳のお下がりは家族で食べる
陰膳のお下がりは家族などで必ずいただきましょう。
少量でも口にすることで供養する意味を持ちます。
陰膳は一度お供えしたものとなるので、そのまま食べるのは失礼に値するのではないかと考える方もいます。
しかし、お供えした後のお膳は全て食べることが本来のマナーです。食べることが故人への供養になると考えられているので、一切箸をつけずに食事を捨ててしまう方がよくないこととされています。完食できなくてもせめて一口でも口にするようにしましょう。
また、陰膳のお下がりは少量ではなく、全て食べても構いません。
陰膳を置く期間は?
陰膳を置く期間は「四十九日」までです。
浄土にたどり着くまでの食事の意味としてお供えするなら、仏様になるまでの期間、置くことになります。
ただし、四十九日を過ぎたら陰膳は行ってはいけないというわけでなく、その後の陰膳は、仏様にお供えする意味に変わるので、そのまま続けても構いません。
四十九日までを一つの区切りとして、できるだけ毎日欠かさず行うようにしましょう。
また、一周忌や三回忌などの法事の会食でも故人のために食事を用意することがあり、「供養膳(くようぜん)」などと呼ばれます。



陰膳の注意点
ここでは、陰膳の注意点について紹介します。
陰膳の必要がない宗派がある
陰膳を行わない宗派があるので、それを確認してください。
仏教では、四十九日まで陰膳を行うと極楽浄土にたどり着けると言われ、故人が無事に極楽浄土にたどり着けるように影膳を用意しますが、同じ仏教の宗派の中には陰膳を必要としない宗派があります。
浄土真宗では「往生即成仏」といわれ、亡くなった直後に仏様に変わると捉えられているので旅の過程がなく、陰膳を行う習慣もありません。
陰膳の作法は宗派・地域で変わる
陰膳の作法は宗派・地域によっても変わることがあります。
事前に押さえていたポイントとは違うということもあるので、不安な方は作法に詳しい方に確認するとよいでしょう。
まとめ
陰膳は「浄土にたどり着くまでの食事」と「遠方の家族の無事を祈る食事」の二つの意味があります。
しかし現代においては、さまざまなツールを使うことで遠方の家族とも気軽にコミュニケーションが取れることから、前者の意味として取り扱われることが多くなっています。
陰膳には、五つの食器と一膳の箸を使います。
器の配置としては、親椀は「膳の左下」、汁椀は「膳の右下」、高坏は「膳の真ん中」、平椀は「膳の左上」、壷椀は「膳の右上に置く」のがマナーです。
盛る料理は、精進料理が選ばれていますが、家族と同じメニューでも構いません。
陰膳を置く期間は、「浄土にたどり着くまでの食事」という意味では四十九日までです。
お下がりを少量でも家族が口にすると、供養の意味を持ちます。
注意しないといけないのは、陰膳は宗派や地域によっても作法が異なることがあるということです。不安な方は、詳しい方に相談して確認してください。
一番大切なことは故人への想いや供養の気持ちです。家族と同じ普段の食事や故人が好きだった物をお膳にするなど、柔軟な考えで心を込めて食事を用意するとよいでしょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。