埋葬料の請求手続きの方法とは? 葬祭費も合わせて解説

お葬式の費用はなかなか予期したくないものですが、出費については考えておかなければなりません。同時に公的な支援としての「給付金」があることを知っておきましょう。
家族の逝去によるお葬式に伴う費用として、家計への負担を軽減するために「埋葬料」と「葬祭費」という給付の制度がありますが、意外に知られていないのが実情です。
本記事では、「埋葬料」と「葬祭費」とは何か、それぞれの給付を請求するための申請方法、「埋葬料」と「葬祭費」の違いなどについて解説します。



埋葬料とは?
埋葬料とはどのような性質の給付金であり、どういった場合に請求が可能なのでしょうか。
埋葬料は健康保険による給付金
埋葬料は、故人が生前、会社員として組合健保や協会けんぽに加入していた場合に健康保険から給付される給付金です。埋葬費用(葬儀費用)の一部を健康保険が負担します。
受給者は遺族に限らない
埋葬料が給付される対象者は、亡き被保険者の収入により生計を維持しており、かつ故人の埋葬(葬儀)を行う者とされています。
家族の誰かが対象者となるケースが一般的ですが、受給者は遺族に限らず、条件に当てはまりさえすれば親族や血縁者以外でも請求が可能です。
埋葬料は一律だが、給付総額は必ずしも一律ではない
給付される埋葬料の「法定給付」は一律5万円と定められています。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。
葬儀を行うか行わないかに関わらず給付される
埋葬料は、被保険者の死亡を受けて給付されます。つまり、まだ葬儀を行っていない場合や行う予定がない場合でも請求が可能です。
扶養家族が亡くなった場合も同様の給付を受けられる
被扶養者が亡くなった場合には、「家族埋葬料」と名称は変わりますが、同額の給付金が給付されます。
資格喪失後でも請求が可能なケースもある
故人(被保険者)がその資格を喪失した後であっても、次の場合には埋葬料を請求できます。
■被保険者がその資格喪失後(退職後)3カ月以内に亡くなった場合(資格喪失前の加入期間の長さは問われない)
■被保険者がその資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている期間中、または当該給付を受けなくなってから3カ月以内に亡くなった場合
なお、被保険者の扶養家族が亡くなった場合に給付される家族埋葬料は、被保険者の資格喪失後には請求できません。
申請から受給までの期間と受け取り方法
埋葬料は故人が生前加入していた健康保険組合(もしくは社会保険事務所)へ申請してから2~3週間ほどで受給できますが、申請書類の内容に不備があると書類の再提出が必要となるため、受給までが遅れる可能性があります。
埋葬料の受け取り方法は、申請書類に記載した口座のみに限られ、現金での受け取りはできません。また故人名義の口座は、死後一定期間は凍結されるため、申請書類には申請者名義の口座を記載するようにしましょう。
葬祭費とは?
故人が生前、自営業者などで国民健康保険に加入していた場合は「埋葬料」ではなく「葬祭費」が給付されます。名称は異なりますが、その性質や意味合いは埋葬料と同じです。
ただし、埋葬料が一律5万円(付加給付分を除く)であるのに対し、葬祭料の金額は自治体によって異なります。自分が住んでいる自治体の状況を確認しておきましょう。
また、埋葬料が被保険者の死亡を受けて給付される一方、国民健康保険から給付される葬祭費はあくまで「葬祭」に対し給付されるものです。お葬式と火葬・埋葬に対しての支援ということになります。
葬祭費の申請は葬祭を執り行ってから2年以内に行う必要があり、2年を過ぎると受給資格を失います。



埋葬費、葬祭料の違い
埋葬料・葬祭費とよく似た名前で「埋葬費」や「葬祭料」というものがあります。埋葬料・葬祭費との違いはどこにあるのでしょうか。
埋葬費
埋葬費は、埋葬料(生計維持に関係ある人)の支給を受ける者がおらず、かつ故人の埋葬(葬儀)を行った者に対して給付されます。
葬儀費用に関しては、上限を5万円として支給されます。一律ではないので注意が必要です。
例えば、故人が独身であり、その埋葬を行ったのが生計を一つにしない弟であった場合、その弟は埋葬料の給付対象ではありませんが、埋葬に掛かった実費を埋葬料の範囲内で埋葬費として請求できます。
葬祭料
勤務先での労働災害で亡くなった場合は、労働基準監督署に必要書類をそろえて請求することにより、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。葬祭料は以下の二つの計算により算出された額の高い方の額が支給されます。葬儀費用として支出した実費全額が支給されるわけではないので注意してください。
- 給付基礎日額 × 30日分 + 31万5000円
- 給付基礎日額 × 60日分
なお、亡くなった日の翌日から2年を過ぎると請求する権利が失効してしまうため、早めに手続きしましょう。
埋葬料の請求に必要なもの
埋葬料を受給するには、申請が必要になります。申請に必要な書類としては下記のようなものが挙げられます。
健康保険組合によっては、事業主による証明があれば書類添付が不要となったり、被扶養者以外が申請する場合には住民票の添付が必要になるケースもありますので、確認が必要です。
健康保険埋葬料(費)支給申請書
健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。直接配付してもらう他にも、健康保険組合のウェブサイトから書面をダウンロードできます。あらかじめ必要事項を記入しておきましょう。
健康保険証
故人(=被保険者)の健康保険証を提出します。被保険者の死亡により同保険証は返納することになります。
火葬許可証もしくは埋葬許可証、または死亡診断書
すでに役所に死亡届を提出してある場合、火葬許可証もしくは埋葬許可証が発行されているはずなので同許可証を提出します。死亡届提出前であれば、医師により発行された死亡診断書を提出します。
なお、これらの提出書類は原本である必要はなく、コピーでも構いません。
関連記事

火葬許可証とは?発行方法や提出先について解説
「火葬許可証」は、故人の火葬を行う際に必要となる公的な書類です。 とても大切な書類ですが、実際に遺族として経験しないと、発行の手続きや提出先などについては、分かりにくいのが現状です。 この記...
続きを読む
葬儀費用の領収書、葬儀を行った事実と金額が分かるもの
埋葬料の給付対象者(被保険者の収入により生計を維持しており、かつ故人の埋葬を行う者)がいない場合、実際に埋葬を行った人が埋葬料ではなく埋葬費の給付を申請することができます。
埋葬費はその実費が埋葬料の金額の範囲内で給付されるため、関連する証明資料が必要です。埋葬に要した費用(霊柩車代、火葬料、僧侶へのお布施など)の分かる領収書や、その内訳の分かる明細書類を提出します。



埋葬料請求の申請方法と期限
埋葬料を申請する方法、申請期限について確認しておきましょう。
申請先は健康保険組合(または社会保険事務所)
埋葬料を給付するのは健康保険ですので、請求するための申請先は故人が生前に加入していた健康保険組合(または社会保険事務所)です。
なお、故人が生前、国民健康保険に加入しており葬祭費を請求する場合の申請先は役所です。
申請は2年以内に
申請期限は死亡の翌日を起算日として2年以内と定められています。とはいえ、各健康保険組合からは死亡後すみやかに申請するよう呼び掛けられています。
また、時間がたつほど記憶もあいまいになり書類も紛れがちとなるものですので、早めに手続きをするようにしましょう。
国民健康保険に加入している場合、故人の健康保険証を役所へ返却する必要があるため、その際に一緒に申請するとよいでしょう。
申請を希望する人が申請が困難な場合は代理人が申請を行う事が可能です。この場合には、委任状が必要となりますので注意してください。
なお、埋葬料の受給要件を満たす者がいない場合に請求が可能な埋葬費については、埋葬の事実が前提となる関係上、申請期限の起算日は「埋葬を行った日の翌日」となります。
まとめ
悲しみに暮れる中でも葬儀の費用を工面することは必要で、少額であっても給付金はありがたいものです。
何もしなくても自動的に支給される制度もありますが、特に「葬祭費」は自主申告により給付される性質の給付金です。慌ただしい中ですが申請を忘れないようにしましょう。
「葬儀は行わないから」「故人と生前に同居していなかったから」といった理由から請求しないという方もいるかもしれませんが、そうした事情は埋葬料給付の要件とは一切関係がありません。
まずは故人が生前に加入していた健康保険組合に確認するか、行政書士・司法書士などの有資格者に聞いておくとよいでしょう。役所の保険関係窓口でも相談に乗ってくれます。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。










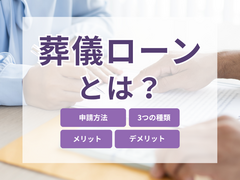










給付金の関係は、相続などとも連動することもあるので、できれば有資格者である士業の専門家に相談することをお勧めします。また自己申告や期限などもあることを忘れないようにしてください。