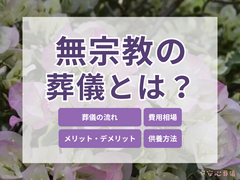天台宗の葬儀とは?葬儀の流れやマナーを解説

日本で営まれる葬儀の多くが仏教式で行われていますが、仏教式と言ってもたくさんの宗派があり、それぞれで葬儀の仕方が違います。中でも天台宗の葬儀は、他の宗派の葬儀とは異なる特徴が見られます。
天台宗の知り合いが亡くなったときに、どのような葬儀を営むのかに迷うことがないように、天台宗について、そして天台宗の葬儀の特徴や進行方法について知っておくことが大切です。
葬儀に参列するときのマナーや、天台宗の儀式に欠かせない梵音具(ぼんおんぐ)も含めて、この記事で解説します。



天台宗の葬儀とは?
天台宗の葬儀には他の宗教宗派と違った葬儀の特徴があります。
ここでは天台宗の葬儀の特徴について詳しく紹介していきます。
天台宗の葬儀の特徴
天台宗の葬儀では、「顕教法要(けんぎょうほうよう)」「例時作法(れいじさほう)」「密教法要(みっきょうほうよう)」の三つの儀式が大切にされています。
顕教法要では「法華経(ほけきょう)」を唱え、日々の懺悔を行い、生前の罪を軽くします。人は仏の子どもで仏性に属していると考えられており、懺悔することで仏性を高める意味があります。
次に行われる「例時作法」では「阿弥陀経(あみだきょう)」を唱え、死後に極楽に行くように祈願するとともに、現世を極楽のように素晴らしい世界にするという願いも込められています。
最後に「密教法要」は、定められた印を結び、「光明真言(こうみょうしんごん)」を唱えます。故人は、この真言を受けることで光明を得て、重罪を滅ぼし、離苦得脱(りくとくらく:苦しみから離れて、楽しみを得る)の多くの幸福をもたらす善行があると言われています。
加えて、故人が極楽浄土へ引導されることも祈ります。
また天台宗の掲げる経典は法華経です。通夜では法華三昧(ほっけざんまい)を行うのも特徴です。
他にも、「剃度式(ていどしき)」と呼ばれる出家をするために髪を剃る儀式が行われます。ただし実際に剃ることは少なく、剃るまねをする場合も多くなっています。
剃度式を行うことで授戒を受け、故人に戒名が与えられます。
天台宗の発祥と教え
天台宗とは大乗仏教の一つで、法華経を経典としています。平安初期に、最澄(さいちょう)によって開かれました。本山は比叡山延暦寺です。
天台宗は、隋の僧侶・智顗(ちぎ)によって六世紀に興された中国天台宗の教えを基にしています。その智顗が説いた教えの中にある「教観ニ門(きょうかんにもん)」と「教相判釈(きょうそうはんじゃく)」という教えは、今も天台宗の根幹をなしています。教観ニ門は、お釈迦様の教えを研究する「教相門」と教えを実践するための修行や決まりごとをあらわした観心門の二つからなり、智顗はこの二つを自転車の車輪のように喩えていて、どちらが欠けても進めなくなるので、この二つとも軽んじてはいけないと説いています。
中国から日本に天台宗を伝えたのは確かに最澄ですが、中国の教えをそのまま移入したわけではありません。天台の教えに加えて密教・禅・戒律の教えも受け継ぎ、この四つの教えをまとめることで日本独自の天台宗を作りあげました。
さらに、後には最澄の弟子・円仁(えんにん)によって浄土教の「念仏」も加えられることになります。最澄は仏教のさまざまな教えの区別に囚われず法華経」の教えを基に全てを統一しようとしました。最澄は、誰もがみな平等に仏になれるという一乗思想の考えを重視していたのです。
また、鎌倉仏教と呼ばれる宗派のうちの多くが、天台宗の影響を受けて派生しました。天台宗の教えは、「全ての人は仏の子だ」ということです。
自分にはその仏性があり、仏であることを自覚することが大切です。悟りに至るための方法は全ての人々に開放されているので、その仏性を自ら磨きます。
そして自分自身を磨くことで周囲も照らされ、光り輝く人々がつながることで、素晴らしい世界を築くことを目指そうというものです。
天台宗の葬儀の特徴的な三つの儀礼
天台宗の葬儀では、故人と参列者全員が一緒になり祈ることで成仏ができるという考え方に基づいています。
この考えを実現するために、天台宗では仏の教えを、「顕教(けんぎょう)」と「密教(みっきょう)」の二つに分け、そこから三つの儀礼が生まれました。顕教とは、お釈迦様が聞く人の能力に合わせて、わかりやすい言葉で顕(あらわ)に説かれた教えであり、密教とは、大日如来が真理そのものの現れとして究極の秘密の教えを示したものです。
その儀礼とは、顕教から生じた「法華懺法(ほっけせんぼう)」と「例時作法」、そして密教を基礎とした「密教法要」です。
法華懺法とは自らの罪を懺悔する儀礼
法華懺法とは、天台宗の根本の経本である「法華経」を読むことで、自らの罪を懺悔します。法華経は「サッド・ダルマ・プンダリーカ・スートラ」という仏教の経典で、意味は「妙法・蓮華(白)・経」となります。
法華経には多くの本訳書が存在しますが、最も有名な翻訳は羅什訳の「妙法蓮華経」です。仏教発祥の地インドでは大きく扱われなかった法華経ですが、大乗仏教の伝わった中国や日本では、重要視される経典となり、特に天台宗においてはバイブル的な存在となって、古くから宗派の垣根なく読まれてきた経典です。
ここでいう罪とは、差別したり、一つのものに執着して他を恨むなど、「全ての存在は平等である」という根本的な理念に反した行動や考えのことです。
こうした罪を犯すのは私たちの心の中に煩悩があるからで、この煩悩により本来あった仏となれるはずの仏性が隠されています。法華懺法により自分の罪を懺悔すれば、この仏性が自覚されます。
例時作法とは極楽浄土で往生することを願う儀礼
天台宗では「朝題目夕念仏(あさだいもくゆうねんぶつ)」という言葉の通りに、朝の勤行時には「法華懺法(ほっけせんぼう)」=題目を読み、夕方の勤行時には「例時作法」=念仏を読むことになっています。
例時作法は、阿弥陀経を中心として、いくつかのお経で構成され阿弥陀様の救いを求める意味があります。例時作法では「南無阿弥陀仏」と念仏を唱え、仏様のいる極楽浄土で往生することを願います。
密教法要で最も有名なのが光明供
密教法要の中で最も親しまれているのが「光明供(こうみょうく)」です。葬儀でもまず光明供が執り行われて葬送の儀へと移ります。
光明供では、「光明真言(こうみょうしんごん)」を念誦(ねんじゅ)して、故人が極楽浄土へと導かれることを祈ります。

天台宗の葬儀の式次第
天台宗の葬儀の式次第とは仏になり極楽浄土へ導く儀式
天台宗の葬儀には、法華経、阿弥陀経または光明真言がそれぞれ主体となった葬儀方法があります。
その中でも一般的なのが「阿弥陀経」を主体とした葬儀式で、故人を極楽浄土へと導きます。「阿弥陀経」とは、浄土教における根本聖典であり、鳩摩羅什が漢訳した「無量寿経」と「観無量寿経」とともにに「浄土三部経」の一つに数えられています。無量寿経を「大経」と呼ぶのに対して、阿弥陀経は「小経」と呼ばれます。
原本はサンスクリット語で書かれていて、現在は日本に伝えられたものだけが残っています。漢訳は、日本では玄奘が訳したものより鳩摩羅什訳のほうが用いられ、特に浄土教諸宗派では、所依の根本経典として扱われています。
しかし、極楽浄土へ導かれるには、故人が仏にならなくてはいけません。天台宗の教えでは、全ての人が仏性を持っているため、必要な儀式を行えば仏となることができるのです。
天台宗の葬儀では、故人が仏となるための儀式から、浄土へと導かれるまでの儀式を全部で五つ行います。
ただし、式次第の内容は地域によって異なり、また葬儀によっては式次第の一部を省略することがあります。
そのため、天台宗の葬儀を行う場合は、具体的な内容は葬儀関係者と確認が必要です。
ここでは、五つの式次第の特徴を紹介していきます。
五つの式次第
- 「剃髪式(ていどしき)」
故人が仏の元に出家するための準備をする儀式です。故人の体を水と香で清めた後、髪の毛を剃ります。
現在の葬儀では実際に髪を剃ることはなく、形式的に髪に剃刀を当てるしぐさによって煩悩を払います。この儀式によって、故人が仏教に入信し、仏となる準備が整ったと解釈します。 - 「誦経式(ずきょうしき)」
「阿弥陀経(あみだきょう)」を読み、故人が仏の恵み(功徳)によって悟れるように祈ります。 - 「引導式(いんどうしき)」
主に光明供から故人に法語を与えて、涅槃(ねはん:悟り)の世界に行くように故人を諭すための儀式です。 - 「行列式(ぎょうれつしき)」
故人が西方にある極楽浄土へ向かうことを象徴した儀式です。 - 「三昧式(さんまいしき)」
三昧式は、故人が心を落ち着かせて安定した境地へと入ることを表す儀式です。「三昧」とは仏教用語で、「心を一つに集中して動揺しない様子」という意味です。
具体的に「三昧式」では、参列者全員が法華経を唱えます。そして参列者の心を静めて、葬儀に集中するように気持ちを整えます。



天台宗の葬儀の流れ
天台宗の葬儀はどのように進んでいくのでしょうか。
ここでは天台宗の葬儀の式次第について紹介します。
天台宗の葬儀式の次第
- 臨終誦経(りんじゅうじゅきょう)
- 通夜
通夜読経
剃度式(辞親偈・懺悔文・授三帰三竟の順番に唱えられる)
授戒式 - 葬儀
導師の入場
光明供修法(こうみょうくしゅほう)
九条錫杖(くじょうしゃくじょう)
随法回向(ずいこうえこう)
列讃(れっさん)
鎖龕(さがん)・起龕(きがん)・奠湯(てんとう)・奠茶(てんちゃ)・歎徳(たんどく)
導師による下炬文(あこぶん)
弔事・弔電の読み上げ
読経
法施
念仏・光明真言・向口文の読み上げ
総回向
導師の退場
出棺
同じ宗派の式でも、地域や寺院によって内容や式の順番などが異なる場合があります。
疑問点がある場合は、事前に葬儀社や寺院に確認しておくと安心です。
次の記事から、これらの内容を詳しく解説します。
通夜の流れ
天台宗の通夜では、主に遺族が出席して営まれます。ここでは一般的な天台宗の通夜の進行について紹介します。
- 臨終誦経(りんじゅうずきょう)
通夜前日の臨終誦経では、故人の枕もとで枕経が読まれます。故人が極楽浄土へ往生できることを祈願して、「阿弥陀経」が読経されます。 - 通夜読経(つやどっきょう)
通夜の当日、朝と夕方にお経が読まれます。朝は「法華経」を読みながら精神を集中させる「法華三昧」が行われ、夕方になったら「阿弥陀経」が読まれます。
ただ「阿弥陀経」が読まれるときは、例時作法にのっとって行われるため、その抑揚は緩やかなものになります。 - 剃髪式
「阿弥陀経」が読まれた後、剃髪式が執り行われます。故人が仏門に入門するための儀式で、故人に引導を渡すための僧侶である導師によって行われます。
故人の頭に剃刀が当てられて「辞親偈(じしんげ)」が唱えられます。これにより家族との縁を断ち出家することを誓います。
続いて「懺悔文(ざんげもん)」が読まれ、故人の過去の行いを懺悔し、最後に「授三帰三竟(じゅさんきさんきょう)」が唱えられて、仏・法・僧の三宝に帰することを誓います - 授戒式(じゅかいしき)
最後に、戒名を故人に与える授戒式が行われます。「授円頓戒(じゅえんどんかい)」では、「円頓戒」という天台宗だけでなく浄土宗にも伝えられる最高の大乗戒(だいじょうかい)が与えられます。
それに続く「位牌開眼式(いはいかいがんしき)」では、位牌に読経をして故人の魂を移します。
葬儀式の流れ
天台宗の葬儀式には、親族などの遺族以外にも会葬者が出席して執り行われます。
葬儀式の流れは地域や僧侶によっても異なりますが、ここでは一般的な光明真言による光明供が取り入れられた儀式の流れを紹介します。
- 導師・衆僧入堂
参列者が全員着席の下、導師が入堂します。 - 列讃(れっさん)
開会の辞の後に行われる列讃では、穏やかな楽曲が流れる中、故人の臨終を告げる声明(しょうみょう)が唱えられます。 - 光明供修法(こうみょうくしゅほう)
阿弥陀如来を迎え入れて、故人を仏とするための儀式です。 - 九条錫杖(くじょうしゃくじょう)
法具である錫杖の徳を述べていきます。その際、各条ごとに僧侶が始めの句を唱えるので、参列者はその後を斉唱します。 - 随行回向(ずいこうえこう)
故人の成仏を祈り供養をするための声明が唱えられます。 - 鎖龕(さがん)と起龕(きがん)
列讃が再度行われた後、棺の蓋を閉じる「鎖龕」の儀式が執り行われます。そして起龕によって棺を起こす儀式が続き、故人を浄土へと送る準備が整えられます。 - 奠湯(てんとう)と奠茶(てんちゃ)
奠湯と奠茶の儀式により、故人に茶が供えられます。 - 引導
「歎徳(たんどく)」によって故人の生前の業績が讃えられた後、導師は霊前に進み出ます。
そして「菩薩戒偈」と呼ばれる菩薩としての心構えを唱えたあと、「引導」により「故人が成仏できるように」と祈って、浄土へと導かれます。 - 下炬(あこ)と参列者による焼香
導師が松明か線香を手にして、円を描きながら宙に梵字を結びます。そして故人を讃える「下炬文(あこぶん)」が読み上げられます。
その後、読経されるので、その間に参列者が焼香を行います。 - 弔辞拝受と弔電拝読
焼香の後、他の葬儀式と同じように、弔辞を承り弔電が拝読されます。 - 法施(ほうせ)
再び、読経が行われます。 - 念仏または光明真言
念仏または、光明真言が読み上げられます。 - 総回向
回向文が読み上げられて、葬儀が終了します。 - 導師退場
導師が退場します。 - 出棺
出棺が行われます。
上記の儀式とは別に、天台宗では「散華(さんげ)」という儀式が執り行われることもあります。
僧侶が棺に花びらや花びらに模した紙をまくことで、仏が来迎したときに仏をたたえるという意味や、仏が説法を解いたときに天から花が降ってくるという言われを再現した儀式です。
告別式の流れ
告別式は、故人との別れを惜しむための集まりとして、葬儀式とは別に行われる習慣がありました。
しかし最近では、告別式は葬儀式の中で済まされる傾向があります。
告別式が葬儀式の中で行われるという傾向は、どの宗派の葬儀でも言える傾向です。
それでは、天台宗の告別式の進行について紹介します。
- 僧侶が入場した後、開会の辞が読まれます。
- 列讃が行われた後、「阿弥陀経」が読経されます。
- さらに「観音経」と続いた後、「鐃鈑打流し(にょうはちうちながし)」というシンバルのような楽器が打ち鳴らされます。
- 僧侶が退場します。
- 親戚代表者などが挨拶をして、告別式が終了します。

天台宗の葬儀マナー
天台宗では他の宗教宗派と異なる葬儀のマナーがあります。
焼香や数珠の使い方など詳しく解説していきます。
焼香の作法
焼香の回数に決まりはない
焼香とは、香を焚くことで故人を悼み拝むことです。参列者の全員が行い、天台宗の葬儀における焼香の回数は基本3回となります。
ただし、必ず3回でなくてはならないという決まりがないので、1回でも構いません。
焼香の順序:抹香の場合
焼香の順番が来たら、焼香台まで進み出て、合掌礼拝をします。
右手の親指と人差し指、中指で香をつまみ、左手を添えて、額の辺りまで掲げます。そして香を香炉の中に落とします。
この一連の動作を1回~3回行い、最後に合掌礼拝をして焼香を終えます。
焼香の順序:線香の場合
抹香の代わりに線香で焼香をする場合は、合掌礼拝の後、線香を3本取ってろうそくから火をつけます。手であおいで火を消し、香炉に立てます。
一本を香炉の中心に、残りの2本をその奥に立てるようにします。
また線香の数は、3本の代わりに1本でも構いません。その場合は香炉の中心に立てるようにします。
最後に合掌と礼拝をして、焼香を終えます。
数珠の種類と使い方
天台宗で用いる数珠の種類
天台宗で用いられる数珠は、楕円形をした玉が結び合わさったものです。煩悩の数と同じ108つの主玉に、四つの天玉が付いています。
さらに親玉も付いていて、その親玉からは紐が伸び、その先には弟子玉と呼ばれる玉が付いている独特な形容をした数珠です。男性用は9寸、女性用には8寸の長さの数珠が一般的です。
数珠の持ち方
数珠は左手に持ち、合掌の際には、親指と人差し指の間に数珠をかけて、数珠の残りは弟子玉が付いている房の部分が下に来るように垂らします。
天台宗ではない参列者は、自身の宗派の数珠か、宗派を超えた簡易式の数珠を持つことができます。一般参列者ならば数珠を持たなくても構いません。
葬儀に参列するときの服装
親族は正喪服か準喪服
親族なら正喪服が葬儀に参列する場合の正式な服装ですが、準喪服も認められています。
男性の正喪服とは、洋装ならば黒のモーニングコートにレギュラーカラーの白シャツ、黒を基調としたコールパンツを合わせます。
正喪服の代わりに、準喪服となるブラックスーツを着用することもできます。ネクタイやベスト、靴下、靴もすべて黒で統一します。
女性の洋装の正喪服は、ブラックフォーマルウエアで、黒無地で光沢感のないワンピースやアンサンブルです。ストッキングや靴も黒で統一します。
華美なアクセサリーを身に着けることは避ける
アクセサリー類は結婚指輪を除いて、身に着けないようにします。
真珠なら大丈夫とされていることもありますが、一概には言えませんので、必要がなければ身に着けないほうが無難でしょう。



天台宗の葬儀での香典について
天台宗ではどのように香典を準備すればよいのか、詳しく解説していきます。
表書きについて
天台宗では香典の表書きは「御霊前」と書きます。
もし四十九日を過ぎてから渡す場合は「御仏前」とし、四十九日か分からないときは「御香典」にするのがよいでしょう。
香典の相場
香典の金額は故人との生前の関係によって変わってきます。
友人や会社関係者は3000円~5000円、親戚や取引先の人は1万円、おじおば・祖母・祖父は1万円~3万円、きょうだいは3万円~5万円、両親・義理の両親は10万円が一つの目安になります。
さらに香典の金額によって、香典袋も変わってくるので注意が必要です。
香典が1万円以内なら、水引が印刷されたシンプルな香典袋でもよいですが、3万円以上になる場合は印刷ではなく水引がついているタイプを選びます。
香典に入れるお札は古いものや新札を一度折り曲げたものを入れるのがマナーです。決して新札を入れることのないようにしましょう。
天台宗の葬儀に参列するときの服装
天台宗の葬儀に参列する場合の服装のマナーは一般的な葬儀と同じで構いません。
そのため、特に案内がなければ、正喪服か準喪服を着用しましょう。
男性の場合は正喪服は和装かモーニングコート・白シャツ・コールパンツを着用します。
準喪服のときはブラックスーツを着用すれば問題ありません。
靴下、ネクタイ、靴、ベストも黒でそろえるようにし、ネクタイピンは使用しないようにしましょう。
女性の場合はブラックフォーマル、ワンピース、アンサンブルが基本です。
過度な肌の露出はマナー違反になるので、スカートの丈は長すぎず短すぎない膝下からふくらはぎの丈のものを選びましょう。
ストッキングや靴も黒色を着用します。
男女ともに派手なアクセサリーは避けるようにし、結婚指輪や婚約指輪以外は基本的に外しましょう。
女性であれば、パールのピアスやネックレスであれば着けることができます。ただし不幸が重なると考えられることから2連や3連のものは避けるようにしましょう。
メイクも派手になりすぎないナチュラルメイクにして、髪が長い場合は後の低い位置で束ねるようにします。



天台宗の葬儀で渡すお布施
お布施の相場
読経と戒名を付けてくれたお礼として渡すのが、お布施です。
お布施の相場は約15万円~20万円と言われていますが、地域や寺院との関係などで変わってくるため、あまり参考にはならないでしょう。
お布施料をいくらにするのか見当がつかない場合は、まずはお寺に相談してみましょう。それができない場合は、お寺との関係が長い方に問い合わせてみるか、葬儀を引き受ける葬儀社の担当者に聞くのがよいでしょう。
戒名料の相場
お布施とは別に戒名料も渡します。戒名料とお布施を一緒にして渡すことが多いのですが、戒名料は一般的には戒名の長さや位によって異なります。
最も一般的な戒名は男性なら「居士」、女性なら「大姉」を入れた戒名で、相場は約50万円~70万円だと言われています。
これよりも安く済む戒名で「信士・信女」が約30万円~50万円、最も長い戒名の「院居士・院大姉」なら100万円を超えると言われています。
戒名を付ける寺院によっても戒名料は変わってくるので確認しましょう。
お布施の包み方
お布施の包み方には、「奉書紙」か「白無地の封筒」を使う二通りがあります。
「奉書紙」の場合
最も丁寧な包み方が、奉書紙を使った方法です。お札を半紙で包み、中包みにします。その中包みを奉書紙で包みます。
奉書紙の折り方は、慶事の上包みと同じく、折り返す部分の上側を下側で被せるようにします。
御布施袋の場合
一般的には白無地の封筒か、「御布施」と表書きされた市販の袋を用いるのが多いでしょう。中袋がある場合はそれにお札を入れて、金額や住所氏名などを記入します。中袋がない場合は直接お札を入れても構いません。
また、水引は黒白や双銀を用いますが、必要ないとする考え方もあります。不幸が起きたのはお寺ではないからです。
お布施の渡し方
お布施は、直接手渡しをするのではなく、小さなお盆などに乗せて僧侶に渡します。渡すタイミングですが、葬儀前の挨拶のときか、別れ際の挨拶のどちらでも構いません。
もしも僧侶がタクシーなどで来た場合は、お車代として約5000円~1万円を別途包みます。僧侶への交通費はお布施に含まれないためです。封筒に「お車代」と表書きをして、お布施と一緒に渡します。
また僧侶が会食に参加しない場合は御膳料も一緒に渡しましょう。
関連記事

お布施をお渡しする際の挨拶とは?その際のマナーも紹介します
寺院にお布施を納める機会は葬儀や法要くらいで、そうそう頻繁にあるものではありません。そのため「お布施を渡すときの挨拶やマナーはこうだ」と自信を持って言える方は少ないのではないでしょうか。 特に...
続きを読む
天台宗の葬儀で唱えられるお経

天台宗の葬儀で唱えられるお経には三つ種類があります。
それは「法華経」「阿弥陀経」「般若心経」です。この三つのお経にはどのような意味が込められているのかを紹介します。
法華経
「法華経」は、大乗仏教の代表的な経典です。法華経では「誰もが平等に仏になることができる」と唱えられています。
天台宗を開いた最澄は、この教えを最も大切にしていたとされています。
阿弥陀経
「阿弥陀経」は、天台宗の全ての教えが詰め込まれています。
故人はこの世を去り、浄土で生まれ変わることを願います。
般若心経
「般若心経」は、世界でも有名なお経の一つで、仏教の全経典の中でも一番短いお経の一つでもあります。仏様に故人の死を告げて祈るために唱えます。



天台宗の葬儀で使う仏具
天台宗の葬儀では、密教由来の音の鳴る仏具「梵音具(ぼんおんぐ)」が使われます。ここではそれらの梵音具について、素材や使い方を紹介します。
大徳寺りん
「大徳寺りん」とは、読経に使用される鐘です。その「りーん」となる澄んだ音が、極楽浄土まで届き、仏様にも聞こえると考えられています。
「りん」は「鈴」や「輪」とも書き、その書き方は定められていません。
また「りん」などの鐘は、お堂の中で使われるものは「磬子(けいす)」と呼ばれています。
「大徳寺りん」の鐘は青銅製で、形状はつぼ状や鉢状になっているものが一般的です。大きさは口径が15㎝~45㎝ほどまで、いろいろあります。
「りん」には鋳造されていないのもありますが、「大徳寺りん」は鍛造されています。
りんはりん台の上に置かれて、「倍(ばい)」と呼ばれるバチで鳴らします。横からりんの脇を軽くたたくようにすると、透き通ったきれいな音が出ます。
大徳寺りんを鳴らすことで、空間を清めて邪気を取り除くためにも使われます。
木魚
「木魚(もくぎょ)」はりんと同じく、読経の際に用いられる梵音具です。木魚を鳴らすのは読経のリズムを取るためや眠気覚ましという意味合いもあり、精神統一のためにも使われます。また木魚の口には「煩悩の珠」があしらわれ、煩悩を吐き出す意味でも使われていました。
元来の木魚は、魚の形をした「魚板(ぎょばん)」でした。なぜ「魚板」が魚の形をしているのかというと、「魚のように目を開けて、寝る間も惜しんで精進するように」という意味合いが込められていたからです。
その魚板が変形して円形となった木魚には、今でもその表面に魚のうろこなど魚のデザインが施されたものがあります。
ちなみに木魚は、天台宗だけでなく浄土宗や禅宗でも用いられていますが、木魚を使わない宗派もあります。
宗派ごとに木魚の違いはなく、素材は楠や桑が主流です。また木魚は、木魚専用の布団の上に乗せて使われます。
妙鉢
「妙鉢(みょうばち)」は、天台宗の葬儀式で使われるシンバルのような楽器です。天台宗以外でも、浄土宗や真言宗などで使われています。
別称は「バチ」で、「ドラ」と呼ばれることもあります。妙鉢は、中国から伝わり、宮中などで演奏用の打楽器として使われていたのが、寺院でも使われるようになりました。
妙鉢を打つことで邪気を払い、心を清めるなどの意味があると同時に、他の仏教楽器と同じく、人々の関心を向けさせるという意味も含まれています。
葬儀などの法要では、妙鉢を鳴らすことで仏様をお迎えし、もう一度鳴らすことで、仏さまを涅槃へお返しするという役割で使用されます。
妙鉢の鳴らし方は、シンバルのようにお互いをたたきつけた後、残音を長くするためにお互いをこすりつけるようにします。
木でできているため「カンカン」と軽い音が鳴るのが特徴です。
銅鑼
「銅鑼(どら)」も梵音具の一つで、法要で使われるときは妙鉢の合いの手として打ち鳴らされます。金属製の皿型の金属板を、専用のバチである「倍」でたたきます。
葬儀の参列者などの見送りの合図に使われたり、法要の際にも使われます。
銅鑼は、天台宗では儀式内で使われていますが、広くは仏教音楽からチベット仏教などの他の仏教でも使われています。
懺法太鼓
「懺法太鼓(せんぽうたいこ)」とは、お経が読まれる際に使われる小さな太鼓で、平太鼓と胴長太鼓などがあります。
天台宗の特徴とされる大切な法要の一つ「法華懺法(ほっけせんぽう)」には、平太鼓が使われた絵柄が入っています。その大きさには直径が24㎝~36㎝ほどです。
懺法太鼓の使い方は、金属製の輪である釻に指をかけて、バチで片側だけを打ちます。
懺法太鼓は主に天台宗、浄土宗などの法要で使用されます。
印金
「印金(いんきん)」は、「磬子(けいす)」の一種で「引磬(いんきん)」と書かれることもあります。携帯することのできる磬子で、その鐘の口径は7㎝~12㎝ほどです。
鐘を支えるように座布団があり、その座布団の下には持ち手である取っ手がついています。バチである倍でたたいて鳴らします。
「印金」には、仏教儀式で使われるものと、お墓参りなどにも持っていきやすいように小ぶりにしたものもあります。小さくても澄んだ美しい音が響きます。
錫杖
「錫杖(しゃくじょう)」は、つえの頭部分に複数の金属の輪を揺らして音を鳴らします。
錫杖には浄化する力があるとされており、手に持って振りながら音をたて、お経を読んだり、加持をする道具としても使われることがあります。
茶湯器
「茶湯器(さゆき)」とは、水やお茶をお供えするときに使うコップのような器です。
毎朝お水を入れ替えお供えします。お参りをした後はそのまま流してもよいでしょう。
また浄土真宗では、極楽浄土には八つの水が満ちているのでお供えは必要ないという教えがありますが、故人が飲み物に困らないことに感謝してお供えをすることもあります。
最後に
天台宗の葬儀には、顕教と密教を基にした特徴的な儀式があり、他の仏教の葬儀とは趣が違うところがあります。
ただし、天台宗の教えである「誰もが仏性がある」という教えから、葬儀では仏門に入るところから始まり極楽浄土での往生の祈願までが行われるため、理にかなった葬儀とも言えます。
このような葬儀が営まれる天台宗の葬儀ならば、故人も安心して永眠できるのではないでしょうか。天台宗の教えにのっとり、葬儀の流れを理解すれば、故人を送り出す遺族も心を落ち着けて参列することができるでしょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。