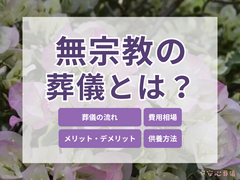日蓮宗のお葬式で準備することを解説

仏教において各宗派の葬儀には、それぞれの宗派ならではのしきたりや作法があることを知っていますか。葬儀は宗派によってさまざまな決まり事があります。
近親者が亡くなり、葬儀を執り行うことになった際、準備をスムーズに進めるためにも、しきたりや作法を事前に知っておくことが重要です。また、葬儀に掛かる費用やお布施についても事前にある程度予測できていれば、心の準備ができるでしょう。
今回の記事は、日蓮宗の葬儀を準備する際に注意したいことや知っておきたいことを紹介します。



日蓮宗の葬儀について
日蓮宗とは、当初は日蓮法華宗(にちれんほっけしゅう)と呼ばれていたものが、やがて省略されて日蓮宗と呼ばれるようになったものです。仏教の中で開祖(宗派を開いた人)の名前である立正大師日蓮(日蓮)がついた唯一の宗派で、仏教の一派です。日蓮聖人が生まれたのは1222年、わずか16歳で「生死・社会・仏教界」の三つの疑問をきっかけとして出家しました。
仏教の宗派の中でもとりわけ個性が強烈で、何度弾圧を受けても決して屈しない仏教界の革命児とされている宗祖・日蓮聖人の人生がそのまま反映された宗派です。
日蓮宗は、いくつもあるお経の中で「妙法蓮華経(略して「法華経」)」を一番大切に考えています。「法華経」は聖徳太子の時代から日本仏教において最も重要とされてきた全八巻二十八品ある「久摩羅什(くまらじゅう)訳」の経典です。
日蓮宗では、「法華経」で説かれている「全てのものには仏性がある」という教えが大事だと考えています。日蓮聖人の教えは、永遠に存在して人々を救い続ける久遠実成(くおんじつじょう)のお釈迦様の救いを信じ「南無妙法蓮華経」のお題目を唱え、来世ではなく現世での救済を願うということに集約されているのです。
ここからは、日蓮宗の特徴や葬儀について詳しく説明します。
日蓮宗の葬儀の特徴
日蓮宗の葬儀の考え方
日蓮宗では「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」をお題目と呼び、この言葉に全ての功徳が込められていると考えています。人は「南無妙法蓮華経」と唱えることで修行を積み、誰でも仏になることができると言われています。
特に葬儀では、「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えることで故人を霊山浄土(りょうぜんじょうど)に送り出す、という意味合いがあり、葬儀中は会葬者も含めて全員でお題目を唱えます。
日蓮宗は、仏教の開祖としての釈迦牟尼仏ではなく、法華経の中で説かれている「永遠の昔に悟りを開いた仏としての久遠実成の釈迦牟尼仏」と考えています。これを文字にして日蓮が描いた十界曼荼羅を本尊(多くは略して中央に「南無妙法蓮華経」の七文字だけ書かれたもの)とし、葬儀ではそれが描かれた経帷子を使うことも特徴の一つです。
日蓮宗の葬儀とは、死出の旅路へと送り出すに当たって、十王(※)の裁きを踏まえ、俗での姿や価値観、仏弟子となるべく引導においての教えを聞き、誓いを立て、俗を離れた証として戒名を受けて旅立つ儀式です。
また、他の宗派の葬儀で使用される木魚は使われず、木鉦(もくしょう)と呼ばれる法具を打ち鳴らして読経が行われます。
※十王:不動明王・釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩・地蔵菩薩・弥勒菩薩・薬師如来・観音菩薩・勢至菩薩・阿弥陀如来
日蓮宗と日蓮正宗の違い
日蓮宗は、日蓮聖人が教えを広めた仏教の宗派の一つで、鎌倉時代に争乱や天災・自然災害などが多発した波乱の時代に布教(仏教の教えを広めること)しました。現世に生きることこそが大事であるとする教えで、その教えは諸外国にまで広まっています。
日蓮には弟子が六人いましたが、日蓮の亡き後、五人は日蓮宗の教えを継承していきましたが、残りの一人である日興が新たに創始したのが日蓮正宗です。
日蓮正宗は、日蓮大聖人が描いた本尊(曼荼羅)に向き合って「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えることで、「いかなる人も仏の境涯が現れ救われる」という教えです。
また日蓮宗、日蓮正宗ともに「南無妙法蓮華経」を唱える、という点では同じです。大きく異なるのは日蓮宗が釈迦を本尊とする(日蓮聖人のまたの名が日蓮大菩薩であり、日蓮聖人を大菩薩として考えているから)のに対し、日蓮正宗は日蓮を日蓮大聖人と呼び日蓮を本尊としているところです。
また日蓮宗は山梨県にある身延山久遠寺(くおんじ)を総本山とし、日蓮正宗は静岡県にある多宝富士大日蓮華山大石寺(たいせきじ)を総本山としています。
日蓮宗の葬儀の流れについて

日蓮宗の葬儀の流れ
日蓮宗の葬儀は最後の門法修行の場です。日蓮聖人の教えのもとに「法華経を信じて南無妙法蓮華経と唱えるものは霊山浄土(りょうぜんじょうど)に行くことができる」という考え、三世(過去・現在・未来)にわたって法華経の教えを守り、故人を霊山浄土に導くことを目的として執り行われます。
まず、司会から開式の言葉が述べられ、導師による読経が行われます。
その後、以下の順序で執り行われます。
- 総礼:一同が合掌し、題目である「南無妙法蓮華経」を3回唱え、礼拝する
- 道場偈(どうじょうげ):諸仏諸尊を迎えるための声明を流す
- 三宝礼(さんぽうらい):仏法僧の三宝は釈迦、法華経、日蓮にあると考え心を込めて祈る
- 勧請(かんじょう):霊山浄土に居ると言われている仏・菩薩・神々・日蓮聖人を葬儀の場に迎える
- 開経偈(かいきょうげ):読経の前に法華経の功徳をたたえることを唱え、仏の教えに出会えたことに感謝する
- 読経:法華経の中の重要な部分を拝読する
- 咒讃鐃鈸(しゅさんにゅうはち):諸仏を供養するために唄をうたい、楽器を演奏する(導師が一人の場合は省略される)
- 開棺:導師が棺の近くに立ち、棺の蓋を叩きながらお経を唱え、引導の前に悟りに入ることを予告する
- 献供:茶・膳を供える(事前に供えて省略する場合もある)
- 引導:故人が今の世から心を新たにして次の世界へ旅立つように導く棺の側で払子(はっす)を3回振り、焼香を3回し、引導文を読む
- 弔電:司会から弔電が読まれる
- 読経:法華経の中の重要な部分が拝読される
- 祖訓:日蓮が遺した言葉を拝読する
- 唱題:題目である「南無妙法蓮華経」を唱えながら、焼香を行う
- 宝塔偈(ほうとうげ):回向の前に唱えられる偈文で、法華経の功徳をたたえる
- 回向(えこう):故人が仏と一体になったことで得られる喜びをこの世の全ての者にささげて、その喜びに守られて霊山浄土に向う
- 四誓(しせい):人々を救うための誓いの四つの言葉を唱える
- 三帰(さんき):法要の終わりに、三宝に帰依し精進することを表す
- 奉送(ぶそう):諸仏諸尊を送る声明を流す
- 閉式:導師が退場し、司会から閉式の言葉が述べられる
日蓮葬の流れには多くの項目がありますが、近年ではいくつかの項目を省略することもあります。
葬儀中に会葬者や親族が唱和したり、焼香をする場面では導師や司会者から指示があるので指示に従いましょう。前述したように、日蓮宗では全員で「南無妙法蓮華経」を唱えることに意味があるため、唱えることを忘れないように注意が必要です。
所要時間は多くの場合、導師入場から45分〜1時間程度となっています。



日蓮宗の葬儀のマナーについて
どの宗派にもしきたりやマナーがあります。ここでは、その中でも大きな特徴があると言われている日蓮宗の葬儀に関するマナーについて説明します。
日蓮宗の葬儀のマナー
焼香のマナー
焼香とは故人を弔い、心身を清めるという意味があります。抹香と呼ばれる細かく刻まれた香を使い、それを香炉にくべて行います。
焼香の歴史も、仏教同様インドから始まりました。インドの気候が高温なことから汗をかきやすかったり、物が腐りやすいことから、体臭や悪臭を消すための風習から「清める」ことを重要視し、仏教だけではなく他宗教でも取り入れられるようになりました。
日蓮宗の場合、焼香は南無妙法蓮華経の題目を読む間に行われます。
葬儀担当者の指示の元、祭壇に進み、遺族に一礼、参列者に一礼します。
焼香台の前で合掌、一礼してから焼香盆のお香を右手の親指と人差し指で軽くつまみ、一度額の前に押しいただき、火種にくべます。日蓮宗の場合、焼香の回数は正式には仏・法・僧に帰依するという意味から3回ですが、会葬者の人数によって参列者は1回焼香の場合もあります。焼香が終わったら、左手に数珠をかけ、再び合掌して自席に戻ります。(焼香後も遺族並びに参列者に一礼する場合があるが省いてもよい)
線香を立てる形式の場合には、1本もしくは3本の線香を使います。3本の場合は仏様側に2本、自分側に1本立てます。葬儀の参列者が多い場合は、香炉の真ん中に1本立てます。
数珠のマナー
数珠(念珠)は法具と言って、煩悩を取り除いて功徳を得ることができると言われています。
日蓮宗の数珠は、人間の煩悩の数と同様に108個の玉でできています。この108個の玉を主珠とよび、他に四つの四天珠、二つの親珠をつないでできており、2本の房が出ている方の親玉は釈迦如来(しゃかにょらい)で、3本の房が出ている方の親玉は多宝如来(たほうにょらい)を表していると言われてています。
数珠は、仏壇・仏具店で購入する他、現在はインターネットでもさまざまな種類の数珠を購入することができます。
また、他の宗派で用いられる数珠の房とは形が異なり、菊房と呼ばれる丸い房が2本のものと3本のものが一つずつ付いており、房が3本の側を左手の中指に掛け、一回ひねってから房が2本の側を右手の中指に掛けるのが正しい合掌の仕方です。
合掌以外の際は、左手で軽く握って持つようにします。
日蓮宗専用のものが手元にない場合、どの宗派でも使える片手の略式数珠でも代用が可能です。
服装、持ち物のマナー
通常の葬儀と同様に、男性ならモーニングや紋付羽織袴、女性なら黒のワンピースや黒紋付などの正喪服や準喪服を着用するのがマナーです。通夜であれば、紺や濃いグレーなどのダークカラーのスーツでも問題ありません。
靴やカバン、ネクタイなどの小物は黒色で統一するようにします。
派手なアクセサリーを着用することは避け、着用する場合は1連のパールネックレスなどの落ち着いたものにします。
女性のメイクは、派手なものは避け、片化粧にとどめます。
子供が参列する場合は、ダークカラーなどの落ち着いた色彩の服装であれば問題ないでしょう。制服があるのならば、制服を着用させても構いません。歩くときに音が鳴る靴は葬儀の場にはNGなので注意しましょう。
日蓮宗葬儀のお布施について
日蓮宗の葬儀での、お布施の相場や渡すタイミングなどを説明します。
日蓮宗葬儀のお布施
お布施とは
元来のお布施とは、出家した修行者や仏教教団、更には貧窮者などに施しを与えることで、三施(財施・法施・無畏施)という三つの布施があると言われています。
本来は各宗派の御本尊にお供えするのが「お布施」ですが、現在では読経してくれたお礼と戒名料を合わせて、「お布施」としていることが多いようです。
お布施は葬儀が始まる前の僧侶への御挨拶時、または終了後に、お礼として当日中に僧侶に直接手渡しします。この他に、僧侶が法要後の食事を辞退された場合には、御膳料を渡す場合があります。また、葬儀が寺院以外の斎場などで執り行われた場合は御車代も渡す場合があります。
御膳料は5000円~1万円、御車代も5000円~1万円が相場と言われています。
(御善料も御車代も必ず渡さなければいけないというものではありません)
お布施の相場:5万円/回
お布施は通夜・葬儀・火葬・初七日・四十九日のそれぞれの法要で必要になります。金額を設定しているお寺もあれば、「お気持ちで」と言うところもあるでしょう。目安として1回当たりの読経で5万円と考えてもよいかもしれません。この金額はあくまでも目安で、お布施は故人とお寺の関係や地域性によって金額は異なりますので、直接お寺に確認するか、親しい檀家さんに聞いてみましょう。
1回のお葬式のお布施の相場:20万円~
1回の葬儀でのお布施の相場は20万円前後からと言われています。
最近では、読経料、戒名料と分けるのではなく、まとめて「お布施」として渡すのが主流のようです。
お布施の金額は、授かる戒名の階級や、地域性によっても異なるので、菩提寺がある場合は直接相談しましょう。
葬儀社に紹介してもらう場合は、葬儀社に相談します。
なお、二名以上の僧侶によって葬儀が取り行われた場合、別途費用が掛かりますので注意が必要です。
関連記事

お布施をお渡しする際の挨拶とは?その際のマナーも紹介します
寺院にお布施を納める機会は葬儀や法要くらいで、そうそう頻繁にあるものではありません。そのため「お布施を渡すときの挨拶やマナーはこうだ」と自信を持って言える方は少ないのではないでしょうか。 特に...
続きを読む



日蓮宗葬儀の香典について

日蓮宗の葬儀に参列するときに備えて、香典の相場や香典袋の書き方なども確認しておきます。
日蓮宗葬儀の香典
香典とは
古くは故人の霊前に香(花や米など)を供えていたのが始まりで、明治時代以降はその代わりとして金品が用いられるようになったのが現在の香典と言われています。
昔は、お香は大変高価なもので、通夜ともなれば一晩中焚き続けなければいけませんでした。今でこそ線香などの技術が発達していますが、昔はすぐに消えてしまうお香ばかりであったため、近所の人などが皆で協力してお香を持ち寄り、一晩中焚き続けられるようにしていました。現代になり、お香(線香)の技術も発達したのでお香を持ち寄る必要性はなくなりましたが、相互扶助の考え方と香を備える(香典)という言葉が残り金銭を包んで持参するようになったのです。
香典は不祝儀用ののし袋に現金を入れて渡します。持ち運ぶ際には袱紗(ふくさ)に包み、渡す際には袱紗から不祝儀袋を取り出し、袱紗の上に置いて名前が受付の方に読めるようにします。
香典袋の書き方
日蓮宗では四十九日をもって故人が成仏されるという考え方を持っているため、四十九日以前の通夜や告別式の場では「御霊前」または「御香典」、四十九日以降は「御仏前」または「御香典」と香典袋に表書きをします(厳密にいえば「香典袋」という言葉は仏教の葬儀時にしか使わない言葉です)。
水引の下段の中央にフルネームを記載します。いずれも薄墨を使用してください。薄墨は「悲しみの涙で墨が薄くなった」という意味や「故人の不幸を聞きつけたので急いで駆けつけたために時間をかけて墨を充分にすっている間もなかった」という意味もあります。しかし現代ではその意味合いを知らない人の方が多く、逆に薄い墨を使っていると悪印象を与えてしまう場合もあるので注意が必要です。
袋の後ろ、または中袋にフルネーム、住所と封入した金額を書いておきます。
金額の書き方、特に漢字ですが、一は「壱」、二は「弐」、三は「参」、万は「萬」、円は「圓」のように旧漢字を使用するとより丁寧でしょう。
香典の相場
香典は故人との関係によって金額が異なります。
例えば、知人・友人の場合は5000円~1万円、特に親しい友人や祖父母、おじ・おばなどの場合は1万円~3万円、きょうだいなど法要後の会食に参加する親族の場合は3万円~5万円、両親の場合は5万円~10万円が香典の相場と言われています。
通夜と告別式の2日間に渡って参列する場合は、通夜に香典を持参します。なお、やむを得ず葬儀に参列できない場合には、香典を郵送することも可能です。その場合は、現金書留を利用します。
また、使用するお札は「事前に準備するものではない」という考えがあるため、新券は使いません。新券しか手元にない、という場合は意図的に折り目をつけてから不祝儀袋に入れましょう。お札の入れる向きにも注意します。封筒(中袋)の裏面にお札の表面が来て、顔は下になるようにいれます。お札を裏にするのは、あくまでお悔やみですので「顔」を伏せるという意味から「裏・下」と言われています。
日蓮宗の葬儀を行う際に掛かる費用

日蓮宗の葬儀に掛かる費用はどれくらいでしょうか。日蓮宗の葬儀に掛かる費用について説明します。
日蓮宗の葬儀を行う際に掛かる費用
日蓮宗の葬儀を行う際に掛かる費用の相場
家族葬の場合は約60万円~100万円くらい、友人・知人が会葬者として参列する一般的な葬儀の場合は約70万円~200万円くらいが相場と言われています。
幅があるように思われるかもしれませんが、これは会葬者の人数とそれに比例した会場の広さによって費用が変わってくるためです。
具体的には会葬者が多い場合、会葬御礼や通夜振舞いなどの費用が増加し、会場もある程度の広さが必要になり、会場費用も増えます。
それ以外にも、会食費、病院から自宅・斎場まで遺体を運ぶ搬送費、斎場の利用料、火葬費用、祭壇や棺などの費用も必要です。
加えて、参列者が遠方に住んでいる場合は、現地までの交通費や宿泊費が別途必要になります。
葬儀とは別途で掛かる費用
日蓮宗では読経料が掛かります
読経料はお布施の項目でも触れたように、読経1回につき5万円が目安になっています。しかし、故人とお寺のそれまでの関係により異なることがありますので、事前にお寺に確認しましょう。
また、通夜、葬儀、火葬場の炉前法要、初七日など、読経をする回数によっても費用が異なります。読経に際して出張が伴った場合には5000円~1万円程度の御車代を渡す必要がありますので忘れないようにしましょう。
戒名を行うのに費用が掛かる
日蓮宗では日蓮聖人の教えにより戒名を法号と言い、日蓮信仰に深く帰依した証として授けられます(そのため日蓮宗では葬儀時に授戒の作法がない)。法号は「院号」「道号」「日号」「位号」で構成され、本来の戒名の部分は「日号」に当たります。
法号は、存命中の社会への貢献度や信心深さから菩提寺の僧侶が名付けることになります。男性の場合は「大居士」「居士」「信士」のように貢献度・信心深さの程度によって用いられる位号が異なります。
日蓮宗における戒名の付け方は主に「位」と「意味」の二つを定めることから始まります。
日蓮宗はもともと門流の多さから統一的なものを定めることは難しいのですが、近年では主に次のブロックに分けることができます。
- 道号、法号、位号(△△○○信士、信女もしくは△△○○居士、大姉)
- 院号、法号、位号(▲▲院○○信士、信女もしくは▲▲院○○居士、大姉)
- 院号、道号、法号(日号)位号(▲▲院○○日●信士、信女・▲▲院○○日●居士、大姉)
その他(水子、孩児、院殿、大居士、清大姉など)
に大別することができます。
最近は、△△○○信士、信女を「一般戒名」と定めていることが主流です。
次に2もしくは3の一部を「院信士、院信女」とし3の信士、信女を「院日信士、信女」、2もしくは3の居士、大姉を「院居士、院大姉」とすることが通例になりました。この位号によって戒名料も異なり、信士・信女の場合は30万円からが相場だと言われています。
関連記事

戒名とは?つけ方や意味、費用相場について解説
本記事の結論戒名とは、仏道に生きることを決めた者に対して師匠が弟子に授ける名前のこと原則的に菩提寺の住職か、今後菩提寺として付き合う寺院の住職に付けてもらう戒名の位は原則的に住職が寺院や社会への...
続きを読む



まとめ
この記事では、日蓮宗の葬儀について準備と当日の流れを説明しました。同じ仏教でも宗派によってしきたりは異なりますし、特に日蓮宗の葬儀では、流れを省略せず行いますので、事前に流れが分かっていると安心です。また葬儀に掛かる費用についても事前にある程度の予測を立て、いくつかの葬儀社に見積もりをとるとよいでしょう。
日蓮宗の葬儀の正しい知識を知って、不安を解消してください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。