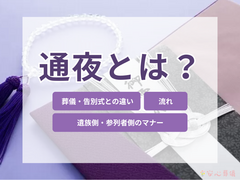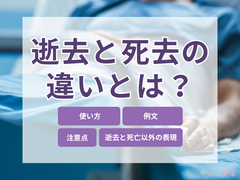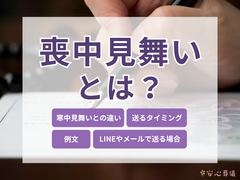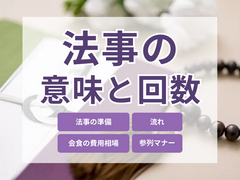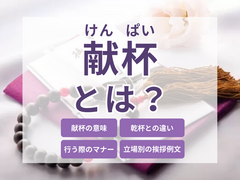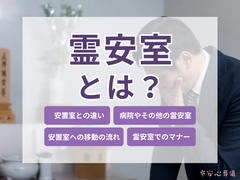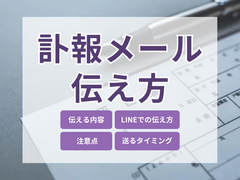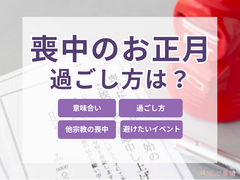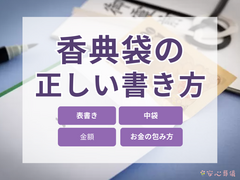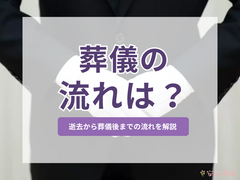お骨拾いで気をつけるべき事は?骨上げの手順やマナーを解説

火葬後は、遺族や親族の手によって遺骨を骨壷に収める儀式があり、これを「骨上げ」と呼びます。骨上げは、故人との別れを偲ぶ重要な場でもあります。
本記事では、骨上げの手順やマナー、地域による違いなどについて解説します。



骨上げとは?
骨上げとは、火葬後に主に遺族や親族の手によってお骨(遺骨)を骨壺に納める際の一連の手順から成る儀式を指します。「収骨」または「拾骨」と書いて「しゅうこつ」と呼ばれることもあります。
その内容には地域により違いが見られるものの、お骨を骨壺に納める手順の基本部分は共通です。
火葬終了後に遺族・親族が集まり、二人一組となって「箸渡し」の作法によりお骨を骨壺へと移します。
また、故人と関係の深くない人物が喪主を務める場合や、故人に家族や親族がいない場合は骨上げを行わないこともあります。
箸渡しについて
箸渡しは、骨上げの際に二人一組で遺骨を拾い、骨壷におさめる作法です。かつては一人で遺骨を箸で持ち、それを次の人へ順々に渡していく方法だったようですが、現在では一つの遺骨を二人がそれぞれの箸で一緒に持ちます。
使用する箸もただ長いだけではなく、わずかに長さの異なるものが組み合わされていたり、竹製の1本と木製の1本とでセットとなっていたりと、通常の箸とは違って不揃いになっている場合が多く見られます(宗教や地域などにより異なります)。
箸渡しには、「箸」と「橋」が同じ音であることから、この世とあの世の橋渡しをして、「故人を無事に送れるように」「三途の川を無事に渡ることができるように」という意味が込められていると言われています。
また、食事中の箸使いでは、箸渡し(移し箸・合わせ箸・拾い箸ともいう)は避けるべき作法である「忌み箸」のひとつとして知られます。
これは、「火葬後の骨上げを連想させる」という理由や、繰り返してほしくない種類の非日常である葬儀全般に見られる「あえて日常とは逆のことを行う」という考え方に基づいていると言われています。
骨上げの手順
骨上げの手順は、おおむね次の通りです。ただし、宗教や地域によって異なる場合もありますので、基本的には火葬場の係の人の指示に従うようにしましょう。
遺骨を囲む
火葬が完了すると、炉から遺骨が取り出されるので、火葬場に同行してきた人たちは遺骨の周りに集まります。
棺を載せていた台をそのまま利用する場合もあれば、遺骨を専用の収骨台の上に移す場合もあります。
二人一組となる
骨上げは二人一組となって行うため、ペアを組みます。男女一組でと指定される場合もありますので、係の人の指示に従いましょう。
箸を用い遺骨を骨壺へ納める
喪主の組から、血縁の濃い順に二人一組で箸を使って遺骨を骨壺へ納めます。
生前のように足が下、頭が上にある状態でお骨が骨壺に納められるようにするため、足の方のお骨から拾い始め、頭の方へと上がっていくように順に拾っていき、最後に頭部の骨と喉仏の骨を拾うようにします。
どのお骨を拾うかといった点については係の人の指示を仰ぎましょう。
お骨の拾い方としては、一片のお骨をペアとなっている二人同時に箸で拾い上げるという方法で行われることもあれば、一人が拾い上げたお骨をもう一人に箸から箸へと受け渡す方法で行われる場合もあります。
これも基本的には火葬場の係の人の指示に従いましょう。
骨上げが終わったら、骨壺を埋葬許可証とともに箱に納めます。



骨上げのマナー
骨上げのマナーにはどういったものがあるでしょうか。
箸を使ってお骨を拾う
お骨は、専用の箸を使って骨壺に納めます。
係の人が手袋をした手で遺骨をざっと分けたり、骨壺に入らない大きさのお骨を細かくしたりといったことはありますが、それはあくまで骨上げをスムーズに進めるための準備としての作業です。
遺骨を骨壺へと納める儀式である骨上げでは、火葬場側で用意している専用の箸を使うようにします。
一般的な箸に比べ、かなり長いものを使うこともあり、手元が狂って拾い上げたお骨を落としてしまうこともあるかもしれませんが、そうした場合にも係の人の指示を仰げば問題ありません。
故人と関わりが深い順に拾う
骨上げでは複数組のペアが順にお骨を拾っていきますが、配偶者や喪主などの故人と関わりが深い立場にあった人から順に拾うのが基本です。
儀式ですので、その場の流れでなんとなく遺骨のそばにいる人から拾い始めるというものではありません。
具体的には、まず配偶者・喪主を含むペアから、続いて遺族→親族→知人や友人といったように、血縁の濃い順に進めていきます。最後に再び喪主と近しい親族のペアに箸が手渡されますので喉仏を拾います。
係の人が適宜指示を出してくれるはずですので、それに従いましょう。
骨上げの際に分骨したい場合
遺骨を2カ所以上の場所で別に供養したい場合は、分骨を行います。骨上げの時点で既に分骨することを決めているのであれば、骨上げの際に行うとよいでしょう。
お墓に納めた後に分骨するとなると墓石を動かす必要があり、寺院や石材店との調整も必要になるので、手間も費用もそれなりにかかるためです。
火葬当日に滞りなく分骨を行うためには、事前の手配が必要です。分骨を希望する場合は、あらかじめその意向を葬儀担当者に伝え、分骨証明書や分骨用の骨壺を手配してもらいましょう。
分骨した遺骨を将来的に納骨するとなった場合には、埋葬許可証に代わるものとして必要となるのが分骨証明書です。
自分で依頼するケース、葬儀社を通して依頼するケースなどがありますが、いずれの場合にも火葬場に発行してもらったものを忘れずに受け取るようにします。
なお、分骨を希望する人が複数人いる場合は、分骨する数だけ分骨証明書も必要となります。分骨証明書は火葬場で発行してもらえるので、事前に忘れずに依頼しておきましょう。
分骨については以下の記事でも解説しています。
関連記事

分骨の方法とは?手元供養の考え方や分骨の際の証明書についても紹介します
遺骨は、骨壷に納めてからお墓に納骨することが一般的ですが、二つ以上の骨壺などに取り分けても問題はありません。そのようにして、遺骨を分けて別々の場所で供養することを「分骨」と言います。 本記事で...
続きを読む



骨上げ後の流れ
仏式を例とした骨上げ後の流れはおおむね次の通りです。
自宅に骨壷を持ち帰り、後飾り壇に置く
骨上げが終わると火葬場の係の人が骨壺の蓋を閉めて包んでくれるので(桐箱に入れたものを風呂敷で包むか専用のカバーをかけるのが一般的です)、自宅へ持ち帰り、納骨までは後飾り壇(四十九日まで設けておく仮の祭壇)に安置します。
ろうそくと線香を灯す
仏壇で行うのと同じように、後飾り壇にろうそくと線香を灯します。
なお、四十九日の忌明けまで灯明や線香を絶やさないようにするのが正式で伝統的な作法ですが(宗派により異なる場合あり)、ろうそくや線香は火の気を伴いますので、防災上の問題もあります。
対応可能な範囲で供養するようにしましょう。
お供え物をする
後飾り壇に仏飯(炊きたての最初のご飯)や水、生花などをお供えします。
四十九日まではご飯と水は毎日取り換え、生花は枯れたら交換するようにします。
また可能であれば、お経(般若心経)を唱えられるとよいでしょう。
地域によっては繰り上げ法要を行うことも
一部地域では、葬儀当日のうちに遺骨を持ち帰って行う還骨法要や、四十九日までの繰り上げ法要を行うこともあります。
法要後には、精進落としと呼ばれる会食が振舞われることが一般的ですが、近年の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、参列者にお持ち帰りの弁当や引出物を手渡すケースも増えています。
地域による骨上げの違い
冠婚葬祭の類には、地域差が色濃く残っている傾向が強いようです。骨上げについても、地域により異なる点が見られます。
例えば、東日本では全ての遺骨を骨壺に納める「全部拾骨」が主流ですが、西日本では足から頭まで各部位の骨を少しずつ拾い、残りの遺骨は火葬場に残して帰る「部分拾骨」が一般的です(火葬場に残された遺骨はその後、火葬場側で供養されます)。
納める遺骨の量が異なるため、骨壺のサイズも東日本と西日本とでは違います。全部拾骨の東日本では大きめのもの(6寸以上が目安)、部分拾骨の西日本では小さめのもの(5寸以下が目安)となっています。骨壺のサイズが違うため、墓地や納骨堂におけるカロート(納骨室)の大きさも東日本と西日本では異なることがあります。
この他にも地域ごとの慣習があり、遠方に住む親族などの葬儀での骨上げの際には戸惑うこともあるかもしれませんが、火葬場の係の人の指示に従っておけば問題ないでしょう。



まとめ
骨上げとは火葬後の遺骨を骨壺に納める儀式のことです。東日本では全ての遺骨を骨壺に納める「全部拾骨」が主流である一方、西日本では各部位の骨を少しずつ拾う「部分拾骨」が主流になっています。
骨上げは主に、遺族・親族やごく近しい関係者で進められることが一般的です。専用の箸を使い、二人一組の箸渡しの作法で骨壺に納めます。
配偶者や喪主から始め、続いて血縁の濃い者から順にお骨を拾うのが基本で、火葬場の係の人の指示に従って足元から上半身、頭の方へと向かってお骨を拾っていきます。
骨上げの際に分骨を希望する場合は、事前に葬儀社にその旨伝え、分骨壺と分骨証明書を必要数だけ用意してもらいます。骨上げを多く経験することはないと思いますので、知識を備えるとともに分からないことは葬儀担当者や火葬場の係の人に確認し、不安なく骨上げに臨むようにしましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。