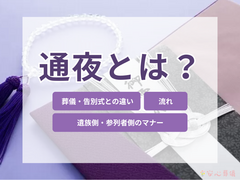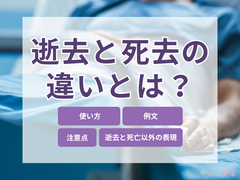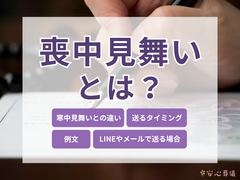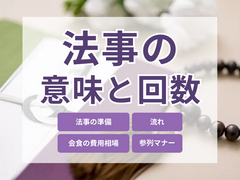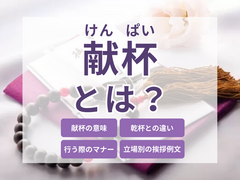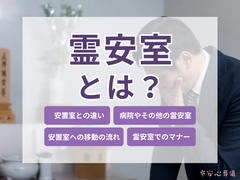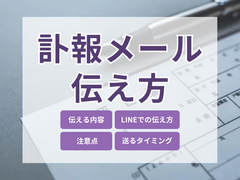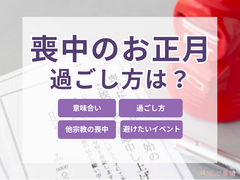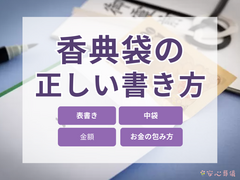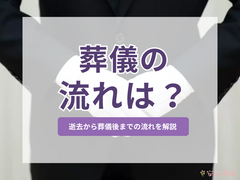分骨の方法とは?手元供養の考え方や分骨の際の証明書についても紹介します

遺骨は、骨壷に納めてからお墓に納骨することが一般的ですが、二つ以上の骨壺などに取り分けても問題はありません。そのようにして、遺骨を分けて別々の場所で供養することを「分骨」と言います。
本記事では、分骨の方法、納骨先、分骨する際の注意点などについて解説します。



分骨とは?
分骨(ぶんこつ)とは、亡くなった方の遺骨を2カ所以上の場所に分けて納骨し、供養することを言います。
分骨をするシチュエーション
分骨される事情はさまざまですが、代表的なものとしては次のようなケースがあります。
お墓が遠方にある
故人の地元が遠方の場合、そこにある先祖代々のお墓までお参りに行くのは、遺族にとって簡単なことではありません。
お彼岸やお盆の時期のお墓参りだけでも大変ですし、日常でこまめにお墓参りをしたいと遺族が希望する場合もあります。
そういったケースでは、先祖代々のお墓に納骨されているご遺骨の一部を遺族の居住地に近い場所に用意した別の納骨先に納めることが解決策の一つとなります。
手元供養を行いたい
お墓という形式ではなく、故人の遺骨をもっと身近に置く形として「手元供養」という方法があります。
手元供養の場合、分骨した遺骨をミニ骨壺などに納めて自宅の仏壇に安置したり、ペンダントや指輪といった装身具に遺骨の一部を納めて供養します。
また、故人の生前の希望により、海洋散骨や樹木葬などの「お墓が残らない形での埋葬」を選択したものの、遺族としては故人を偲ぶ「よすが」がほしいとの思いから、手元供養するために分骨する例もあります。
故人が本山納骨を希望していた
故人が熱心な信者であったなどの場合、信仰する宗派の本山に自分の遺骨の一部を納骨してほしいと生前に希望するケースがあります。
東日本ではあまりなじみのない本山納骨ですが、北陸や関西の一部では、本願寺への本山納骨が風習として残っています。
ただし本山納骨を行うと他の遺骨と合祀されるので遺骨を取り出すことはできなくなります。
離れて暮らすきょうだいがそれぞれ立てたお墓で両親を供養するため
親族が離れて暮らしていると、「立地的な問題でなかなかお墓参りにいけない」などの理由から、別々の場所にお墓を建てることがあります。
このような場合も分骨を行います。
散骨するため
故人が散骨を希望していた場合、遺骨全てを散骨してしまうと、遺骨を取り戻すことはできません。
「散骨は行うが一部はお墓にも納めたい」など遺族や親族の意向がある場合、遺骨の一部を手元にも遺しておくために分骨を行います。
分骨はしてもよいのか
分骨することに法律上の問題はありません。
ただ一方で「遺骨には魂が宿っているから分けるのはよくない」など、分骨することに抵抗を感じる人もいます。
反対に「四十九日を過ぎれば故人は成仏するので遺骨には魂は残らない」という考えや、「お釈迦様のご遺骨(舎利)も分骨されているのだから問題はない」という考え方もあります。
結局のところ、いずれの考え方も人それぞれの信じるところであり、どれが正解というわけでもありません。親戚の意見などを参考にしつつも、最終的には遺族の意向をまとめて決断しましょう。
遺族の中には分骨に反対する人がいる場合もあります。
一部の遺族だけの意向で勝手に分骨するとトラブルに発展する可能性があるので、必ず周囲の遺族や親族に事前に了解を得ておくようにしましょう。
分骨のタイミングと方法とは
分骨はどういったタイミングで、どのように行うのでしょうか。
火葬時に分骨
分骨するための手間や費用は、お墓に納骨する前後で大きく変わります。
お墓に納める前に分骨するほうがずっと容易で、その中でも最初に骨壺に納める際に分骨するのが最もスムーズです。分骨することを決めているのであれば、火葬場での骨上げ(遺骨を拾って骨壺に収める儀式)の際に分骨するのがよいでしょう。
火葬場で分骨する際は、葬儀を依頼する葬儀社を通じて、分骨を希望する旨を事前に火葬場へ伝えておきます。
通常は一つだけ用意する骨壺ですが、分骨する数の分だけ追加の骨壺を用意するよう手配し、骨上げの際に各骨壺に遺骨を分けて収めます(収める遺骨の部位や量などについては、基本的に火葬場の担当者の指示に従います)。
納骨先が1カ所の場合は火葬後に発行される埋葬許可証で事足りますが、分骨した場合はそれぞれの納骨先で「分骨証明書」が必要になります。火葬場にあらかじめ連絡しておけば、火葬後に分骨する数の枚数を発行してもらうことができるので、忘れずに受け取るようにしましょう。
分骨した遺骨を当面は自宅に安置する予定であっても、将来的に納骨することになった場合に必要となってきますので、分骨証明書は必ずもらうようにします。
お墓から取り出して分骨
既にお墓に納骨済みの遺骨を分骨する場合、まずはお墓の管理者である寺院や霊園に連絡を取り、お墓を開ける石材店との日程調整を行うなどして遺骨をお墓から取り出す段取りをつけます。
新しいお墓や仏壇に分骨した遺骨を納める場合は、僧侶を招いて開眼供養を行います。
これらの一連の儀式には当然費用が掛かってきますので、必要となる金額を事前に確認しておくと安心でしょう。
また、お墓に納骨済みの遺骨を分骨するケースでは、お墓の管理者(寺院・霊園)に分骨証明書の発行を依頼することになります。
納骨棺(カロート)入口のふた(拝石)を簡単に開けられるお墓ならば、遺族自身で開けることもありますが、管理者によっては勝手に開けてはいけない場合もあるので確認しましょう。
また分骨を行う際は取り出した遺骨を入れるための骨壷を事前に葬儀社やネットショップで用意しておきます。
準備ができない場合は、骨壷でなくてもひとまず密閉できる容器を用意できれば問題ありません。



分骨の費用相場とは
分骨の費用相場は、火葬場で分骨するか、既にお墓に納めてある遺骨を分骨するかで大きく変わってきます。
火葬場で分骨する際の費用
火葬場で分骨する際に必要な費用は、納骨先で掛かる費用(お墓の購入費用、納骨堂の利用料金、手元供養品の購入など)を除けば、ごく限られています。
具体的には、分骨用の骨壺・ペンダントなどの容器代と「火葬証明書(分骨用)」の発行料(無料という自治体もありますが、おおむね1通当たり300円前後)だけです。
分骨をする骨壺の分だけ分骨用証明書が必要になるので、その数だけ発行してもらうようにしましょう。
お墓から取り出して分骨する際の費用
既にお墓に納められている遺骨を分骨する場合は「分骨証明書」の発行料(施設により1通当たり数百円~数千円)や、墓石を動かし遺骨を取り出すための費用が発生します。
具体的には、墓石の移動に2万円~3万円、新しい納骨先の開眼供養や墓じまいのための閉眼供養が必要な場合は1万円~3万円程度が見込まれます。
納骨の方法によっては、分骨用の骨壺・ペンダントなどの容器代や、納骨堂の利用料金など、新たな納骨のために別途費用が必要となります。
骨壺の数や大きさ、ペンダントのデザインや素材などによって費用は異なります。
一般的な骨壺の費用相場は8000円程度で、ペンダントなどのアクセサリーの費用相場は約1万円~3万円くらいと言われています。
分骨後の手元供養の種類とは
手元供養のための仏壇や骨壷、アクセサリーにはどのような種類があるのでしょうか。
手元供養の種類
仏壇やミニ仏壇
自宅の仏壇に骨壺を安置し供養するのは、一般的な手元供養の方法です。
仏壇には、伝統的な手法で作られたものだけでなく、今日の住宅事情を踏まえたシンプルでモダンなデザインのものまでさまざまな種類があります。手元供養用に作られたミニサイズの仏壇もあります。
仏壇を置くためのスペースなどを考慮して、希望に沿うものを選びましょう。
最近ではインテリアになじむようなデザインのミニ仏壇なども多く、ぱっと見て中に何が納められているか分からないデザインであれば、急な来客があった場合でも気にならないでしょう。
遺骨を家に置いておくということによい印象を持たない方もいるため。そういった点でも選ぶとよいでしょう。
骨壺やミニ骨壺
漆器や七宝、高級感あふれる上絵付けの施された磁器製といった工芸品に近いデザイン性のものや、小ぶりなサイズ感のものなど、部屋の中の目につく場所にあっても馴染むよう考えられた手元供養用の骨壺も販売されています。
仏壇の代わりに、小さなテーブルやちょっとした台などを用意して骨壺を安置するのも一つの選択肢です。
リビングや寝室など、普段からよく目にする場所に置く方が多いようです。
自宅に仏壇を持っている場合は、仏壇の中に安置する方もいます。
小さい骨壷であれば持ってお出かけできるため、旅行などに携帯したいという方にはお勧めです。
以下の記事でも手元供養の方法や費用相場について取り上げていますのでぜひご覧ください。
関連記事

手元供養とは?アクセサリーや保存の容器、費用についても紹介します
亡くなってしまった大切な方を、より身近に感じていたいという希望を叶える方法として「手元供養(てもとくよう)」があります。 従来は葬儀などを終えれば、お墓に納骨することが当たり前でしたが、昨今は...
続きを読む
遺骨アクセサリー
故人を常に身近に感じていたいと願う人向けに、粉砕した遺骨を入れて身に着けるアクセサリー形状の収納容器もあります。
また、遺骨を樹脂で固める手法、合成ダイヤモンドに加工する手法もあります。
ペンダントや指輪、ブレスレットなど、好みで選ぶことができ、一見ではごく一般的なアクセサリーにしか見えませんので、周囲に違和感を与えることなく身に着けることができます。
ペンダントの形は、カプセル型や筒型、またハートやクロス型などさまざまな種類があり、お手入れが簡単で耐久性のあるチタンやステンレス素材のペンダントが人気です。
カプセル型はしっかりと密閉性の高いため、遺骨が漏れたり異物が混入する心配がありません。
故人の誕生石を埋め込んだり、名前を刻印できたりするものもあるのでこだわってみるのもよいでしょう。
遺骨のペンダントを検討されている方は、こちらの記事もご参照ください。
関連記事

遺骨ペンダントとは?手元供養について紹介
「遺骨ペンダント」を知っていますか? お葬式のスタイルも多様化している昨今ですが、その後の供養方法も同様にさまざまなスタイルが見られるようになっています。 遺骨の行先といえば、昔は墓石を建て...
続きを読む



まとめ
分骨とは、遺骨をいくつかの骨壺などに分けて納め、複数の場所で供養することです。分骨を巡る是非はありますが、信念や考え方の問題であり、法律上の問題はありません。
分骨のタイミングとしては、火葬場での収骨のときとお墓への納骨後が多くなりますが、手間や費用が圧倒的に少ないのは前者(後者の場合はお墓を開ける作業などが伴うため、最低でも数万円必要)です。分骨した遺骨の納骨時に必要となる分骨証明書は、分骨した時点では不要ですが、将来的な可能性を考慮し入手して保管しておくようにしましょう。
ミニ骨壺に遺骨を納めて身近な場所に置いたり、ペンダントなどの装身具に入れてアクセサリーにしたりする手元供養など、現在はさまざまな選択肢があります。
分骨を考えている人はこの記事を参考に検討してください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。