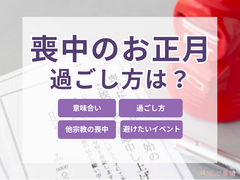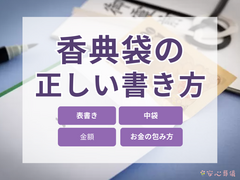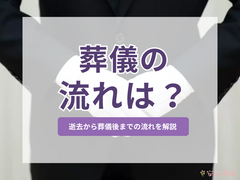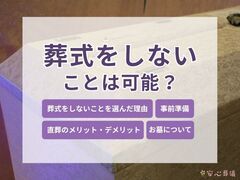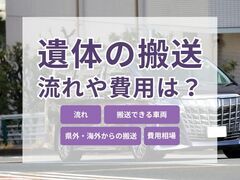後飾りとは?白木の位牌などの処分方法についても紹介します

葬儀・火葬が終わると、お骨は自宅に持ち帰って「後飾り」と呼ばれる祭壇に四十九日までの間安置されます。
本記事では、後飾りとは何か、入手や処分の方法、位牌などについて紹介します。



後飾りとは?
後飾りとは、火葬後の遺骨を安置するための一時的な祭壇を指します。自宅に持ち帰った遺骨を、位牌や遺影、お供え物などとともに安置します。
「自宅飾り」「中陰壇(ちゅういんだん)」と呼ばれることもあります。
仏教では、人は亡くなってから四十九日までは魂がこの世とあの世とをさまよっていると考えられています。後飾りは、故人が四十九日を迎えて成仏するまでの間の仮の安置場所という位置付けで、自宅で故人を偲ぶ際に手を合わせたり、弔問客にお参りしてもらったりする際の、祭壇の役割を果たします。
一般的な後飾りは、白木で作られ(宗派によって異なる場合があります)、白木以外の材質の場合には、白い布をかけます。
後飾りの入手方法
葬儀を依頼した葬儀社に準備してもらうケースがほとんどです。
葬儀社によっては、後飾りがセットプランに含まれていることもあるので、確認しましょう。プランに含まれている場合、設置作業も葬儀社側で行なってくれることが大半ですが、中には自宅での設置作業に別途費用が掛かることもあるため、事前にプラン内容を確認しておきましょう。
葬儀社によって用意される後飾りは、ごく一般的なタイプのものに限られることがほとんどです。設置する部屋の環境やスペースの関係で、別の台や手持ちの家具などを後飾りに使用したい場合は、前もって葬儀担当者に伝えておくとよいでしょう。この場合は、事前に家族の間で後飾りの内容を相談しておくとスムーズに手配を進めることができます。



宗教別の後飾りの期間や弔いの方法
後飾りはいつまで設置するものなのか、また期間中はどのように弔えばよいのでしょうか。
宗教別に確認しておきましょう。
仏教の場合
後飾りを設けておくのは忌明けとなる四十九日までの期間中です。
遺骨や遺影、位牌を置いた後飾りには、四十九日まで毎日、新しい仏飯や水をお供えします。そのほかにも、果物やお菓子など、故人が好きな物をお供えすることもあります。生花は枯れないうちに取り替えるようにし、灯明や線香は基本的に毎日灯すようにします。
四十九日をもって故人は成仏したとみなされ、その後遺骨はお墓に納骨、位牌は仏壇に安置されるという流れが一般的です。
位牌は四十九日を迎えるタイミングで白木の位牌から本位牌に作り替えます。四十九日法要で本位牌への「魂入れ」を行うことが多く、それまでに本位牌を準備する必要があります。また、仏壇を購入される場合は、四十九日を迎えるまでに準備しておくとスムーズです。
後飾りは仏壇がある場合には仏壇の前に設置し、仏壇がない場合には部屋の北や西に設置します。一時的な祭壇とはいえ、毎日お供えをしたり灯明や線香を灯したりする場になるので、安全面やお参りがしやすい場所であることも考慮するとよいでしょう。また、遺骨が痛む原因となるため、直射日光が当たる場所や湿度の高い場所、空調の真下は避けるようにしましょう。
神道の場合
本来、神式では火葬後すぐに納骨するという流れですが、今日では仏式同様に一旦自宅に遺骨を持ち帰り、一定期間後に納骨するという流れが主流となってきています。
火葬を終えて遺族が帰宅すると、仏教でいう位牌に当たる霊璽(れいじ)を仮の祭壇に祀って帰家際(きかさい)を行います。帰家祭とは、葬儀が無事に終了したことを霊前で奉告する儀式です。
帰家祭以降は、仏教でいう法要に当たる霊祭(霊前祭)が10日ごとに設けられ、五十日祭をもって忌明けとなります。
五十日祭が終わるまでは、「仮御霊舎(かりみたまや)」などと呼ばれる後飾りを設けておくことが一般的です。
五十日祭を終えた御霊代(霊璽)は、「祖霊社(それいしゃ)」や「御霊舎(みたまや)」と呼ばれる祭壇に祀られます。
もともと神道に後飾りの考え方はないため、弔い方の作法は特に定められていませんが、忌明けまで故人を悼みお参りするのが一般的です。
キリスト教の場合
キリスト教には忌中や忌明けの概念がありません。
そのため、いつまで後飾りを設けておくかは遺族の考え方次第となりますが、カトリックでは亡くなって1ヵ月後の追悼ミサ、プロテスタントでは同じく1ヵ月後の召天記念日のタイミングで納骨を行うことが多くいため、それまでの期間は自宅に遺骨を安置しておくことが主流となっています。
キリスト教における後飾りは、あくまで日本独自の風習を踏襲したものであるため、弔い方の作法は特に定められていません。設置期間中は故人を偲ぶ「よすが」とします。
宗教別の後飾りの内容や違い
後飾りに置くものとして、遺骨および遺影の他、花をお供えするための花立てや花瓶、ろうそく立ては各宗教共通ですが、それ以外のものについては宗教ごとに異なってきます。
仏教における後飾り
遺骨、遺影、花立て、ろうそく立ての他に、位牌(白木の位牌)、香炉、お鈴(おりん)、お供え物を飾ります。線香立てもあれば飾りましょう。
2段か3段のひな段状になっている白木の祭壇を用意することが一般的ですが、3段の場合はその上段に遺骨と遺影を、中段の中央に位牌を、下段にお供え物やその他の仏具を置くというのが主流です。白木でない場合は、白い布をかけておきます。
2段の場合は、上段に遺骨、位牌、遺影を並べておきます。
なお、浄土真宗では亡くなるとすぐに成仏するという考え方をすることから、後飾りの設け方にも上記とは異なる点があります。
具体的には、追善供養は不要であるため、仏飯や水、果物などのお供えものはしません。
神道における後飾り
神式の後飾りは、「案」と呼ばれる左右に4本ずつ脚のある白木の台(八足の祭壇)が正式なものになりますが、仏式同様に階段状の祭壇を用いる場合もあります。
遺骨や遺影、榊立て(花ではなく榊を飾るため)、ろうそく立ての他に仏式の位牌に当たる霊璽(れいじ)を祀り、米や水、塩、酒などをお供えします。
祭壇が3段となる場合、上段に遺骨と遺影を、中段に霊璽と榊立てを、下段に残りのものを置くというのが一般的です。
キリスト教における後飾り
祭壇の仕様について特に決まりはありません。小ぶりのテーブルや台に白い布をかぶせ、祭壇代わりとすることもあります。
遺骨や遺影、花立て、ろうそく立ての他に、十字架や聖書、お皿に載せたパンなどを置くことが多いようです。
小ぶりのテーブルでは、全てをその上に並べることになりますが、3段の祭壇を利用する場合には、上段に十字架を、中段に遺骨と遺影を、下段に残りのものを置くのが一般的です。
仏式や神式と比べると、非常にシンプルな後飾りです。



白木の位牌と本位牌について
故人の戒名などを記し、故人の魂の依代(よりしろ)とする位牌には、白木の位牌と本位牌の2種類があります。
白木の位牌とは
簡単に説明すると、白木の位牌は葬儀で祀るためにとり急ぎ準備する「仮の位牌」です。
亡くなってから冥土の旅をする故人の魂が「四十九日目に極楽浄土に辿り着き成仏する」と考えられており、その大切な区切りで仮の位牌から本位牌へと故人の魂の移し替えを行います。
そのため、葬儀を終えた食後の後飾り祭壇には、仮の位牌である白木位牌を遺骨とともに安置するのが一般的です。
本位牌とは
四十九日法要以降、故人の魂の依代として永く祀られていくのが本位牌です。漆塗りや唐木製といった本格的な仕様のものになっています。
四十九日法要の読経の中で、僧侶により白木の位牌から本位牌へと魂を移す儀式(魂入れ、開眼供養)が行われます。
本位牌の表側には戒名と没年月日が、裏側には生前の名前(俗名)や享年などが彫られます。
夫婦で連名として一つの本位牌にする「夫婦位牌(めおといはい)」や、先祖の位牌を一つにまとめて「先祖代々の位牌」とすることもあります。
浄土真宗の場合は、浄土で仏になるとされているので忌明け後に本位牌を作りません。その代わりに、本位牌に彫る内容を記す「過去帳」を用意します。自分で記入してもよいですが、紙の質によっては書きづらい場合があるため、仏具店にて記入してもらうことをお勧めします。
本位牌の手配について
四十九日法要で白木の位牌から本位牌へと作り替えるため、本位牌をそれまでに用意しておく必要があります。
葬儀でも使われる白木の位牌は、葬儀社のセットプランに含まれ、葬儀社側で用意してもらえることが一般的ですが、本位牌については遺族自らで手配することになります。
仏具店で入手できますが、葬儀社を通じて手配する場合が多いようです。
戒名などを入れる工程が伴いますので、一般的には仕上がりまでに1~2週間ほどを要します。余裕をもって手配するようにしましょう。
位牌の種類や選び方については以下記事もご参照ください。
関連記事

位牌の相場や選び方とは?宗派による違いや準備のタイミングを紹介します
身近な方が亡くなると、仏教では多くの場合、位牌を用意して仏壇に祀ります。 位牌を見たことがあっても、実際にどのような意味があるのか把握されている方は少ないでしょう。 この記事では、位牌の持つ...
続きを読む
四十九日法要後の白木の位牌の取り扱い
故人の魂の依代(よりしろ)としての役目を終えた白木の位牌は、僧侶に引き取ってもらい、お焚き上げをお願いします。
後飾りの処分方法
四十九日を過ぎれば不要となる後飾りは、どのように処分すればよいのでしょうか。
基本的には自治体ルールに従って処分
白木の位牌については魂抜きをした上でお焚き上げを行いますが、後飾りの処分に当たっては、魂抜きやお清めといった宗教的作法は不要です。ろうそくや陶器製の仏具などは一般的な廃棄物として各自治体のルールに則った方法で処分します。
葬儀社のセットプランに含まれていたケースで、葬儀社から提供を受けた後飾りであれば、利用期間後に葬儀社が引き取ってくれる場合もありますので、確認しましょう。
また、四十九日を過ぎても引き続き利用したいといった希望があれば、必ずしも処分しなくても問題はありません。中には、お盆飾りの盆棚として再利用できるものもあります。
なお、後飾りをレンタルしていた場合は、当然のことながら処分ではなく返却手続きを取ります。



まとめ
後飾りとは、葬儀後から納骨までの期間、遺骨や遺影を安置する祭壇のことです。忌明けとなる四十九日までの期間限定で使う仮の祭壇という位置付けで、葬儀を依頼した葬儀社を通じて入手することが一般的です。
本来、後飾りは仏教の習慣ですが、日本での葬儀における風習として神道やキリスト教でも同様の弔い方がなされるケースが多いようです。
四十九日の忌明けをもって白木の位牌は本位牌へと取り替えられるので、本位牌や仏壇などを必要に応じあらかじめ準備しておき、使用後の後飾りは、通常の廃棄物として各自治体のルールに従って処分してください。



葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。