デジタル遺品とは?整理する際の注意点と方法までを解説
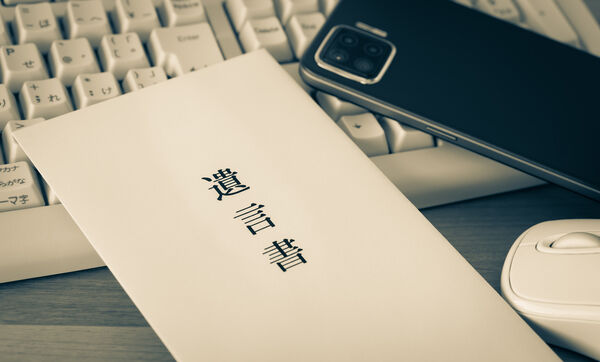
身近な方が亡くなったら遺品整理を行うこともありますが、忘れてはならないのがデジタル遺品です。
パソコンやスマートフォンを所有している方なら誰もが遺すことになる「遺品」です。
プライベートな内容となる「遺品」ですので、安全に整理したいと感じる方も多いのではないでしょうか。
デジタル遺品によって起こりやすいトラブルを押さえておくと、適切な整理ができるようになります。
今回の記事では、デジタル遺品を整理する際の問題点と解決方法について紹介します。



デジタル遺品とは
まず、デジタル遺品について解説していきます。
デジタル遺品とは
デジタル遺品とは、故人が保有・管理していたデータなどを指しますが、明確な定義はありません。
故人が所有していたパソコンやスマートフォンに保存されている情報だけでなく、メールやSNSアカウント、ネットショッピング履歴などもデジタル遺品に当たります。
デジタル遺品は大きく分けて、手元にある電子機器やUSBメモリなどの記録媒体に保存されたデータ(オフラインのデータ)と、インターネット上のメディアに保存されたデータ(オンライン上のデータ)の2種類があるとされます。
インターネットの普及により、オンライン上でデジタル遺品を遺す方が増えていますし、写真や書類などを電子機器で管理する方も多いです。
故人が所有していた電子機器にはデジタル遺品が詰まっている可能性が高く、中身の確認をせずにリサイクルショップに売ってしまうと、情報の流出にもつながるので、慎重に扱うことが大切です。
また、デジタル遺品と似ている言葉に、デジタル遺産があります。
デジタル遺産は、故人がデジタル形式で保有・管理していた財産のことを言い、ネットバンキング口座や電子マネー、有料会員サービスなどがあります。
デジタル遺産は、経済的価値に直接つながることから相続の対象になるものも多くなりますが、情報を把握しているのが本人だけの場合も多く、相続の手続きが複雑になる傾向があります。
特に会社の経営者は、事業の継承に関する情報や金融資産となる重要な情報を、厳重に管理していることも珍しくありません。
デジタル遺品は家具や日用品の遺品と異なり、存在が見えにくく価値を見逃しやすいので、しっかりポイントを押さえる必要があります。
デジタル遺品の種類
デジタル遺品の種類は以下となります。
一つ目は、SNSやメール、ネット通販で利用していたIDやパスワードなどの情報です。
これらの情報は、該当するWebサイトにログインを行うために必要な情報です。
パソコンやスマートフォンによっては、まとめて管理してくれる機能があります。
二つ目は、ネット銀行・ネット証券などの情報です。
金融資産となるので、デジタル遺品の中でも重要性が高くなります。
家に届く郵便などから、それらを利用していたことを知ることができます。
三つ目は、スマートフォンやパソコンで利用していたサイトなどへの登録情報です。
SNS、ブログ、ネット通販など、人によってはさまざまなサイトが挙げられるでしょう。
利用していたサイトは、上記したIDやパスワードの情報から把握できます。
四つ目は、メモリやハードディスク内に保存されている文章、画像や動画、音声などの記録情報です。
どこにも公開していない、プライベートな内容も目立ちます。
また、見落としがちなのが、デジタルデータの保存容量を拡大するために、月額料金を支払っているユーザーもいることです。
登録を安易に解除すると、デジタル遺品が消えてしまう可能性があるので気を付けましょう。
デジタル遺品を整理する際の問題点
ここでは、デジタル遺品を整理する際の問題点について紹介します。
家具や日用品の遺産との違いを踏まえた上で、問題が起きやすい点をしっかりチェックしていきましょう。
IDやパスワードが不明
デジタル遺品の問題点として遺族が困ってしまうのが、IDやパスワードが不明のためログインできず、解約や削除などの対応ができないということです。
IDやパスワードはプライベートな情報のため、故人以外が知っていることは少ないためです。
例として、SNSやブログの管理画面にログインできずに削除の手続きが行えないケースが挙げられます。
有料サイトなどにも入れずに解約手続きができないケースも見られます。
パソコンやスマートフォンではIDやパスワードを管理してくれる機能がありますが、そもそもパスコードを知っていなければ中身を見ることができません。
SNSやブログ
故人のSNSやブログを放置していると、アカウントを乗っ取られて悪用されたり、なりすまし被害に遭うリスクが高まります。
もしアカウントを乗っ取られてしまっても、遺族が把握していなければ対処できず、不正利用が通知されても、その警告にさえ気が付かないケースが多いです。
長期間放置しておくと、悪い人に目を付けられることもあります。時間の経過とともに画像や情報流出の危険性につながるのです。
故人が仕事などで重要なポジションにいたのなら、取り返しのつかないことになることもあるので、早急に対応することをお勧めします。
有料サイト
インターネット上の有料サービスを解約せずにそのままにしておくと、口座凍結やクレジットカードを止めるなどの対応をするまでの間は料金を払い続けることになります。
定額料金で使い放題のサブスクもここに当てはまります。
複数の有料サイトに登録しているなら、その分お金も掛かります。
毎月200円分支払っているなら1年間で2,400円となる計算です。
有料サイトを利用していないのに、余分なお金を払うことになるなら無駄な出費になるだけです。
金融資産
ネットバンキングやネット証券、仮想通貨など、故人がインターネット上に残した金融資産を把握していないと、遺産相続のトラブルになる可能性があります。
故人が外国為替証拠金取引(FX)などリスクの高い取引を行っていた場合は特に注意が必要です。
故人の知られたくない情報
故人が知られたくなかった情報が発見され、遺族がつらい思いをする危険性があることも、デジタル遺品の問題点であると言えます。
例として、SNS上でリアルとは本人とはかけ離れた違うキャラクターを演じていたり、知らない異性とのやり取りを目の当たりにしたときです。
また、万人受けしない趣味を持っている事実を知ることもあるでしょう。
内容によっては、遺された遺族同士でトラブルに発展することもあります。
故人が秘密にしたかった情報が発見されると、後味が悪くなります。



デジタル遺品の整理方法
ここでは、デジタル遺品の整理方法について紹介します。
遺族で整理方法を相談
一つ目は、デジタル遺品の整理方法を遺族で相談することです。
情報を継承するかどうかを話し合っていきます。
また、デジタル遺産があるなら、財産分与についても話し合ってください。
内緒にするようなことがあると、他の相続人からの印象が悪くなるので気を付けましょう。
デジタル遺品を整理する手段として電子機器を売却・廃棄する場合、データを削除・初期化する必要があります。
一人で行うのではなく、なるべく他の遺族がいる中で実行するとトラブルも起きにくくなります。
なお、デジタル機器に詳しい人が率先して行うようにしましょう。
また、厳密には電子機器自体も相続の対象になり、所有者が決まるまでは相続人で共有している状態になるため、むやみに処分したり譲渡したりしないように注意する必要があります。
ただし、相続人同士で合意があれば「形見分け」として遺産分割から省略し、譲り受けることができる可能性もあります。
専門業者に依頼する
二つ目は、デジタル遺品の整理を専門業者に依頼する方法です。
整理だけでなく、買取や供養も行ってくれます。
また、電子機器(特にパソコンよりスマートフォン)にロックがかかっている場合、素人が解除するのは困難です。
無理して解除を試みると、大切なデータまで消えてしまう恐れがあります。
このような状況ならば、専門業者に依頼する方法がお勧めです。
料金は作業内容によっても異なりますが、1万円〜10万円が目安になります。
ログイン、パスワードリスト作成、退会の手続きなど依頼内容が多いほど料金も高くなる傾向です。
自分でできる部分を引き受けるのが、料金を安く抑えるためのコツです。
トラブルを避けるために、専門業者には事前に見積もりをしっかり出してもらいましょう。
安心安全にデジタル遺品を整理したい方は、実績数の多い専門業者に依頼しましょう。
トラブル回避のために今からできること
デジタル遺品は、その性質上、整理する場面で問題も起こりやすいものです。できれば、生前からトラブル回避の対策に取り掛かっていきましょう。
以下、対策を紹介します。
一つ目は、デジタル遺品となる可能性のある情報をまとめておくことです。
デジタル遺品はデータなので、ものとして手元に残るものではありません。
本人も、何がどこに残されているのかが整理しないと分からないことが多いのです。
遺品として残るものを振り返ってみてください。
二つ目は、エンディングノートにIDやパスワード・アカウント情報をまとめておくことです。
エンディングノートは自分の死後についての希望を記載できるノートです。
IDやパスワードが分からずに専門業者にロック解除の依頼をしたとしても、確実に成功するという保証はありません。もしものことを考えた上で備えておくと、余計な手間も費用も掛からずに遺族も手続きが取りやすくなります。
エンディングノートは、何度でも書き直しができるので気軽に作成に取り掛かれますが、自分が亡くなった後に確実に見つけてもらう必要があるため、保管の方法には注意しましょう。
三つ目は、知られたくない情報は生前に削除しておくことです。
故人が秘密にしておきたい情報を知ることで、内容によっては遺族が傷ついたり揉め事に発展したりする可能性もあります。
死は誰にでも訪れるものと考えた上で、健康なうちからデジタルデータの整理をしておくことをお勧めします。
四つ目は、情報管理ソフトを利用することです。
管理ソフトを使って情報をひとまとめにしておくと、遺された遺族も手続きを進めやすくなります。
無料で利用できるソフトも多いので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
五つ目は、死後に追悼アカウントへ切り替えるための手続きを生前から進めておくことです。
追悼アカウントとは、故人が生前に利用していたSNSアカウントを残し、遺族や故人を知る人々が思い出を共有するために使用できる状態にするサービスです。近親者にアカウントを管理してもらうことで、死後、アカウントが乗っ取られる危険性を防ぎます。
SNSのサービスごとに特徴は異なりますが、「閲覧や追悼コメントの受け付けは可能で新規投稿やダウンロードはできなくなる」「遺族や限られた知人のみ閲覧可能」などの状態になります。
六つ目は、遺言で遺品整理について記載しておくことです。
正しい形式で作成された遺言書は法的効力をもち、所有するデジタル遺産を明らかにしたり分割の指定に有効です。
法務局などで安全に保管される場合が多いので、エンディングノートよりも確実に保管・発見されますが、決められた形式で書く必要があるため作成に手間がかかります。
なお、デジタル遺品の整理については、遺言書の「付言事項」に記載する内容に当たるため、法的な拘束力を持たないことに留意しましょう。



まとめ
デジタル遺品は、家具や日用品などの実態のある遺品とは違って、「情報」を扱うことから問題が出やすいので、解決方法をしっかり理解しておくことが大切です。
デジタル遺品整理の最初の段階としてデータを調べる必要があるのですが、電子機器にロックがかかっている場合、素人が取り掛かるとデータが消える恐れがあるので、専門業者に依頼しましょう。ここでつまずいてしまうと先に進めなくなってしまいます。
特にデジタル遺産が存在するのでしたら、遺産相続のトラブルを回避するためにも遺族や相続人にその情報を共有し、話し合う場を設けることをお勧めします。
また、デジタル遺品には故人の知られたくない情報、遺族が知りたくない情報も入っている場合があります。
デジタル遺品を遺す側が今からできることとして、デジタルデータの生前整理をお勧めします。データの整理・削除のほか、IDやパスワードの一覧を残しておくことも遺族の負担軽減につながります。
身近な方が亡くなった場合、安心安全に遺品整理を進めていきましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。





















