死亡診断書の発行方法は?費用は掛かる?その内容を詳しく解説

「死亡診断書」とは、読んで字のごとく、死亡を診断する書類であり、人が亡くなった事実を証明する際に法律上で必ず必要となる書類です。
死亡診断書が発行されて初めて法的に死亡が認められることになるため、故人の火葬許可書または埋葬許可証を取得するために欠かせない書類になります。
本記事では、死亡診断書とは何か、その発行方法、提出方法、費用について解説します。



死亡診断書とは?
死亡診断書とは、人の死亡を医学的・法的に証明する書類です。そして、死亡診断書がない状況では火葬・埋葬はできません。
加えて、保健・医療・福祉分野における行政の基礎資料となる「死因統計」を作成するための貴重な資料となるのが死亡診断書です。
法律的に死亡を証明するためには、前提として確かな医学的知見に基づく証明が必要です。そのため、記入者は医師、歯科医師に限られます。
また、死亡診断書が発行されない限り、法的には故人は引き続き生存しているとみなされるため、課税や年金支給なども継続することになります。そういった観点からも法的に死亡を証明する死亡診断書は、各種手続きに欠かせません。
■参考:厚労省が作成している記入マニュアル
※この資料は毎年度更新されます。
死亡診断書に記載される内容
死亡診断書には、以下の内容が記載されます。
- 故人の氏名・性別・生年月日
- 死亡日時
- 死亡した場所とその種別
- 死因
- 外因死の追加事項
- 1歳未満で病死した場合の追加事項
死亡診断書には所定の様式があり、故人が死亡に至るまでの経過などといった医学的・客観的事実を医師が可能な限り詳細に記入することと定められています。
死亡診断書は、故人のさまざまな情報が記載されている大切な書類です。診断書が発行されたら、内容に誤りがないかをしっかりと確認するようにしましょう。
死亡診断書は医師しか作成できないの?
基本的に、死亡診断書は医師・歯科医師が作成するものとして法律で義務付けられています。ただし、歯科医師は「死体検案書」の作成・発行はできません。
在宅医療が増えている昨今においては(参考:厚生労働省「在宅医療について」)、平成29年に「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」が厚生労働省より発出されました。
このガイドラインでは、看護師が患者の元へ向かい、患者の容体をテレビ電話などを用いて医師に伝え、それを元に医師が遠隔で患者の状況を把握し、死亡の確認や異常がないことを判断することを可能にしています。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書と死体検案書は、同じような様式の書類ですが、違いを大まかに言うと、故人が死亡したときの状況の違いです。
具体的に説明すると、死亡診断書とは、故人が生前に医師の診療を受けていた傷病で亡くなったと認められた場合に発行されます。一方で死体検案書は、故人が突然死や交通事故、自死など、医師が診断した病気以外で亡くなった場合に警察医から発行されます。
死亡診断書の発行方法
医師がどのように発行するかは故人の死亡時の状況により異なってきます。
原則的にバイタルサイン(※)の消失として、下記の三点を確認して判定します。
(脳死の場合は、別の規定による)
- 自発呼吸の停止
- 心臓・脈拍の停止
- 瞳孔拡大(無反応)
※生命徴候。「脈拍」「血圧」「呼吸」「体温」の四つの項目を基本として(状況によっては、「意識レベル」「尿意」も含める)、全身状態の変化を見る
故人が入院していた場合
病院に入院していた故人が、その入院先でなくなった場合には、担当医師が死亡診断書を発行します。
故人が自宅で息を引き取った場合
自宅で亡くなった場合(≒医師が故人の死亡に立ち会えなかった場合)には、故人が通院して診療を受けていたか否かによって発行手続きが異なってきます。
何らかの傷病のため病院で診療を受けており、その傷病が死因となって(または関連して)死亡した場合には、診療に当たっていた担当医師が死亡診断書を記入・発行します。
医師による遺体の診察の結果、生前に診療を受けていた傷病に関連する死亡であることが確認できれば、同医師が死亡診断書を発行します。
なお、生前における最終の診察後24時間以内の死亡の場合は、死亡後に改めて診察を行わなくても「生前に診療を受けていた傷病に関連する死亡である」と判定できるのであれば、必ずしも死亡後の診察は不要とされています。
一方、故人が傷病の診療を受けていない状態(昨日まで元気にしていたのに今朝急に亡くなったなど)で死亡した場合には、警察に連絡し、検死(状況に応じて、検視・検案・解剖)が行われます。
この場合、発行されるのは死亡診断書ではなく、死体検案書となります。死亡診断書のフォーマット名は「死亡診断書(死体検案書)」となっており、様式としては死亡診断書と死体検案書と同様です。
死亡診断書と死体検案書の違いを簡単に言えば、医師の診療のもとで死亡が確認され発行されるのが死亡診断書、急死や孤独死などにより警察の介入を受けて発行されるのが死体検案書ということです。
死亡診断書ではなく死体検案書となる他のケースとしては、生前に診療を受けていた傷病以外の死因であると判定される場合、死亡時の状況に何らかの異状が認められる場合、不慮の事故による死亡の場合などがあります。
関連記事
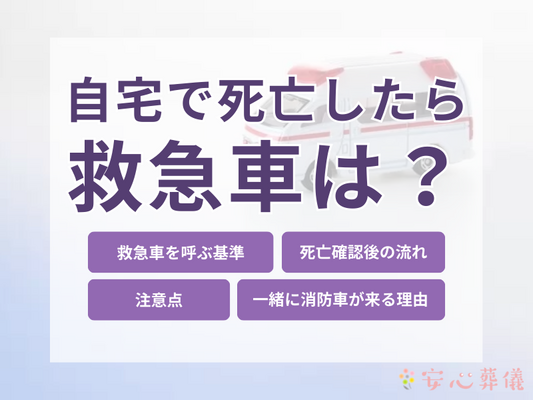
自宅で死亡した場合に救急車は呼んでもいい?適切な対処についても解説
外出先から帰宅したら祖父が意識を失い倒れていた、朝起きて気づいたら妻が息をしていなかったなど、大切な家族の一大事に冷静でいられる人はなかなかいません。 このような一大事に遭遇したとき、まず救急...
続きを読む
故人が事件や事故に遭った場合
事件や事故に遭って病院に搬送後に診察を受けたもののそのまま亡くなった場合は、故人が入院していた場合と同様の流れで発行されます。死因に関して不審な点や不明点がある場合は、検視や検案、それでも判定できないときは解剖が行われ、死体検案書が発行されます。
なお、事故直後は軽傷であったが一週間後に突然死するというケースもあり、その死に対する事故との因果関係が問われることもあります。死亡保険の補償内容においては、病死と事故死では死亡保険金の額にも大きく影響するからです。
関連記事
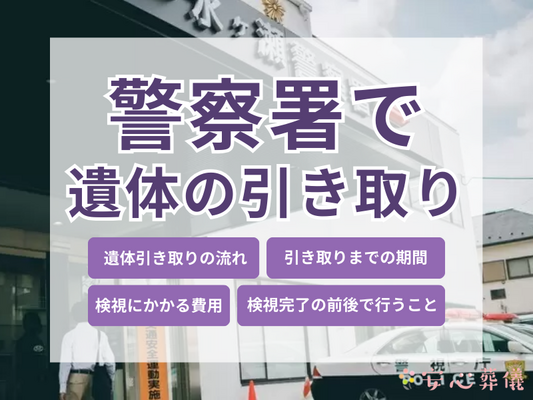
警察署でご遺体を引き取るまでの段取りとは?検視の流れや費用も紹介します
事故死や変死で亡くなった時や、死因が不明な場合などは、監察医による検死が行われます。遺族は検死が終わるのを待ち、警察からの連絡を受けて遺体を引き取ります。 初めて当事者となった遺族には、戸惑うこ...
続きを読む
故人が施設に入居していた場合
入居した施設先で亡くなった場合で、担当の医師が故人をみとったのならば、その場で死亡診断書が発行されます。担当の医師が故人の最期に立ち会えなかった場合は、改めて担当の医師が施設へと出向き、診察を行った上で死亡診断書が発行されます。



死亡診断書発行時に掛かる費用
死亡診断書の発行に掛かる費用は平均すると5000円程度になります。
死亡診断書の発行には、健康保険が適用されません。医療機関が独自に決められる金額になるため、一通当たりで3000円〜2万円程度まで幅があります。
また、死体検案書では費用が異なり、こちらは3万円〜10万円程度が必要になります。死体検案書の場合、死因調査のための検案や遺体の搬送、保管などに料金が掛かるためです。
死亡診断書の提出方法
医師から受け取った死亡診断書は、死亡届とセットになっています。用紙の右側半分が死亡診断書、左側半分が死亡届です。
死亡届に必要事項を記入した上で署名・捺印(認印)し、死亡診断書とともに故人の死亡地か本籍地、または届出人の居住地か住民登録している住所地の市区町村役場に提出します。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3カ月以内となります。
死亡届・死亡診断書を提出する義務のある人は「届出義務者」と呼ばれ、「同居の親族、その他同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」(参考:「戸籍法第87条」)とされています。また、同居の親族以外の親族も届け出ることができます。
死亡届には届出人の署名・押印が必要ですが、記入済みの書類を役所の窓口(24時間受付)へ提出するのは、他者の代理でも構いません。一般的に、葬儀社が代行提出をサービスとして行っていることも多くあります。その際、併せて火葬許可証の取得も代行してもらいます。
死亡届・死亡診断書は提出後に返却されないので、後日必要となってくる各種手続き(金融機関や保険会社での手続き、年金関連の手続きなど)のために死亡診断書の方のコピーを 10枚ほど取っておくとよいでしょう。
ただし、提出先(各保険会社など)によっては、その会社や団体の独自の書式があり、そ れを死亡診断書を書いた医師に、あらためて発行してもらうこともあります。
また、提出を他者や葬儀社に代行してもらう場合、その書類の内容がかなり深遠な「個人情報」(同時に「故人」情報)であることを充分に認識してください。届け人の認め印なども預けることになりますので、代理提出者への信頼と信用を見定めてから渡すことが肝心です。
関連記事

死亡届の書き方とは?提出場所や期日なども紹介
「死亡届」は人が亡くなった際、最初に必要となる公的な書類です。 その後のさまざまな手続きでも必要とされることが多く、正確に記入して、期日までに所定の場所へ確実に提出しなければなりません。 こ...
続きを読む



死亡診断書を再発行するには?
コピーを取り忘れるなどで、手続きのために死亡診断書が必要なのに手元にない状況になった場合は、条件付きで再発行が可能です。このときにもらえるものは「死亡届の記載事項証明書」という、死亡届の写しになります。再発行を依頼できる機関は、死亡届を提出してからの時間によって異なるので、注意しましょう。
- 死亡届を提出してから約1カ月以内→提出した市町村役場
- 死亡届を提出してから1カ月以降→故人の本籍地を管轄する法務局の戸籍課
なお役所から法務局へ書類が送付されるスケジュールは、自治体によって若干差があります。そのため、再発行を依頼する際には事前に死亡届がまだ役所にあるのか、それとも法務局に送付されているのかを問い合わせてから依頼にいくのがよいでしょう。
死亡診断書の再発行ができるのは、3親等以内の家族、もしくは配偶者のみに限られています。依頼する際には「身分証明書」「戸籍謄本」「委任者からの署名・押印がある委任状」が必要です。
死亡診断書の再発行は以下の手続きに使用するときのみ可能となります。
- 年金関連の手続き
- 100万円以上の郵便局の簡易保険の支払いの手続き
これは詐欺などの不正利用の防止のためです。これらの特定の使用理由に該当しない場合や、原本が欲しい場合は死亡診断書を発行した病院や施設に再発行を依頼します。
死体検案書については、警察署で再発行してもらえます。費用については、死亡診断書の発行時と同じ程度掛かります。
まとめ
死亡診断書の発行や費用について説明してきました。最後に重要なポイントを箇条書きにまとめてみます。
- 死亡診断書は、通常は死亡届と一体となって印刷されており、死亡を医学的・法的に証明する書類で、人の死去にまつわるさまざまな手続きに必要
- 死亡診断書がないと火葬・埋葬が許可されない
- 死亡診断書を記入・発行するのは、医師または歯科医師
- 故人が入院先で亡くなった場合は、担当医師が発行する
- 故人が自宅で亡くなった場合で、生前に何らかの傷病の診療を受けていたときは、診療していた医師が発行する
- 故人が自宅で亡くなった場合で、生前に診療を受けていなかった場合は、警察に連絡。警察医から死体検案書が発行される
- 死亡診断書は死亡届とともに市区町村役場に提出する。葬儀会社が提出を代行することもある
- 死亡診断書発行に掛かる費用には幅がある。利用している病院などが分かっていれば、事前にホームページなどで確認を
死亡診断書に関する取り扱いの注意点をふまえて、万が一のときには慌てないよう冷静な対応が取れるようにしましょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。





















死亡届・死亡診断書は左右一枚の書式になっています。死亡届の方は遺族が記入。診断書は医師が手書きします。時々発行の日付など、つい未記入などの場合もありますが絶対他者が書き足さないように。違法になります。