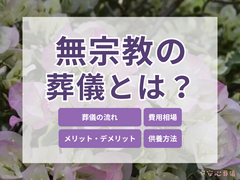神道の葬儀の流れやマナーを解説

葬儀は宗教によって、やり方が大きく異なり、仏教と神道でも流れや作法に大きな違いがあります。
現状、仏教に基づいて行われる葬式が多数と言われていますが、神道は古来より日本独自の宗教として信仰されており、神道で行われるお葬式も全国各地で見られます。
しかしながら、神道のお葬式に参列する機会は少ない事もあり、神道の葬儀については知らない方が多いようです。
そこで今回は、神道の葬儀の流れ、作法、費用などを総合的に解説していきます。



神道の葬儀
神道の葬儀は「神葬祭(しんそうさい)」とも呼ばれます。神社の宮司による司式のもとで行われる葬儀です。神道では、亡くなった方は神様の世界へと帰って行き、子孫を永久に見守ると考えます。その考えから、神葬祭での儀式の意味として、故人が子孫達の守り神になってもらうために行うということになります。
神葬祭には「先祖崇拝」と「穢れ」の二つの大きな意味合いがあります。「気が枯れる」とも書くこともある穢れは、生きる力が減衰した意味であり、その悪い穢れの状態を、お払いをすることで清められるということです。
神葬祭を行う意味には、普段の何気なく幸せで平和な日々に戻すという意味があります。
また、先祖崇拝は、私たちのご祖先様が、守り神として一族全てを永久に守ってくれる存在だと考えます。
神葬祭を行うことで、亡くなった方は祖先神(そせんしん)となり、霊璽(れいじ)に故人の御霊(みたま)を移し、祖霊舎(それいしゃ)にお祭りすることで、一族全てを永久に守ると考えられています。神道の歴史は古く、古墳時代にはその原型ができたと伝えられていますが、公に神葬祭が行われるようになったのは江戸時代以降のことです。
それでは、神道で行う葬儀について、主な特徴を解説します。
神道のお葬式の特徴
ここでは仏教式の葬儀との比較も交えながら、神道式の葬儀について特徴を挙げていきます。
諡号
諡号(しごう)とは、故人をたたえる意味で死後に授けられる名前で、「諡(おくりな)」「諡名(おくりな)」と呼ばれることもあります。
本来は神道の葬儀とは関係なく、皇族など地位の高い方に対して生前の功績をたたえるために、故人に対する尊敬の意を込めた呼び名として諡号がありました。神道では、全員に諡が平等に付けられます。
また、中国における「第3者が、他人を本名で呼ぶことは失礼に当たる」という考え方も、諡号を故人に送る慣習ができたことに影響していると言われています。
仏教での戒名に当たるものが神道では諡号と捉えられています。
ただし、諡号は戒名のように階位による差はなく、基本的に年齢と性別で異なります。
| 男子 |
女子 |
|
|---|---|---|
|
幼児(5歳くらいまで) |
稚郎子(わかいらつこ) |
稚郎女(わかいらつめ) |
|
少年(10歳くらいまで) |
郎子(いらつこ) |
郎女(いらつめ) |
|
青年(15歳くらいまで) |
彦(ひこ) |
姫(ひめ) |
|
成人・壮年(60歳くらいまで) |
大人(うし) |
刀自(とじ) |
|
老年 |
翁(おきな) |
媼(おうな) |
上記は諡号の付け方の例です。神社や地域によっては、さらに細かく年齢などによる区分をしている場合もあります。
そして神道の場合、故人の名前は「生前の本名+諡号+命」で決まり、この名前全体のことを諡と呼ぶ場合もあります。「命(みこと)」は尊号と呼ばれ、諡号の後ろに付けられる称号です。
命は、読み方は同じですが「尊」という字が使われることもあります。なお、命は「みこと」と読みますが、諡号に続いて読むときには「~のみこと」と読みます。
例えば、鈴木一郎さんが成人で亡くなり、神道で葬儀を行う場合には「鈴木一郎大人命(ずすきいちろううしのみこと)」となります。
関連記事

神道は戒名がない?諡(おくりな)のつけ方も紹介します
多くの人が、墓石や位牌に刻まれた戒名を一度は目にしたことがあるでしょう。戒名は仏教徒に授けられる名前です。 それでは、仏教ではなく神道を信仰している方が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。 ...
続きを読む
玉串奉奠
仏式葬儀での焼香やキリスト教式葬儀での献花に当たるものが、神道式葬儀では「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」です。
参列者が玉串に自分の心を託して神に捧げ、祭壇に奉納します。
このときに使う玉串とは、榊の枝に「紙垂(しで)」と呼ばれる特別な断ち方をして折った紙を「木綿(ゆう)」という麻で結んだものです。沖縄などではガジュマルの枝が用いられることがあります。
玉串に使用する枝は、本来であれば常緑樹なら何でもよいとされていますが、一般的には榊(さかき)という常緑樹が使用されています。
この玉串を故人に対して手向けることを玉串奉奠と言います。玉串奉奠は、神道の葬儀において参列者一人ひとりが行うものとなります。
神道の儀式において榊は重要なものです。玉串の起源は古く、天照大御神の天の岩戸隠れの神話に由来していると言われています。語源も諸説あり、神前に手向けるために手向串(たむけぐし)と呼んだのが変化したという説や、木竹(串)に玉をつけたものだったために「玉串」と称した説があります。
また玉串を神様に捧げて拝礼する玉串奉奠は神式のお葬式で行うことが多いですが、その他にも祈祷式や、神前の結婚式である神前式等にも行われます。
お墓
神道のお墓については、仏教式のお墓と異なる部分がいくつかあります。
- 戒名は彫刻されない
仏教のお墓には一般的に戒名が彫刻されますが、神道のお墓では戒名ではなく諡(故人の本名+諡号+命)が彫刻されます。 - 奥津城
仏教のお墓では「〇〇家之墓」と彫刻されますが、神道のお墓では「〇〇家奥津城」または「〇〇家奥都城」と刻まれることが一般的です。
「奥津城」も「奥都城」も「おくつき」と読み、現代風に噛み砕くと「~の眠る場所(墓所)」という意味になります。 - 形状
神道のお墓は、竿石(お墓で一番目立つ縦長の石)の上部が尖っています。これを「兜巾型(ときんがた)」と呼びます。三種の神器のうちの一つである「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ」を模していると言われています。
また、仏教のお墓には香炉がありますが、神道では八足台(はっそくだい)という玉串奉奠を行うための台が設けられます。 - 神社にお墓は建てない
仏教であれば寺院の敷地内に墓地がありますが、神道では死を穢れとして捉えるため神社の敷地内に墓地が設けられることはなく、当然お墓も建てられません。 - 祖霊舎(みたまや)
仏教でいうところの仏壇に当たるものが神道では祖霊舎です。祖霊舎は「それいしゃ」と読む場合もあります。
ただし、仏壇は本尊を祀るためのものですが、祖霊舎は神様ではなく先祖の霊を祀るためのものという根本的な違いがあります。 - 神棚封じ
神棚封じとは、家族の誰かが亡くなったときに、家にある神棚を封じることです。神道では死は穢れと考えているので、神と死を遠ざけるために神棚封じが行われます。神棚封じは、忌中である50日間行います。
神道の葬儀の流れ
神道の葬儀では、神社の宮司によって式が進められていきます。神道の葬儀はどのように進められていくのでしょうか。
神道の葬式の流れ
ここでは神道の葬儀について、臨終を迎えたところから順を追って見ていきましょう。
臨終~納棺
- 臨終
医師の死亡診断を受け、葬儀社の手配をします。特定宗教宗派のみを対象とした専門葬儀社を除いて、ほとんどの葬儀社で神葬祭も対応できます。なお、仏教で行う末期の水は、神道では行いません。 - 帰幽(きゆう)報告
神棚や祖霊舎に向かい神様や先祖に対して、帰幽(死者が出たこと)を報告します。この際、神棚封じとして神棚や祖霊舎の扉を閉め、その前に白い半紙など縦長の白紙を貼ります。 - 枕直しの儀
故人の頭を北向き、または部屋に向かって右側(上位の場所)の向きになるようにして安置します。 - 納棺の儀
棺は、紙垂を下げた注連縄(しめなわ)が巻かれたものを使用することが特徴になります。仏教でいう湯灌にあたる沐浴(もくよく)を行ってから納棺を行います。
仏教では納棺の際、旅装束を整えますが、神道では神様になるための姿として、男性は白丁(はくちょう)、烏帽子(えぼし)、笏(しゃく)、女性は白い小袿(こうちき)、扇が死装束として用意されます。
通夜祭・遷霊祭
- 通夜祭
仏教の通夜式に当たるものが、通夜祭です。通夜祭では主に下記が行われます。
修祓(しゅうばつ・しゅばつ)…祭壇や参列者に対してお祓いをします。
斎主一拝(さいしゅいっぱい)…故人に対して斎主(さいしゅ)にならって全員でお辞儀をします。神社の宮司で葬儀の司式を行う方のことを、葬儀の場では斎主と言います。
献饌(けんせん)…神様に供え物をする作法を行います。
祭司奏上(さいしそうじょう)…斎主が故人の経歴や人柄を述べて、その安らかな死を祈ります。また、遺族や子孫を守ってくれるように故人に願います。
玉串奉奠…参列者全員が一人ひとり、玉串を故人に手向けます。 - 遷霊祭
故人の霊を霊璽(れいじ)に移す儀式です。この儀式は、「御霊移し(みたまうつし)」と言われることもあります。霊璽は仏教でいう位牌のようなものです。
霊璽には、神職から命名された故人の姓名の後に「〜霊」「〜之霊」「〜霊位」などが付く霊号を文字入れします。霊号以外には、裏面に亡くなった日付や享年が記されることがあります
また遷霊祭で霊を霊璽に移す際には、式場内を暗転させて、真っ暗な状態で行われます。地域によっては通夜祭と遷霊祭を分けるのではなく、一連の儀式の流れの中で、「遷霊の儀」を行うこともあります。 - 直会
通夜祭、遷霊祭のあとには直会(なおらい)という食事の席が設けられ、参列者などをもてなします。
葬場際~帰家祭
- 葬場祭
基本的には通夜祭と同様の流れで進められていきます。葬場祭を斎場など別の場所で行う場合は発柩祭(はっきゅうさい)を行います。ただし最近ではこの発柩祭は省略される場合が多くなっています。
斎主による儀式、参列者による玉串奉奠が行われた後は、故人と遺族親族との最後のお別れの時間、出棺へと移行していきます。 - 火葬祭
火葬場の炉前で火葬祭としてお祓い、祭司奏上、玉串奉奠などが行われます。 - 埋葬祭
埋葬祭はお墓への納骨を行う際に行われるもので、お祓い、祭司奏上、玉串奉奠などが行われます。火葬後にそのまま墓地へ移動して埋葬祭を行うこともありますが、お墓の準備が整っていない場合など、後日埋葬祭を行うこともあります。 - 帰家祭
仏教でいう還骨回向(かんこつえこう)に当たるものが帰家祭(きかさい)です。神様や先祖に対して葬儀を終えた旨を報告します。 - 直会
帰家祭が終わったあと参列者へのねぎらいや感謝の気持ちを込めて直会の席が設けられますが、火葬後や火葬中に直会を行う場合もあります。
具体的な流れ
- 手水の儀(ちょうずのぎ・てみずのぎ)
手水の儀とは、葬儀場に入る時や帰宅した際に手を清めることです。
ひしゃくで水をすくい、左右の手を清めた後、左手に水をためて口を清め、最後に左手をもう一度清めることです。 - 修祓の儀(しゅうばつのぎ)
斎主と呼ばれる神官に、大幣でお祓いしてもらう儀式のことです。 - 開式の辞
修祓の儀まで終わると、喪主や司会者から葬儀の開始が案内されます。 - 献饌の儀(けんせんのぎ)
神前にお供え物(米・酒・もち・魚・野菜など)を供え、伶人(れいじん)が雅楽を演奏する儀式です。 - 祭詞奏上・誄歌奉奏(さいしそうじょう・るいかほうそう)
神職が神前で祭詞を読み上げ、伶人が雅楽を演奏します。 - 弔辞拝受・弔電奉読
寄せられた弔辞や弔電を読み上げます。 - 玉串奉奠(たまぐしほうてん)
神職が玉串と呼ばれる紙の幣をつけた榊(玉串)を、神前に供える儀式です。 - 参列者の玉串奉奠
故人との関係が近い順番で喪主、親族、参列者と玉串奉奠を行っていきます。 - 撤饌の儀(てっせんのぎ)
神前にお供えしたお供え物を下げるための儀式です。 - 閉式の辞
葬儀が終わったことを宣言します。 - 直会(なおらい)
葬儀終了後には、神前にお供えしたお供え物を参加者全員で食べます。
神様と同じものを食べることで「神様のお力を分けていただく」との考えで行われます。
出棺後の流れ
出棺のときに行われるのが「出棺祭」です。出棺祭では一般的な葬儀と同じく、喪主からお礼が述べられ、火葬場へ向かいます。
火葬場に到着すると斎主が祭詞を奏上し、遺族や参列者が玉串を捧げた後に火葬が行われます。火葬が終わると、仏式と同じように骨上げを行います。
その後、埋葬祭が行われてお墓に納骨するのですが、最近ではいったん遺骨を持ち帰り、忌明けとなる五十日祭に合わせて行うこともあります。
葬儀が終わり帰宅する際にも、塩や水で手を清めてから家の中に入るようにしましょう。



神道の葬儀の作法

遺族として神道の葬儀を営む立場になったとしても、神道の葬儀に参列する立場になった場合でも、神道式のマナーや作法を知っておきたいところです。
礼拝の作法
礼拝の仕方
神道での礼拝の作法は「二礼二拍手一礼」で表わされています。2回深めのお辞儀をして、2回拍手をして、最後にもう一度深めのお辞儀をするという方法です。
深めのお辞儀とは、腰を90度に近い角度まで折り曲げるくらいのイメージです。なお、拍手については「しのび手」と呼ばれる作法で音を立てずに手を合わせて行います。
また手を合わせるときには、右手を少し下に引き、両手をぴったりと合わせるのではなく、ずらすようにします。これは神様より一歩下がり、神様を崇拝する気持ちを表すためと言われています。
少数派ではありますが、神社によって「二礼四拍手一礼」や「三礼三拍手一礼」の場合もありますので、実際の葬儀においては、それぞれの神社の作法に従うようにします。
玉串奉奠
基本的には、斎主など神社関係者、遺族、親族、一般参列者の順に玉串奉奠を行っていきます。自分の順番になったら、次の手順で玉串奉奠を行います。
- 喪主、遺族に一礼します。その後、神社の方か葬儀社スタッフから玉串を一礼してから受け取ります。両手で受け取りますが、基本的には右手、左手の順で手を添えて受け取る方法が正式です。
- 玉串は左手側に葉先、右手に根本という向きで、みぞおち辺りで両手に持ち、そのまま玉串を捧げる台まで進みます。この際、左手は玉串の葉先を下から支える形で持ち、右手は根元を上から手を覆い被せるような形で持ちます。
- 神前に一礼します。
- 玉串を正面に立てるように、玉串を持つ左手を根元にして右手を葉先に持ち替え、玉串を時計回りに地面と平行に回転させ、根元が神前に向くようにして捧げます。
- 玉串を捧げたら礼をして、二礼二拍手一礼をします。二拍手のときは、音を立てないよう特に注意が必要です。
- 少し下がって神社の方々、喪主や遺族に軽く礼をしてから自席に戻ります。
持ち物や服装
持ち物や服装のマナーについては、数珠が必要ないという点を除いては仏教の葬儀に参列する場合と同様です。
ダークスーツや地味な色の服装
急いで駆け付ける場合には、男性であればダークスーツや地味な色の服装でもよいでしょう。ただし、それ以外は喪服が基本となります。
男女ともに、喪服として販売されているものを着用するのが基本的マナーです。
なお男性の場合、ジャケットはダブルでもシングルでも構いません。
女性の場合にはアンサンブル、ワンピース、スーツなどいろいろなスタイルがありますが、アンサンブルを着ている方が多数です。スーツやワンピースは、色やデザインが地味なものを選ぶようにしましょう。
派手なアクセサリーは避ける
婚約指輪、結婚指輪以外のアクセサリーは外しておくことが基本です。一部例外として、真珠のアクセサリーは付けてもよいと言われています。
真珠以外のアクセサリーは避けるようにしましょう。また真珠も二連や三連のものは不幸が重なると言われているためマナー違反になるので注意が必要です。
もちろん、時計もアクセサリーと同様に派手なものは避けましょう。特に葬儀の場では金色の装飾品は避けるのがマナーです。
その他の持ち物、服装の留意点
男性の場合、ワイシャツは白色、ネクタイ、靴、靴下は黒色です。女性の場合、インナー類、靴など全て黒色となります。
なお、子供が参列する場合、学生ならば礼服があれば着用しますが、持っていなければ学校の制服を着用される方が多数です。
また、制服を持っていない子供は、黒や紺などダーク系の洋服を着用すれば問題ありません。
繰り返しになりますが、仏式の葬儀で使われる数珠は神道の葬儀では必要ありません。
関連記事

神道式の「神葬祭」の流れとは?仏式との違いも解説
葬儀と聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは仏式の葬儀ではないでしょうか。 実際、日本で葬儀の大半を占めるのが仏式の葬儀と言われていますので、神道形式の葬儀に参列したことがないことはごく普通のこ...
続きを読む
神道の葬儀のお供え

仏教の葬儀でもお供え物をしますが、神道の葬儀において、お供え物は欠かせないものであり、神式葬儀をする場合には特に注意して準備が行われることの一つです。
ここでは神道の葬儀で行われるお供え物について説明します。
神道の葬儀のお供えについて
神道において神様に献上する食事のことを「神饌(しんせん)」と呼びます。この神饌が神様に対するお供え物の中心です。
仏教ではお供え物として生花が好まれますが、神道の場合は神様に献上する食事ですからお供え物は飲食物がメインになります。特に花を供えることがマナー違反ということはありませんが、神道では花を飾る風習がないため避けた方がよいでしょう。
お供え物の内容
お供え物の神饌としては次のようなものがあります。基本的には、調理または加工したものではなく、素材そのままのものをお供えします。
米であれば、炊いたものではなく、生米(精米したもの)のままで供えられます。
神饌には、米・酒・餅・川魚・海魚・野鳥・野菜・海菜・水鳥・野鳥・塩・水・菓子などが選ばれます。
|
常饌(じょうせん) |
米、塩、酒、水、餅、豆類など |
|
海の魚 |
鯛、かつお、ブリなど |
|
川の魚 |
鯉、ニジマスなど |
|
野の野菜 |
きゅうり、大根、山芋、茄子など |
|
海の野菜 |
昆布、わかめ、ひじき、寒天など |
|
山の果物 |
みかん、ブドウ、梨、バナナなど |
|
その他 |
菓子類 |
その他、乾物という括りで、鰹節やスルメや煮干しが加わることもあります。
これら全てをお供えしなければならないということではなく、神饌の内容は神社によって異なってくるため、実際の葬儀では神社に確認をしてから用意することになります。
例えば、スルメは乾物ではなく、海の魚という扱いにする神社もあります。通常、葬儀社が神社に確認を行い、これら神饌の手配も葬儀社が行ってくれます。
お供え物を並べる際の順番がある
お供え物は、米、酒、餅、魚、乾物、野菜、果物、塩、水の順番で並べるケースが多く見られます。
祭壇の中心部の奥手を最も上位の場所として、その次は最上位の右隣り、その次は最上位の左隣りといった順番で中心から広がるように並べていきます。
ただし、並べる順番も神社によって異なる場合があります。神饌の手配と同じように、並べる順番についても葬儀社が神社に確認を行います。



神道の葬儀の香典
神道では香を焚きませんので香典という言葉は使いませんが、お金を包んで持参することは仏教での葬儀と同じくあります。
ここからは、正式な名称ではありませんが「香典」と称して解説していきます。
香典袋の表書きの書き方
神道の葬儀で、香典に当たるものは「御榊料(おさかきりょう」、「御玉串料(おたまぐしりょう)」、「御神前(ごしんぜん)」などと呼ばれます。
香典袋の表書きにも「御榊料」、「御玉串料」、「御神前」などと書きます。
香典袋についてのマナー
神道での香典袋は白いシンプルなものを使います。また水引は、黒と白の結び切りのものを選びましょう。
蓮の花が書かれているものは仏教用なので、神道での葬儀のときは避けるように注意が必要です。
香典の金額の相場
宗教による金額の差はなく、仏教でもキリスト教でも神道でも包む金額に差異はありません。包む金額は、主に故人や遺族との関係性や、自身の立場や年齢によって変わってきます。地域によっても異なりますが、下記が相場と言われています。
- 家族および親族内で不幸があり、葬儀に参列する場合:約1万円~10万円
- 知人や友人の身内で不幸があった場合:約5000円~1万円
- 近所の家や職場で不幸があった場合:約3000円~1万円
神道の葬式の費用
神道で葬儀をした場合、多くの方がどれくらいの費用が掛かるのかが気になるでしょう。仏教で葬儀をした場合と違いはあるのでしょうか。
ここでは神道の葬式に掛かる費用を説明します。
神道の葬式の費用
神道のお葬式では、全体として約80万円~140万円が相場と言われています。この金額には神社へのお礼は含まれません。
金額に幅があるのは、規模、地域による差、祭壇のグレードなどによるものです。神道の葬式に掛かる費用の特徴は、下記の要素が挙げられます。
費用の相場を決めることは難しい
先に費用相場を紹介しましたが、実際に神葬祭を行った場合にどれくらいの費用が掛かるかは、葬儀の内容によって大きく異なります。
各家庭によって葬儀規模は異なりますし、地域による差などでも金額が上下するからです。葬祭ホールの利用料は、地域による違いが生じやすい項目です。
また、神道の葬式の場合には、依頼する神社によって準備するものや内容が変わる部分が多いという点も費用の相場を決めることを難しくさせる要因でしょう。
費用の目安が難しいので、追加で掛かる料金を事前に説明してくれる葬儀社を選ぶようにしましょう。先にしっかりと説明を受けておくことで、後で高額な追加料金を請求される事態を避けることができます。
また、複数の葬儀社から見積もりをもらって比較してから選ぶようにします。
必要な費用
神式で葬儀をする際に必要な費用は、斎場使用料などの葬儀自体の費用と火葬料や搬送費用、マイクロバス費用なども掛かります。
他にも、香典返しの費用や葬儀後に開かれる直会費用、入京者への読経料・交通費などが掛かります。
神式が安いと思われる理由
神式の葬式は比較的安く行えると認識している方がいます。その理由は、榊が中心なのでお花代が掛からなくて済むということや、仏教のような戒名料が掛からないと捉えられているからです。
しかし実際には、榊は確かに用いますが、供花や生花飾りも使われることもありますので、必ずしもお花代が掛からないということはありませんし、戒名料はなくても神社へのお礼は必要となります。
神式が高いと思われる理由
一方で、神式の葬式は比較的高くなると認識している方もいます。その理由は、祭壇などの商品やサービスの選択肢が少ないことから見積もりが難しいことや、神社に玉串料を支払うことが必要であると考えているためです。
たしかに仏教スタイルの葬儀に比べれば、商品やサービスなどの選択肢は若干少ないかもしれませんが、それほど大きな差はなく、神社に納める玉串料が仏教でいうお布施と比べて特段高額であるということもないでしょう。
費用について世間ではさまざまなイメージがあるようですが、規模などの宗教以外の条件が同じであれば、仏教で行う葬儀と神道の葬儀は費用的な差はほぼありません。
関連記事

神道のお葬式、神葬祭の葬儀費用の相場と内訳
神道のお葬式は神葬祭とも言われます。神道は日本古来より信仰されてきた宗教であり、初詣や七五三など、日本人の多くは神社にお参りに行きます。 しかし、葬儀においては死者供養の役割を仏教寺院が長く担...
続きを読む



神道の葬儀後
神道式の場合、仏教の法要に当たるようなものはあるのでしょうか。
神道では法要に当たるものが霊祭(れいさい)として行われます。
神道では、人は亡くなると、家や家族、子孫を守る神になるという考え方があります。霊祭は、「無事に神様になりますように」「家や家族、子孫をお守りください」と祈る場という意味があります。
神道の葬儀後について
神道の葬儀後には、10日ごとに「毎十日祭(まいとうかさい)」や「旬日祭(しゅんじつさい)」と呼ばれる霊祭があります。
亡くなってから50日目までの期間については、「五十日祭」のみ神社から宮司を招いて行うことが一般的です。
五十日祭を迎えると家庭を守る守護神としての祖霊舎に迎え入れます。そして五十日祭を終えると遺族は忌明けを迎えるのです。
また、五十日祭が行われた翌日には「清祓の儀(せいばつのぎ)」という仏式でいうところの忌明け法要に当たる霊祭が行われます。清祓の儀とは、神棚や祖霊舎に貼ってあった白紙を外し、平常の生活に戻ることを意味するものです。
そして五十日祭から百日祭の間に行われる行事として、合祀祭(ごうしさい)があり、清祓の儀と合祀祭を同日に行うこともあります。合祀祭は、故人の霊を先祖の霊と一緒にお祀りするための儀式です。
五十日祭以降は、亡くなってから100日目の百日祭があり、そのあとは一年祭、三年祭、五年祭、十年祭といった式年祭が続き、一般的には五十年祭にて弔い上げとされています。
なお、霊祭も葬儀同様神社で行われることはなく、葬祭ホールや自宅で行われます。
神道の葬儀の祭壇

神道の葬儀では、八足(はっそく)と呼ばれる白木の台を組み合わせた八足祭壇が使われていましたが、現在は生花で彩られた祭壇など他の形態の祭壇も見られるようになっています。
ですが、神道の祭壇には神道の祭壇として守らなければならない約束事や、用意しなければいけない物品などがあります。
神道の葬儀の祭壇について
神道式の祭壇に関して特徴的なものを紹介します。
三種の神器
神道の葬儀においての三種の神器とは、鏡、曲玉(まがたま)、剣のことです。
祭壇の両脇に日旗(にっき)、月旗(げっき)と呼ばれる細長い旗が備えられ、この旗とともに三種の神器も設置されます。祭壇に向かって右側に日旗と鏡・曲魂、左側に月旗と剣という組み合わせとなります。
神饌
神饌は、先の項目でも説明しましたが、神様へ献上する食事のことです。なお、献上した常餞や魚や野菜などは、その後、家族で食べます。
この献上したものを家族が食べることを「お下がりをいただく」と言います。基本的には食物を無駄にせず全てお下がりとして食べるのですが、魚については葬儀中常温にさらされて傷んでいることがあるので食べることは避けたほうが無難です。
また葬祭ホールでは式場内のスポットライトを照射している関係で、野菜や果物も熱せられて傷んでいることがあるので注意しましょう。
水引幕
水引幕(みずひきまく)は、天井から垂らされた短い幕のことで、祭壇が設置されるスペースとそれ以外の区域や、儀式が行われる会場と会場外などの境界を意味します。または水引幕は結界の役目をし、聖域を守る役目があるとも言われています。
水引幕は白い無地のものが主流ですが、最近ではひだがあるものや染められたものなど、さまざまなものがあります。
幣帛と神輿
幣帛(へいはく)は、神饌以外のお供え物の総称として使われていた言葉です。例えば、布、紙、兵器、農耕具などがお供え物として用いられていました。この中でも布は古代において特に貴重品であるとされ、幣帛の「帛」も布を意味しています。
現在、幣帛は神道の祭壇にお供えしてある串の先に赤い紙を挟んだもののことを意味して使われることが一般的です。この赤い紙は布や紙など神饌以外のお供え物を象徴してお供えされているためです。
また神輿(みこし)と言いますと、お祭りのときに担ぐあの神輿を想像される方が多いかもしれませんが祭壇の一番上の段に設置されている神社の小型版のようなものも神輿と言います。
仏教の葬儀でも祭壇があり、一番上の段には輿(こし)と呼ばれるものが設置されます。仏式祭壇に設置されている輿は、もともと棺に納められた故人を運ぶためのものでした。これに対して神輿は、神様の乗り物という意味合いです。
神様は、神社がない時代においては、山や川などの普段鎮座している場所から、祭事が行われる場所まで神輿に担がれて移動をしていて、それが現代の神式の祭壇に表れているものと考えられています。
大榊
大榊(おおさかき)は、祭壇の両脇に1対で置かれるお供え物です。仏式葬儀のときには生花の盛り篭が供物として祭壇両脇に何基か設置されますが、神式葬儀の場合には榊が供物として設置されます。
なぜ榊をお供えするかというと、榊は神様の世界とこの世をつなぐ境目の木という意味もあるからです。
この供物として設置される榊を大榊と呼びます。全ての供物を大榊で行う地域もありますが、最低限である1対の大榊を供物として出して、それ以外の供物は白系の花を使用した盛り篭で行う場合が多いようです。



神道の葬儀の弔電
神道で行われる葬儀に関して、弔電も神道ならではのマナーがあります。
仏式葬儀のときと同じような内容の弔電を送ってしまうと、失礼に当たる可能性もありますので注意が必要です。
神道形式の弔電の留意点
弔電の文章には、神道以外の宗教用語を使わないということが特に留意したい点です。「成仏」「供養」「冥福」「極楽」「浄土」「往生」は仏教の用語です。「昇天」「召天」「天国」はキリスト教の用語です。
これら仏教やキリスト教の用語は、神道の葬儀で送る弔電には使わないようにします。中でも「冥福」は、「ご冥福をお祈りいたします」のように頻繁に使われている文章であり、誤用しやすいので特に気を付けておきたいところです。
なお、弔電マナーに関するサイトで、「ご愁傷さま」を仏教用語であると紹介しているところがありますが、これは誤りです。「ご愁傷さま」は仏教用語ではありませんので、神道の葬儀では気にする必要はありません。
ただし、「ご愁傷さま」は口頭で使う言葉です。仏教用語であるかどうか関係なく、弔電では使えない言葉なので注意しましょう。
また、神道でも「重ね重ね」や「続きまして」など忌み言葉の使用はマナーに反することになります。これは他の宗教でも同様ですが、不幸を連想させてしまう言葉は、神道形式でも使わないのがマナーです。
他にも生や死を表現する直接的な言葉や漢数字の四や九も基本的には使わないようにしましょう。
もう一点、弔電を送るときには台紙を選ぶことになりますが、蓮の柄が入ったものは仏教をイメージさせるので神道の葬儀では避けた方がよいでしょう。
神道の弔電で用いられる例文
例文1は神道のみで使える内容で、例文2は神道でも仏教でも使える内容となっています。
例文1:御尊父様の訃報に接し、御霊の安らかなることをお祈りいたします
例文2:ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申しあげます。
最後に
今回は、神道の葬儀について、流れや作法、費用など総合的に解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
参列する機会の多い仏教の葬儀と比べると、神道独自の部分がたくさんあることが分かったのではないかと思います。葬儀社にとっても神道の葬儀を担当する機会は仏教の葬儀に比べるとだいぶ少ないのが現状です。
神道の葬儀に詳しい葬祭ディレクターは多くはありません。神道の葬儀での実績や経験のある葬儀社を選択することがよい葬儀を行うためのポイントの一つとなります。
今回の記事を参考にして、よい葬儀につなげてください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。