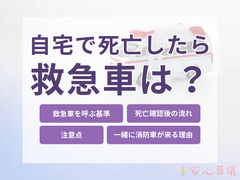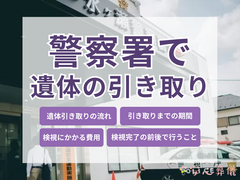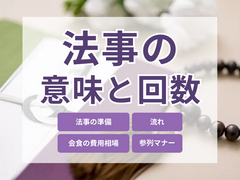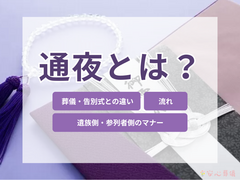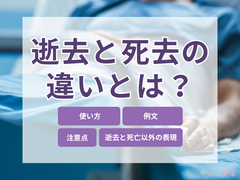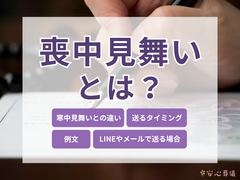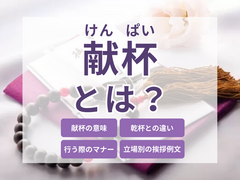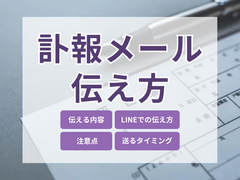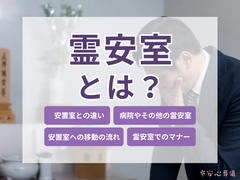永代供養料とは?費用や種類の違いも紹介します

これまでは子供が墓を継承していくことが一般的でしたが、近年は価値観の変化や少子化などの影響から、多くの世帯でお墓の継承が困難になっています。永代供養も、もはや特別な方法ではありません。
しかし、永代供養を考えている人でも、その詳細や費用まで把握していることは少ないのではないでしょうか。
本記事では、永代供養とは何か、永代供養の種類、永代供養料の相場などについて解説します。



永代供養とは
永代供養(えいたいくよう)とは、遺族に代わり寺院や霊園が永代(=長い年月、半永久的)にわたり遺骨の管理と供養を行うことです。
墓を受け継ぎ供養をしていく人がいない、お墓の維持で子供に負担を掛けたくないなどの事情や希望から、永代供養を選ぶ方が増えてきています。
永代とはいっても、個別に安置する期間には限りがあります。寺院や霊園により異なりますが、十七回忌の節目や、「弔い上げ(法要を終了すること)」の区切りとされる三十三回忌までは遺骨を個別に安置し、その後は合祀墓に移すという方法が主流です。合祀とは他の人の遺骨と一緒に共同の墓に納骨することです。
この他、納骨の時点から共同で埋葬する方法もあり、寺院や霊園によって異なるので確認しましょう。
遺骨を預ける際に、寺院や霊園に対し永代供養料を支払います。納骨の際に一括前払いすることが一般的です。
お墓を建てたり管理したりするのにもお金が掛かりますので、「お墓を持つよりも子供に少しでも多くお金を残したい」「お墓を管理する負担をかけたくない」という考えから、永代供養を検討する方が近年は増えてきているようです。
また配偶者がいなかったり、子供がいなかったりとお墓の後継者がいない方が利用することも多いのが永代供養です。
永代供養墓の場合は、土地の使用料や墓石の費用が掛かりません。さらに、いずれ合祀されることや次世代の使用がないといったことからも、継承するタイプの一般的なお墓に比べて価格帯が低いのも特徴です。そのため、お墓の費用をできるだけ抑えたいという方から多く利用されています。
このように永代供養には、「次世代への負担がない」「費用がリーズナブル」という大きなメリットがあります。
ただし、ゆくゆくは合祀されることで、最終的には他の人の遺骨と混ざって埋葬されることになります。一度合祀されると後から取り出すことはできないというデメリットもあるので注意しましょう。
また永代供養は、言葉が似ていることから「永代使用」と混同される場合があります。
永代使用とはお墓を建てるために購入した土地を永代にわたって使用する権利のことです。
墓地にお墓を建て、その土地の使用代として永代使用料を払うのです。
永代供養の種類とは
永代供養とひとくちに言っても、納骨する先のお墓には複数の種類があります。
合祀型
記念碑のようなものや供養塔などの合祀墓(ごうしぼ)に、他の方の遺骨とまとめて納骨されます。個別の納骨はせずに合祀されるため、永代供養の中では一番費用を安く抑えられる方法です。
他の方の遺骨と混ざってしまうため、一度納骨すると取り出せないので、分骨や改葬ができない点に注意が必要です。
本人が希望しているのならば、これらの内容を生前に確認しておき、家族の中で充分に協議する必要があります。親族間でも分骨の希望を確認するなどしっかり話し合い、トラブルにならないようにしましょう。
個別型
個人墓
一般的な墓石同様に、墓石ごとに個別の遺骨を納めます。見知らぬ他の人と同じお墓に納骨されることに抵抗感がある場合や夫婦墓という形式を望む場合などに選ばれることが多いようです。
納骨する人数によって大きさが異なり、金額なども違ってきます。
納骨した施設によっては、一定期間(主に三十三回忌)が経過すると合祀される場合があるため注意が必要です。この期間は墓地によって違うので気になる方は確認しておきましょう。
納骨堂(ロッカー型・霊廟型)
納骨堂などの屋内施設に納骨します。屋内でお参りができること、比較的交通の便が良い場所にあることなどがメリットです。
納骨堂にはコインロッカーのような箱の内部に骨壺を安置するロッカー式、仏壇のような壇が並んだ霊廟型(仏壇型)などがあります。
自動で遺骨を収蔵した厨子が運ばれてお参りができる納骨堂もあり、「機械式納骨堂」や「自動搬送式納骨堂」などと呼ばれています。常時お参りできる状態で納骨されるのではなく、骨壺は格納場所に安置されます。関係者がお参りに来ると専用ICカードなどで認識され、対象の骨壺が納骨堂内のお参りするスペースまで都度機械で自動搬送されます。
樹木葬
墓石の代わりに樹木を使用し、それを墓標として納骨します。
一つの大樹を墓標にして周囲に複数の遺骨を納骨する場合や、個別に1本の樹木を植える場合があります。
自然葬のように草花などで囲ったガーデンのような場所が用意されていて、そこに埋葬する形式も増えてきています。
樹木葬も故人がどこに眠っているのかわかるため、故人を身近に感じながらお参りすることができます。
樹木葬については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
関連記事

樹木葬とは?流れや費用、トラブルについても詳しく紹介
「樹木葬」という言葉を聞いたことがありますか?樹木葬は、近年メディアなどで取り上げられる機会も増えてきたため、聞いたことがあるという方もいるかと思います。 葬式が終わると、遺骨は納骨することが...
続きを読む



永代供養料には何が含まれる?
永代供養料にはどういった費用が含まれるのか、また、永代供養料の他に必要となってくる可能性のある費用にはどういったものがあるのでしょうか。
永代供養料に含まれる費用
今後の供養をしてもらうための費用
遺骨の管理、定期的な合同法要、回忌法要(別途料金が必要な場合あり)などといった今後の供養をしてもらうための費用が永代供養料に含まれます。
納骨式のお布施
一般的な納骨法要では、僧侶に対しお布施を渡しますが、永代供養の場合は、納骨法要の際のお布施の費用が永代供養料の中に含まれていることがほとんどです。
ただし、寺院や霊園により異なることがあるので、事前に契約内容の確認が必要です。
刻字費用
共同もしくは個別の墓誌(故人の俗名・戒名、没年月日などを刻む石板)に字を彫刻するための費用です。これも永代供養料に含まれることが多いようですが、追加料金が必要になるケースもあるので確認しましょう。
永代供養料の他に必要になる可能性がある費用
管理費、年会費
永代供養料の中には、管理費や年会費も含まれていることが一般的です。しかし、寺院や霊園によっては個別に支払いが必要なケースもあるため、事前に契約内容を確認しましょう。
墓石代(個別墓の場合)
もしも個別の墓石を希望するのであれば墓石の建立費用が別途必要です。
法要時のお布施
法要時のお布施は永代供養料に含まれていることが一般的です。
しかし、寺院や霊園によっては別途必要な場合もあります。また、僧侶にお経をあげてもらうのなら、その都度お布施を包むことが慣習となっているという側面もあります。
戒名料
多くの寺院では、授戒(仏弟子としての戒名を授けること)しなくても、永代供養を受け付けてくれます。そのため、家族が自ら戒名を望む場合や個別で墓誌を付けてもらう場合には追加で戒名料が必要となります。
入檀料
入檀(檀家になること)をしなくても利用できる永代供養もありますが、そのお寺に入檀しなければならないなどの条件があるのならば、入檀料が別途必要になります。
会場使用料
年忌法要などで斎場使用する場合などは、会場使用料が必要になります。
永代供養料の相場とは?
永代供養料の相場はどの程度でしょうか。納骨スタイル別に紹介します。
合祀型の永代供養料
合祀墓の場合の永代供養料相場は、約5万円~10万円程度と言われています。
個別型の永代供養料
個別墓や夫婦墓の場合
個別墓や夫婦墓を建立する場合の永代供養料の相場は、約50万円~150万円程度と言われてます。墓石を建てる場合などはさらに別途料金が掛かるため、墓地の広さやどのようなお墓を建てるかによって費用が大きく異なってくるでしょう。また、年間の管理料(一般的には数千円)が掛かってくる場合もあります。
納骨堂の場合
納骨堂の場合の永代供養料の相場は、約30万円~100万円程度と言われています。こちらも納骨堂のタイプによって費用が異なります。占有スペースの広さと値段はおおむね比例するため、家族・親族複数人の遺骨を納めるようなゆとりのあるタイプは値段も上がります。こちらも年間の管理料(一般的には数千円)が掛かってくる場合もあります。
樹木葬の場合
個別型(個々の遺骨を納める区画ごとに樹木を植える)の永代供養料の相場は、約20万円~80万円。合祀型(1本の樹木の根元に他の遺骨と混ぜて納める)は、約5万円~20万円。集合型(1本の樹木の根元の各区画に遺骨を1人分ずつ納める)は、約15万円~60万円と言われています。
このようにお墓の仕様が納骨堂なのか墓石なのか、個別埋葬される期間や広さによって価格帯はさまざまです。
そのため事前に複数社から見積もりをもらって比較するのがお勧めです。



永代供養の法要、お布施
永代供養を選んだ場合、年忌法要は行わないのでしょうか。確認しておきましょう。
法要を個別に行うのは自由
永代供養は、法要も含めた供養を寺院や霊園に一任する契約です。したがって、法要は基本的に寺院や霊園側で行われます。しかし、だからといって遺族が法要を営んでいけないということではありません。
個別の法要を希望する場合は、寺院・霊園側に相談してみましょう。その際にはお布施や会場使用料などが必要です。
法要のタイミング
永代供養だからといって回忌法要などのタイミングが変わるわけではありません。個別の法要では四十九日(納骨法要)、初盆、一周忌などに営む場合が多いようです。
法要時のお布施
法要時のお布施は、3万円〜5万円くらいでしょう。宗派による違いはありませんが、地域性はあります。
他にも、個別法要などを追加する場合は、別にお布施代や会場使用料などの追加料金が必要になります。
また永代供養料の中にお布施代が含まれている場合があります。
ほとんどが最初に払う永代供養料の中に含まれていますが、寺院や霊園によって異なるので確認しましょう。
永代供養料を渡す際の表書きについて
永代供養料を寺院・霊園に渡す際には、金封に入れて渡します。のし袋や水引を用意する場合もありますが、水引のかけられた袋である必要はなく、白地の封筒で問題ありません。ただし、郵便番号枠のついたタイプは避けましょう。
表書きは「永代供養料」、フルネームあるいは〇〇家とします。葬儀ではないので薄墨は用いず、濃墨で、筆か筆ペンを使って書きましょう。
永代供養料は寺院・霊園に支払うものであって、香典のように香典返しの送り先が分からないと後から困るということはありませんので、住所の記載は不要です。
また、渡す際には直接手渡しでも構いませんが、袱紗や切手盆に載せるなどすればより丁寧です。
永代供養料の場合は、包みの中に入れるお札は新札でも構いません。
新札を使わない理由は、通夜や葬式のように突然の不幸を待っていたかと思わせないようにするという習わしなので、永代供養料を渡すときは新札でも古札でも問題ないのです。むしろなるべくきれいなお札の方が失礼がないでしょう。



永代供養料は相続税の債務控除の対象外
相続税は、故人の財産から債務と葬儀費用とを差し引いた残額に対して課税されます。つまり、葬儀費用は相続税課税対象外(債務控除の対象)であるということです。
永代供養料は法要や墓地の建立と同様に、この「葬儀費用」にはあてはまりません。
永代供養料は葬儀後の供養と遺骨の管理のために管理者である寺院や霊園に対して支払う料金であり、債務控除の対象とはならないので注意しましょう。
まとめ
子供がいない、身寄りがないなどの事情で墓の承継が難しいという状況は、今日では珍しくありません。また、子供がいても、墓を継がせて苦労をかけたくないと考える親も増えてきています。
このような背景から、永代供養という埋葬方法は決して特別なものではなくなってきています。また反面、いずれ合祀されることや菩提寺の墓に入らないということに違和感を覚える人がいるのも事実です。
故人の希望や遺族の事情により永代供養を選択する場合には、違和感がある人への配慮を忘れず、親族などに対し丁寧に説明をして理解を得ておくようにしましょう。そうすれば悔いやわだかまりが残らずおだやかな気持ちでお参りができると思います。
ご自身や家族にとって先々の不安を減らし、安心して供養ができる選択のひとつとして、永代供養を検討してみるのもよいでしょう。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。