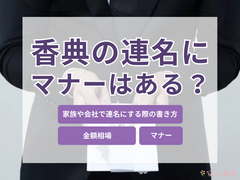宗派ごとの焼香の回数を詳しく解説

日本国内の葬儀では、大半を占めると言われている仏式葬儀。その仏式の葬儀に参列する場合に行うことになるのが焼香です。
葬儀に参列する方の中には、普段不馴れであるがゆえに、前の人の所作を見よう見まねで焼香を行う人も多いのではないでしょうか。
宗派ごとに回数が異なるなど、細かい作法がある焼香ですが、その具体的な作法についてはあまり知られていません。
本記事では、宗派による焼香回数などの作法の違いについて紹介します。合わせて、焼香という行為に込められた意味についても紹介しますので、次に焼香を行う際の参考にしてください。



焼香の意味とは?
焼香とはお香の焚き方の一つです。仏教においてはお香の香り(「香」)は仏にとっての食べ物であると考えられ、「五供」とよばれる基本の供え物の一つとされています。また、お香には不浄を払う働きがあるとも考えられています。
葬儀における焼香は、焼香をする人自身の穢れを落とし、清められた心身で故人を弔うために行われます。
その他にも、「よい香りに満ちているとされる極楽浄土から仏が故人を迎えに来るさまを再現している」「香りが空中にひろがることで仏教の教えや仏の慈悲が広がることを意味している」など、さまざまな意味があるとされています。
焼香の方法
何度も葬儀に参列して焼香も経験している人でも、その細かな方法についてはあやふやということも意外とあるものです。焼香の方法を今一度確認しておきましょう。
焼香を行う順番は故人との関係性順
遺族・親族は、喪主を先頭にして基本的に故人との関係性が深い人から順に焼香を行います。配偶者は例外ですが、それ以外の関係に当たる人については血縁の濃さが基準となります。
ただし、故人のきょうだいの配偶者の場合は、血縁関係にはありませんが、実際の葬儀の場では夫婦はひと組とみなされ、故人のきょうだいの焼香と同じタイミングで行うのが一般的です。
葬儀の場合では、着席の順番が焼香の順番になります。焼香順に細かく配慮したい場合は、事前に葬儀社と打ち合せをしておきましょう。
なお、一般参列者については基本的に順不同で、その順番が問題となることはまずありません。基本的に、着席順に焼香を案内します。
焼香の手順
会場により焼香のスタイルはまちまちです。
座礼焼香(座って行う形式の焼香)や回し焼香(焼香用具一式を順に回して自席で焼香を行う形式の焼香)が行われることもありますが、ここでは主流である立礼焼香(立って行う焼香)を例に焼香の手順を紹介します。
- 係員からの案内、あるいは自分の順番が回ってきたら、席を立ち祭壇手前まで進み出て遺族に一礼します。
- 祭壇の前まで進み、遺影に一礼します。
- 抹香(粉末状のお香)を右手の3本の指(親指・人差し指・中指)でつまみ上げます。
- 抹香をつまんだ右手を目あるいは額の高さまで上げて押しいただきます(※)。
(※)押しいただくとは、物を恭しく目の位置より高く掲げて持つことを指します。「お香自体」に意味があるとしている宗派は、この押しいただく所作を行います。お香の「香り」や「煙」が仏を招くと考える宗派では、この押しいただく所作を行いません。 - 持ち上げた右手を香炉の上まで下ろし、香炉の炭の上辺りに抹香を落としてくべます。
- 合掌します。
- 再び遺族に一礼し、自席に戻ります。



宗派ごとの焼香の回数とマナー

仏教には多数の宗派がありますが、そうした宗派ごとに焼香の作法も少しずつ異なります。とはいえ、葬儀を執り行なう宗派の作法にのっとることが厳密に求められるケースはほとんどありません。
参列した葬儀の宗派に合わせるという考え方もあれば、参列者自身の宗派の作法に合わせるという考え方もあり、どちらも間違いではないでしょう。
また、参列者の人数が多い通夜・葬儀では、宗派によらず「お心を込めて1回焼香で」と案内される場合もあります。
したがって、マナーに反してはいないかと過剰に心配する必要はありませんが、宗派ごとの焼香の作法の違いを、その回数を中心に確認しておきましょう。
宗派ごとの正式な数珠も紹介しますが、どの宗派でも利用できる「略式念珠」を用いることも特に問題はありません。
天台宗
天台宗では焼香の回数は特に定められていませんが、1回もしくは3回行う場合が多いです。また、線香を立てるときは手前側に1本、奥に2本を逆三角形の形になるように3本立てます。数珠は平玉(扁平な形の玉)が使われ、親玉から、平玉の弟子玉20個と丸玉の弟子玉10個が下がっています。
真言宗
焼香の回数は通常3回とされます。1回目のみ押しいただき、残りの2回はそのまま抹香を炭に落として焼香します。線香の場合は、手前側に1本、奥に2本を逆三角形の形になるように立てます。数珠は、主玉108個、親玉2個、四天王玉4個に菊房(梵天房)を付けたものを用います。
浄土宗
焼香の回数に決まりはなく、線香の場合は1~3本の線香を立てます。数珠は、二連の輪違いのもの(一つが27玉、もう一つが男性なら20玉・女性なら40玉、金属製の二連の輪に房が付いている)を用います。
浄土真宗(本願寺派)
焼香の回数は1回。押しいただきません。線香の場合は1本を二つに折って短くしたものに火をつけて横に寝かせて置きます。
浄土真宗の数珠は一般的に、一連の長い数珠を二重にし、片方の房が「蓮如結び」(念仏を唱えるたびに繰って数えることができないようにした独特の結び方)で結ばれているものとされています。男性用としては略式念珠の男性用が用いられることもあります。
浄土真宗(大谷派)
焼香の回数は2回。押しいただきません。線香の場合は1本の線香を二つか三つに折って短くしたものに火をつけて横に寝かせて置きます。
本願寺派と同様に、一連の長い数珠を二重にし、片方の房が「蓮如結び」で結ばれているものが一般的です。男性用としては略式念珠の男性用が用いられることもあります。
臨済宗
焼香の回数は特にこだわらないとされますが、通常は1回です。線香の場合は1本立てます。数珠は、一連の数珠に1本あるいは2本の房が付いたものを二重にして用います。
曹洞宗
焼香の回数は通常2回。1回目は押しいただき、2回目は押しいただきません。線香の場合は1本立てます。
数珠は、同じ禅宗の宗派である臨済宗同様に一連の数珠を二重にして用いますが、金属の輪が通してあるという特徴があります。
日蓮宗
焼香の回数は、通常は3回です。(導師は3回、参列者は1回という場合もあります。)
線香の場合も特に決まりはありませんが、3本が一般的です。
数珠は、5本の房(片方の親玉に2本、もう片方に3本)のついたものを用います。
まとめ
葬儀の参列者としての焼香では、通常「抹香を香炉にくべる」ことができてさえいれば問題ありません。
また、宗派ごとに定められた焼香回数によらず、参列者多数の場合には焼香は1回だけにとどめ手短に済ませることが一般的です。
これはつまり、故人(宗派によっては仏)に供える際の気持ちのありようが問題であり、回数や細かな作法は二の次であるということを意味していると言えます。
宗派ごとの違いをおおまかに把握しておきつつも、必要以上に神経質にならず、故人を見送るその心を何より大切にして焼香を行いましょう。
関連記事

宗教宗派によって異なる葬儀の特徴を解説
お葬式は、宗教や宗派によって内容や作法などが異なります。例えば宗派によって焼香の回数が違います。また特定の宗教や宗派を対象とした葬儀場や葬儀社も存在します。 葬儀を執り行う立場としても、宗教や...
続きを読む



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。