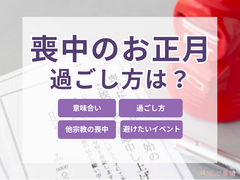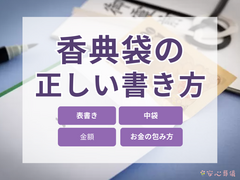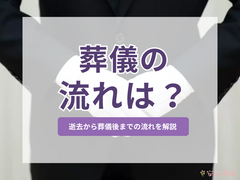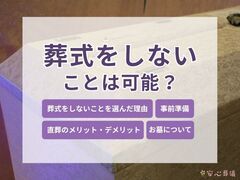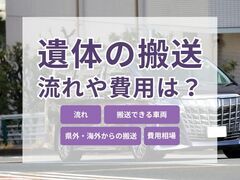出棺について詳しく解説

出棺は葬儀・告別式の最後を締めくくる重要なセレモニーです。火葬場に同行しない遺族、一般の参列者にとっては、故人との最期のお別れの場でもあります。
この記事では、出棺の持つ意味やさまざまな儀式、さらに遺族や参列者のマナーについて詳しく解説します。儀式としての出棺をしっかりと理解し、心のこもったセレモニーとするために、活用してください。



出棺とは?
「出棺」は、一連の葬儀・告別式の流れで最後に行います。その名の通り、故人の棺を火葬場へと送り出すことを指しています。
葬儀・告別式が終了し、故人の棺を祭壇から移動させて遺族や参列者とのお別れの時間を過ごした後、棺は遺族や故人と特に関係が深かった参列者に見送られながら霊柩車に乗棺し、火葬場へ向かいます。
近しい遺族は棺と一緒に火葬場へ向かいますが、一般の参列者と火葬場に同行しない親族にとっては、故人との最期のお別れとなります。火葬場へ到着すると、同行した遺族らは棺の窓ごしに故人との最後の対面をし、そのあと遺体は荼毘に付されます。
地域によっては、火葬場で故人の顔を見てお別れができないところもあり、その場合は火葬場に同行する遺族にとっても、出棺が最期のお別れとなることもあります。
出棺の儀式とは?
棺を火葬場へと送り出す前、一般的にはいくつかの儀式を執り行って、故人の顔を見ながら、最期の別れを惜しみます。
さまざまな様式がありますが「別れ花」を行った後、「釘打ちの儀」を行うことが多いようです。ただし、釘打ちの儀については、近年では行わない地域もあります。
別れ花
「別れ花」は、「お別れの儀」や「花入れの儀」などと呼ばれることもあり、棺の蓋を開けて遺族や近親者が棺の中の故人に話しかけながら、遺体の周囲に生花を手向ける儀式のことです。別れ花が済むと棺に蓋がされるため、故人に触れて直に対面できるのは、この別れ花が最期の時間になります。
別れ花の手順
別れ花の一般的な手順は下記の通りです。
- 葬儀または告別式が終わると、遺族や親族、参列者は一旦会場を退出し、その間に葬儀社のスタッフが別れ花の準備を行います。具体的には、祭壇の生花や供花を摘み取って入れやすいように分け、お盆に乗せます。また、棺を祭壇から会場中央などに移動させます。
- 会場内の準備が整うと、喪主を先頭に遺族、親族の順に会場に入り、用意された生花を一輪または少量ずつ受け取って棺の近くへ進みます。
- 故人と近しい人から順に棺の中に花を入れていきます。通常は喪主が最初で、喪主の配偶者、親、きょうだい、子供、孫の順で花を手向けます。親族の順番が終わった後、参列者の中で希望する人には花入れを案内する場合もあります。
- 遺族・親族や希望者が順に花を手向け、なお花が余っている場合は、順番を問わずに花を束ねて取り、棺に入れて遺体の周りを生花でいっぱいにします。
- 用意した全ての花を手向け終わったら、遺族を中心に故人の傍に集まり、最期のお別れをします。お別れが済むと、その場にいる全員で合掌や黙祷を捧げて故人を見送り、棺の蓋を閉じます(釘打ちの儀がある場合は、続けて行います)。
- 別れ花を終えると、会場内で喪主や代表者が出棺挨拶を行う場合もあります。
別れ花で使う花の種類
棺に入れる花は、通常は祭壇に飾る生花やお供えの花を切り花にするなどして、葬儀社のスタッフが用意してくれます。もし、遺族で花を用意したい場合や希望する花の種類がある場合には、あらかじめ喪主や葬儀社に確認を取っておくほうが安心です。
ただし、あまり大きな花を用意したり、派手な包装や燃えにくい包材を使用したりすることは控えてください。
一般的には、白を基調にした落ち着いた色合いの花が好まれます。よく利用されるのは、菊、百合、カラー、カーネーションなどです。参考までにそれぞれの花言葉を紹介します。
白菊:誠実、真実
百合:威厳、純潔、無垢、純粋
カラー(白):素敵な美しさ、清浄、壮大な美
カーネーション(白):亡き母を偲ぶ、純潔、純粋な愛、尊敬
花以外のものは入れられるか
なお、生花だけでなく故人の愛用品などを棺に入れることもあります。ただし入れられるのは基本的に燃えやすいものに限られます。
例えば、好きだったお菓子や愛用の衣類、手紙といった品物です。紙製であっても、お札は入れることはできません。分厚い書籍も火葬に時間がかかる上に灰も多く残ったりするため、避けるようにします。
また、写真は基本的に棺に入れても問題ありませんが、存命の人物が写った写真を火葬することを不快に思う人がいる可能性もあるため、配慮が必要です。
金属製、ガラス製、ゴム製などの不燃物は基本的に棺に入れることはできません。愛用していた眼鏡や腕時計など、小型の貴金属は骨つぼに収めることが可能な場合があるので、希望する場合は葬儀社に確認してください。入れる順番は、生花と同様に故人と近しい順です。
副葬品にできるもの・できないものについては以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事

副葬品とは?葬儀の際に棺に入れて良いものといけないものを紹介します
故人と共に柩の中に納める副葬品。送り出す側は副葬品に想いを託して、故人が生前に愛用していたものや、送る側の想いを込めたものを納めます。しかし、どんなものでも副葬品として柩の中に入れてよいわけでは...
続きを読む
釘打ちの儀
「釘打ちの儀」の釘打ちとは、棺に蓋をして、釘で固定することです。釘打ちをすると蓋が固定されるので、別れ花を終え、故人とのお別れの最後に行う儀式となります。
釘打ちの儀式には、宗教的な理由と物理的な理由があると言われています。
宗教的な理由
宗教的には、神道由来の「死=穢れ(けがれ)」という考え方や、死霊に対する恐怖心から、死者を封じるために釘を打つと考えられています。その他に、遺族が故人の蘇生を断念して気持ちに区切りをつける、という意味合いを持つとする説もあります。
また、広く土葬が行われていた時代は、遺体の保存状態が悪く、遺体を介して病気に感染するおそれもありました。このため、棺に蓋をして釘を打つことが広く行われるようになったようです。
物理的な理由
物理的な理由としては、遺体を無事に搬送するために釘が打たれるようになりました。
かつて、棺には無垢の板材が使用されていたため、湿度の変化などによって蓋が反ってしまうことがありました。そこで、搬送中に蓋が反って外れないように、釘を打って固定したと言われています。
また、土葬が行われていた時代の棺は、遺体を座った状態で納める座棺と呼ばれるものが用いられていました。
この座棺は、二人の人間が棒を肩に担いで運んでいたために揺れやすく、蓋を縄で縛っただけでは外れてしまうことがあったようです。
釘打ちの儀の流れ
現在では、死に対する考え方の変化、火葬の一般化、棺の形態や造りの改良、搬送方法の進化に伴って、釘打ちを行うことは少なくなりました。しかし、現在でも地域によっては、釘打ちが一般的に行われています。
現在行われている「釘打ちの儀」では、棺の蓋をした後、棺の四方の角に釘打ちが行われます。
通常は、釘の半分をまず葬儀社のスタッフが打ちこみ、次に血縁者が血縁の濃い順番に小石で軽く2回ずつたたいて釘を打ちこみます。その後、再び葬儀社のスタッフが最後まで釘を打ち込みます。
また、葬儀社のスタッフが3本の釘を打った後、最後の1本を喪主や遺族が少しずつ打ち込むという方式もあります。地域によっては、釘打ちは葬儀社のスタッフが行い、遺族は釘打ちをしないというところもあるようです。
打ちこむ際に小石を使うのは、三途の川の石に例えているという考えや、石には呪力が宿ると信じられたことから棺に死者の霊を封じこめるという考え方もあるようです。現在では、石に代わって金槌を使用することもあります。
また、釘打ちを行わず、皆で手を添えながら棺の蓋を閉める場合もあります。
なお、浄土真宗では「死を穢れとして忌避し、封じる」という考え方が教えに反するものであることから、釘打ちの儀式をすることはありません。



出棺の儀式が終わった後の流れ
棺を霊柩車へ運ぶ
「別れ花」や「釘打ちの儀」といった出棺の一連の儀式が終わった後、遺体が入った棺は霊柩車へと運ばれます。
棺を運ぶのは、遺族の男性を中心とした男性六~八人ですが、遺族だけで棺を運ぶことが難しい場合には、葬儀社のスタッフが喪家に近しい人に手伝いをお願いします。
霊柩車へと移動する際は、位牌を持った喪主が先頭です。故人に近しい遺族が遺影を持ってその後に続きますが、棺を先導する場合と、棺の後ろに続く場合があります。
宗教者が喪主や棺の前に立ち、棺や遺族を先導するケースもあります。
棺を霊柩車へと乗せる際に、遺体の頭から入れるか、足側から入れるかということについては、どちらが正しいという決まりはありません。
地域ごとの風習や、火葬場の火葬炉に入れる際の向きなどを考慮して決められますので、向きについては葬儀社のスタッフの指示に従うとよいでしょう。
棺が霊柩車に収められ、火葬場へと向かう準備が整ったら、遺族は参列者に向かって横一列に並び、喪主が遺族を代表して出棺の挨拶を述べます。
出棺の際の喪主の挨拶
出棺の際の喪主の挨拶は、忙しい中で葬儀に参列してくれたことや故人が生前にお世話になったことへの感謝の気持ち、さらに遺族に対する今後の指導、支援へのお願いなどで構成します。
故人の最期の様子や、生前に話していたことなどがあれば、挨拶に盛り込んでもよいでしょう。
出棺の際、参列者は屋外で立ったままお見送りしています。このため、出棺の挨拶は簡潔にまとめるようにしてください。時間にして1〜2分程度、あらかじめ原稿にまとめるのであれば、300〜400文字くらいが目安です。
なお、出棺の挨拶には定型の文例があります。葬儀社でも用意してくれるので、不安な場合は葬儀社に尋ねてみることをお勧めします。
出棺の際、遺族としては哀しみの感情が表出したり、最期のお別れに動揺したりすることは自然なことです。そうした状況に備えて、自身の言葉で挨拶をする場合も、あらかじめ参列者に伝えたいことを紙に書き起こし携帯しておくと安心です。
出棺の挨拶文例
喪主として一言ご挨拶申し上げます。本日は大変お忙しいところ父○○の葬儀にご参列いただき、心よりお礼申し上げます。
生前中はひと方ならぬご厚誼にあずかり、最後のお見送りまでいただき、父もさぞかし皆様のご厚情に感謝していることと存じます。
父が賜りましたご厚情に心から御礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬご指導ご交誼をたまわりますようお願いいたしまして、ご挨拶にかえさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
喪主の挨拶で話す内容やマナーついては以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事

喪主の挨拶では何を話す?マナーや例文を紹介
喪主は葬儀の主催者であり、遺族の代表者です。ほとんどの場合、故人との関係性が深い人が務めます。そのような立場から、葬儀のさまざまな場面で故人に代わって、あるいは遺族を代表して挨拶することが求めら...
続きを読む
出棺時の参列者
葬儀・告別式に参列した場合、故人と親しい関係にあった人は、できるだけ最後までお見送りするようにしてください。
出棺は多くの場合、建物の外で行われます。冬場はコートを着用して待機しても問題ありませんが、出棺の儀式の際はコートを脱いでお見送りするのがマナーです。
葬儀会場から棺が出される際は、棺の方を向いて立ちます。喪主の出棺の挨拶が済み、遺族が礼をした際には、参列者も一礼しましょう。
棺が霊柩車に乗せられ、火葬場へと出発する際には、霊柩車に向かって丁寧に一礼して、黙礼または合掌で見送ります。
霊柩車が見えなくなっても、いきなり大きな声で話し始めたり、笑い声を上げたりするのは、大変失礼なことです。くれぐれも謹むようにしてください。
まとめ
出棺は葬儀・告別式の最後に行われます。姿かたちのある故人とお別れをし、火葬場へと向かうための準備をするための儀式です。
故人と親しい人が遺体に話しかけながら棺の中に切り花や故人の愛用品などを入れる「別れ花」、棺に蓋をして四隅に釘を打つ「釘打ちの儀」といった出棺の儀式が行われ、遺族は故人との最期の別れを惜しみます。
出棺の儀式が終わると、棺は遺族・親族の男性の手で霊柩車に乗せられ、火葬場へと向かう準備が整います。喪主が遺族を代表して挨拶を行い、棺は参列者に見送られながら火葬場へと向かいます。
遺族としての立場、参列者としての立場、どちらであっても出棺においてマナー違反がないように、しっかりとした知識を蓄えておいてください。



葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。