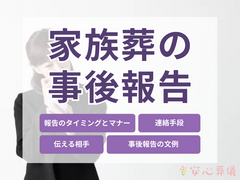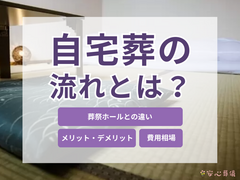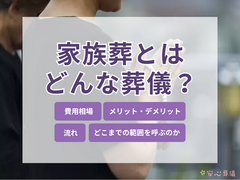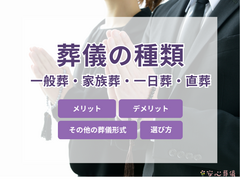社葬とは?社葬を行う場合と開催の流れを紹介

社葬は、社内的にはもちろんのこと、対外的にも重要な意味を持つ会社行事です。
一般的な葬儀については何となくイメージができる方も、会葬の機会が非常に少ない社葬については、詳しく知らない方がほとんどではないのでしょうか。
今回は社葬の意味や流れなどについて解説していきます。



社葬とは
まずは社葬の意味など基本的な部分を紹介します。
社葬とは
社葬とは会社が葬儀の運営主体となり、かつ費用の負担も行う葬儀のことを言います。
社葬が行われる意義としては下記が挙げられます。
- 企業として、故人が生前にお世話になったことに対する感謝の意を表明する
- 故人の会社への貢献に感謝し、追悼する
- 故人亡き後の会社の体制を伝え、挨拶をする
- 会社の従業員の意思統一、結束を図る
社葬にはいくつかの形式があり、下記のようなケースもあります。
- 通夜は身内だけで行い、葬儀・告別式のみ社葬として行う
- 通夜、葬儀・告別式、火葬までを社葬として一般葬と同じように行う
- いったん密葬で火葬まで済ませ、後日改めて本葬として社葬を行う
大きな会社になると社葬もそれなりの規模となり、各所への連絡などの準備をする時間が必要となるため、火葬までは家族葬または一般葬として行い、後日改めて社葬を行うというケースが多数です。
なお、社葬は必ずしも大規模な葬儀になるわけではありません。
家族経営の会社などは、参列者は数十名で、実質的に家族葬や一般葬と同じような規模で行われる社葬もあります。
また、社葬を行う際は、必ず遺族の同意が必要になるので、事前に確認します。
社葬の一種である合同葬とは
合同葬とは、葬儀の運営、葬儀費用の負担が複数の会社や団体などによって行われる葬儀のことです。
その場合には「〇〇会社 ▲▲会社 合同葬」というように銘打って実施されます。会社同士で行われる以外にも「〇〇家 〇〇会社 合同葬」というように喪家と会社が合同で行うケースもあります。
合同葬では、特別な事情がない限り遺族が喪主を務め、施主は会社が行うことが多くなっています。
葬儀全体の内容は葬儀実行委員長が決めます。葬儀委員長は社葬の最高責任者で、喪主よりも先に焼香をあげたり、参列者に挨拶を述べる立場になります。
社葬や合同葬の場合の葬儀実行委員長は、会社の代表者などが努めることが多いです。
合同葬などの社葬を行うのは、故人を追悼することに加え、社外の人に対して生前故人がお世話になったことへの謝意を伝えることや、故人がその会社に残した功績をたたえるために行います。
故人が創業者や会長などである場合は、その想いを引き継いでいくことをアピールする場となることもあります。
また後継者が関係者に対して、事業を継承し新たな体制を知らせる場でもあります。今後の会社運営がしっかりできることを示すためにも、社葬を滞りなく行うことが重要です。
関連記事

合同葬とは?合同葬のメリット・デメリットについても解説
亡くなった方を見送るための「合同葬」という形式での葬儀が営まれるケースがあります。 その名称からある程度の想像はついても、合同葬が具体的にどういったものかについてはあまり知らないという人も多い...
続きを読む
社葬を行う場合とは

社葬はどのような場合に行うものなのでしょうか。
一般的には会社に大きな貢献をした人(現役の役員など)が亡くなった場合に社葬が行われます。
しかし「多大なる貢献をした人」は、会社ごとによって考え方が異なります。
また「こういう人が亡くなった場合は社葬を行うべき」という通念もありません。
そのため、どのような場合に社葬を行うかは会社ごとの判断に委ねられ、原則的に社葬規定などによって個々に定められています。
詳細な定めは会社によって異なりますが、社葬を行う場合の主なケースを紹介します。
経営の根幹に関わる人物が亡くなったとき
会社のオーナー、創業者、会長、社長、専務、常務などの要職者が社葬の対象となります。
会長以下は現職であることを条件とされる場合がほとんどです。
企業の発展に貢献した現役社員が亡くなったとき
会社の業績を大きく伸ばすような発明やヒット商品を作ったり、商品開発において特許取得に貢献したりした社員が亡くなった場合など、類まれな貢献をした現役社員が対象となります。
業務中の事故などの殉職者
交通事故、自然災害、機械的な事故、殺人事件に巻き込まれたりした場合など、原因はさまざまですが、業務中に従業員が亡くなった場合、いわゆる殉職者が社葬の対象となることもあります。
殉職者が対象となるのは、遺族に対して会社として事故や事件が防げなかったことへの謝罪の意を示すこと、遺族への社会保障を行うことなどの意味があります。



社葬の喪主と施主について
喪主にはいろいろな意味がありますが、主たる意味は「祭祀を執り行う人」、つまり遺族の代表者のことです。
一方で施主の主たる意味は「お布施をする人」で、葬儀の費用負担および運営の責任者のことです。
それでは、この喪主と施主について、社葬ではどのような意味を持つのでしょうか。
社葬の施主とは
社葬では、会社が葬儀の費用を負担し、運営責任を持ちます。そのため、社葬では会社が施主という役割を担うことになります。
一般の葬儀では「施主」という名称で挨拶をしたり、供物を贈ることがありますが、社葬においては「施主」という名称が表立って出てくることはありません。
施主の役割をする葬儀の代表責任者として「葬儀委員長」を立てることが一般的です。
葬儀委員長は会長が亡くなった場合には社長、社長が亡くなった場合には次期社長が対象になるなど、会社の代表者が務め、現役の代表者が亡くなった場合には後継する役員が務めることが一般的です。
それぞれの会社の規定によって定められている場合もあります。
ただし、家族で経営している会社で、役員が全員親族のときには、特に葬儀委員長を決めずに喪主だけを立てる場合や外部の社会的地位のある人にある人に依頼する場合があります。
社葬においては、この葬儀委員長のもとであらゆる運営が進められていきます。
社葬の喪主とは
社葬を行う場合でも、喪主は遺族の代表者が務めます。
社葬の場合でも、一般葬と同じように故人の配偶者や長男などが喪主を務めることが多いです。
そのため、社葬を行う場合には遺族の同意が必要であり、社葬は遺族の協力があって成り立つものです。
ただし、家族経営の会社の場合など、特に葬儀委員長を決めずに喪主だけを立てる場合もあります。
社葬の会場選びのポイント

社葬を行う会場としては、葬儀社所有の葬祭ホール、公営斎場、ホテル、寺院などの他、会社が所有している体育館や大会議場などの施設を利用する場合があります。
社葬の会場選びとしては、まず予想される参列者の人数に合わせた規模の会場を選択することが重要です。
社葬では、数百人から数千人と多くの参列者が会場に来る場合もあります。
参列者の人数が会場の容量を超えてしまうと、参列者の導線や待機場所、返礼品や料理、駐車場などで混乱をきたす可能性があるので、参列者数に合わせた会場選びが重要です。
その他、社葬を行う会場を選ぶ際には下記もポイントとなります。
- 会場の使用料金
会場が大きくなればなるほど、基本的には会場の利用料金も高くなります。 - 交通の利便性を確認する
駅からの近さ、バス停との距離、幹線道路からの近さなど参列者にとって交通の便がよいかも大事な視点です。
多くの関係者が訪れる社葬では、なるべく公共交通機関が利用できる会場を選ぶようにしましょう。 - 駐車場の大きさ
車を利用する参列者が多いと予想される場合には、充分な台数を収容できる駐車場の確保が必要です。 - ホテルを使いたい場合
ホテルを使いたい場合は、遺体や遺骨の持ち込みが可能かどうかを事前に確認しておきましょう。
ホテルによっては、遺体や遺骨の持ち込みを禁止しているところがあり、特に遺体は持ち込みできないホテルがほとんどなので注意しましょう。



社葬の主な流れ
社葬にはさまざまな形式がありますが、ここでは逝去後にまず家族葬を済ませ、その後、日を改めて社葬を実施する場合の流れを紹介します。
社葬前日までの流れ
逝去から社葬の打ち合わせなど、流れを見ていきましょう。
逝去
逝去後、なるべく早い段階で会社関係者は遺族に挨拶、社葬を行いたい旨を説明し、遺族の同意を得ます。
臨時取締役会
臨時取締役会を開催し、社葬を行う旨を決議し、それを議事録に残します。
家族葬、火葬
遺族および、親族のみで密葬として家族葬を執り行い、火葬を済ませます。
このときに遺族から要望があればそれに従い、サポートしましょう。
葬儀社と社葬の打ち合わせ
社葬の内容(宗教宗派、形式、日程、会場、葬儀委員長、祭壇、返礼品など)について葬儀社と相談しながら決めていきます。
会社の名前で行う葬儀です。ミスがあっては会社の信用まで失いかねません。
そうならないためにも、社葬を担当した実績があるなど、経験豊富で信頼の高い葬儀社を選びましょう。
社内で係の振り分け
葬儀委員、運営本部、広報、受付、会計、案内、記録、来賓対応など社内で役割を決めます。
関係先へ案内を送付
取引先を中心に社葬の案内状を送付します。この際に香典や供花などを受け取るかを決めてお知らせします。
香典の会計処理は複雑なため、辞退する傾向が多いです。供花は現金ではないので、会計上の問題は生じません。
供花取り纏め
社内、関連会社の供花の取り纏め、注文を行います。
社葬当日の流れ
次に社葬当日の流れを見ていきます。
関係者会場に集合
関係者が集合後、全体打ち合わせ、係ごとの打ち合わせを行い、式場や控室および導線など会場内外を確認します。
受付開始
記帳方法、香典の受け取り方、返礼品の渡し方などを確認し、受付を開始します。
社葬
本葬として社葬が始まります。式次第は下記の通りです。
- 遺骨の出迎え遺族が遺骨とともに会場入りするのを出迎え、遺骨を式場に安置します
- 受付
参列者を迎え、芳名帳を記入してもらい、香典を預かったり返礼品を渡したりします。 - 導師式衆入場
読経を行う僧侶などが入場します。 - 開式
司会者や葬儀委員長などによって、開会を宣言し葬儀を始めていきます。 - 読経
故人をあの世へ導き、安らかに眠れるように祈るため、僧侶によってお経が読み上げられます。 - 弔辞
参列された方から故人へ最後の挨拶をしてもらいます。
葬儀委員長や取引先のご贔屓さまなど3〜4人で5分程度の挨拶をお願いします。 - 弔電
参列できなかった方からの電報を紹介します。数が多い場合には3通ほどに絞って紹介します。 - 葬儀委員長挨拶
社葬の施主である葬儀委員長から挨拶をします。故人との思い出や人柄、感謝などを述べるようにします。 - 喪主挨拶
遺族の代表として喪主も挨拶をします。参列してくれた方々へ感謝を述べましょう。 - 読経
ここでもう一度読経がある場合があります。 - 指名焼香(喪主、葬儀委員長など主要人物)
喪主や葬儀委員長など葬儀で重要な役割を担う人物によって献花や焼香を行います。 - 遺族親族焼香
次に喪主以外の遺族や親族によって献花や焼香を行います。 - その他参列者焼香
参列者は、遺族や親族の焼香が終わった後に行います。
ただし参列者が多い場合は三人程度で一緒に焼香を行っていくこともあります。 - 導師退場
ここで儀式が終わるので僧侶には控室などに戻ってもらいます。 - 閉式
これにて社葬が終了したことを葬儀委員長などから伝えます。 - 遺骨退場、見送り
遺骨が遺族とともに退出するのを見送ります
以上が流れの例です。
上記の例では仏式を想定していますが、神道やキリスト教など他の宗教で行われることもありますし、無宗教の場合もあります。
また日を改めて行うのではなく、逝去後に家族葬を行わず一般葬と同じように通夜、葬儀式告別式を社葬として行うケースもあります。
社葬の費用と税務上の取り扱い

社葬を行う場合には、葬儀費用や税務上のルールについても把握しておく必要があります。
費用の負担割合
社葬だとしても、全ての場合において葬儀に関する費用の全額を会社が負担するとは限りません。
一般的には会社ごとに、役職や葬儀の行い方などの状況に応じて会社としての費用負担割合が定められています。
損金算入
費用を損金として計上ができるということは、税務上で会社の経費として認められるということです。会社の経費として認められ、その分利益が減少すれば納税額も減少することになります。
まず、社葬費用を損金として計上するためには、社葬について「取締役会の議事録」、計上する全ての支出についての領収書が必要となります。
また、社葬費用には損金計上できる項目と、できない項目があります。
損金算入できる項目
国税庁の法人税基本通達により、一般常識としての観点から社葬を行うことが適切であると判断されるときは、社葬で支出した費用については、法人税の申告を行う際、損金として計上できるとされています。
社葬を行うことが、社会通念上で相当であると認められるときは、社葬のために通常要すると認められる費用について、損金計上できることになっています。
損金計上できる主な項目は次の通りです。
- 社葬に必要な用品およびサービスに対する費用(祭壇、棺、遺影、宗教用具、司会進行のための人件費、受付用具、供花、会場利用料、駐車場代など)
- 社葬(本葬)を前提とした家族葬や一般葬(密葬)に掛かる費用
- 火葬場利用料
- お布施など司祭者への支払
- 遺体搬送車両、霊柩車、マイクロバスやタクシーなどの車両費用
- 納骨費用(石材店への支払、納骨法要の御布施など)
- お手伝いや運転手などへの心付け(寸志)※支払いを証明できる記録が必要
- 社葬の案内状や死亡広告に関する費用(訃報通知)
- 会葬礼状および会葬御礼品の代金
- 通夜振舞い、精進落とし、係員の食事など飲食に掛かる費用
- 葬儀式告別式の流れに続いて初七日法要を行う場合の費用
- 写真やビデオの撮影に掛かった費用
- 葬儀社警備の人件費
- 手伝った社員の食事代や慰労会費用 など
損金算入できない項目
逆に損金計上できない主な項目は次の通りです。
- 戒名料
- 香典返しの代金
- 墓地を借りるための費用(永代使用料、管理料など)
- 墓石、仏壇仏具、本位牌(葬儀で使用する白木の位牌ではなく、その後用意する黒塗りの位牌)などの購入費用
- 四十九日や一周忌など社葬後に行われる法要に関する費用
関連記事

社葬にかかる費用は?内訳や負担割合についても解説
社葬という言葉を聞いて、企業の関わる葬儀であるということは想像できても、実際の運営における細かな点まではよくわからないという方は少なくないのではないでしょうか。 社葬を執り行なう立場となればな...
続きを読む



最後に
今回は社葬の意味や流れなどについて解説しました。
社葬は、故人や遺族のためだけでなく、社内外に対して今後の会社としての方向性を示す意味を持つ行事です。
また節税の観点からも、会社として社葬の費用負担について明確にしておく必要があります。
もしものときに慌てることがないよう、会社のリスク管理の一つとして社葬に関する規定や制度を整備しておくことが大切です。
社葬について検討する際には、今回の内容を参考にしてみてください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。