死亡届はいつまでに?提出先と必要な書類について分かりやすく解説

近親者が亡くなると、遺族は葬儀の準備に加えて、さまざまな法的な手続きも行わなければなりません。
死亡届の提出は、最も早く対処する必要がある手続きの一つで、万一提出が遅れると、罰則が適用されるなどの問題が発生します。
この記事では、逝去直後の慌ただしい最中でも間違いがなく手続きが進められるように、死亡届の提出先や提出場所、届出人の条件、提出後の流れはもちろん、提出しなかった場合に起こる弊害についても解説します。



死亡届について
人が亡くなった場合は必ず「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届とは
「死亡届」は、人が亡くなったことを法的に証明するための書類です。死亡届は戸籍法の第86条・第87条によって届出の期間や書類、届出人などが定められています。死亡届は役所や保険会社などに対して行う死亡後のさまざまな手続きの際に必要です。
死亡届の用紙は病院に用意されており、死亡確認した医師や担当者が準備をしてくれます。市町村役場でも入手できますが、家族が自分で用意することはほとんどありません。
死亡届の用紙は、左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。
「死亡届」の部分は、届出人が必要事項を記入して、署名・押印します。
一方、「死亡診断書」は病院で亡くなった場合、臨終に立ち会った医師に作成してもらい、自宅で持病が原因で亡くなった場合は、かかりつけ医に連絡して作成してもらいます。
ただし、事故死や変死、また自宅で亡くなった場合でも持病が原因でないといった場合は、監察医などに検死を受けて「死体検案書」を作成してもらう必要があります。
こうした場合は、遺体に手を触れずに、すぐに所轄の警察署に連絡してください。
なお、死亡診断書の作成は、医療機関の自由診療にあたるため、費用が掛かります。医療機関によって料金に差はありますが、5000円程度が相場のようです。
死体検案書の作成は、監察医が死因の特定など行う必要があり、検案代や搬送料、遺体の保管料などが掛かるため、高くなる傾向があります。
死後のさまざまな手続きの際に必要になる死亡診断書ですが、いったん役所に提出すると返却されることはありません。
複数の保険会社に保険金を請求する場合など、それぞれの保険会社ごとに必要となるので、必ず複数のコピーを取っておきましょう。
関連記事

死亡診断書の発行方法は?費用は掛かる?その内容を詳しく解説
「死亡診断書」とは、読んで字のごとく、死亡を診断する書類であり、人が亡くなった事実を証明する際に法律上で必ず必要となる書類です。 死亡診断書が発行されて初めて法的に死亡が認められることになるた...
続きを読む
死亡届の提出先について

死亡届、死亡診断書の記入が済んだら、役所に書類を提出します。届出は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれの市町村役場でも可能です。
注意が必要なのは、故人の住民票が登録されている場所では提出ができないので注意しましょう(死亡地であれば故人の住居地でも提出ができます)。
ただし、届出地と故人の本籍地、届出人の住民登録地があまりに離れていると、手続きに時間がかかってしまう場合があります。よほど特別な理由がない限り、故人の本籍地か届出人の住民登録地で届け出をすることをお勧めします。
届出窓口は、婚姻届や出生届などと同じく365日24時間対応していますが、夜間や休日に提出した場合には、その場では受付けのみ、火葬許可証の交付は後日となります。また、もし書類に不備があれば後ほど連絡が来て、内容によってはあらためて窓口に行く必要があります。
役所の支所や出張所でもできることが多いですが、一部地域では対応していないこともあるので、もし支所などで出そうと考えている場合は、事前に確認してから提出するようにしましょう。
届出に必要な書類
死亡届を提出する際に必要な添付書類は下記の通りです。
死亡診断書(死体検案書)の原本
戸籍法によって、死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付することが定められています。
死亡診断書は生前から故人を診ていた病院の主治医、かかりつけの医師などが、死亡の事実を確認して証明する書類で、死体検案書は監察医などが死因、死期などを医学的に確認したことを証明する書類です。
死亡診断書(死体検案書)は、死亡届の用紙と一体になっています。左側が死亡届で空白になっているので右の部分に必要事項を記入します。
死亡診断書は一度提出してしまうと返却してもらえないので、必ずコピーを取っておきましょう。死後の生命保険や遺族年金などの手続きで書類が必要な場合があります。
コピーを忘れた場合は、病院で死亡診断書を再発行する必要がでてくるため、手数料が掛かります。
なお、死因が大規模災害などで、死亡診断書、死体検案書が作成、提出できない場合には、死亡届に診断書、検案書を提出できない理由を記載するとともに、「死亡の事実を証すべき書面」を提出することが定められています。
「死亡の事実を証すべき書面」として、かつては死亡の事実を目撃した者の大量の陳述書が求められました。
しかし、遺族の大きな負担となるため、先の東日本大震災では法務省が定型の書式を用意し、災害の状況を把握している地元の市町村に死亡の判断をまかせるなど、負担軽減措置が取られています。
印鑑
届出人の印鑑です。認印でも問題はありません。シャチハタは不可。届出人の自筆署名があれば、押印がなくても死亡届は受理されますが、特別な理由がなければ押印しましょう。
窓口で記載内容に誤りが見つかった場合など、修正する時には届出人の認め印を訂正印として使用します。
死亡届を提出する際には、「埋火葬許可申請(火葬許可証)」も行うようにしましょう。たいていの場合は、死亡診断書と死亡届を自治体に提出すると「火葬許可証」が交付されます。
一部、死亡届とは別に埋火葬許可証の申請が必要な自治体もありますが、窓口で記入できる簡単なものです。
届出はいつまで行えばいい?
死亡届の提出期限は、国内の場合は死亡を知った日を含めて7日以内、国外の場合は3カ月以内です。仮に、6月1日に国内で死亡の事実を知った場合、提出期限は6月7日です。
もし、正当な理由がなく提出期限を過ぎた場合は、戸籍法により5万円以下の罰金が課せられます。
届出できる人
死亡届の届出人になれるのは、親族、親族以外の同居人、故人の住居の家主や地主、後見人です。
一方、死亡届の届出人欄には「公設所の長」というチェック欄があります。上記に該当する人がいない場合に、病院長などが届出人となる場合にはこの欄にチェックを入れて提出します。
また、死亡届は届出人が記載、押印しなければなりませんが、実際に役所に提出するのは代理人でも問題はありません。近年では、届出人が作成した死亡届を、葬儀を依頼された葬儀社が代行提出するケースが多くなっています。
修正があったときのためにあらかじめ捨印を押しておくか、葬儀社が認め印を一時的に預かる場合もあります。預ける場合は実印や金融機関届出印など、大切な印鑑は避けましょう。
一人暮らしで身寄りのない方が病院で死去した場合は、病院長の名前で届け出を出す事ができます。
死亡届に記入する項目
届出人が死亡届に記入しなければならない項目は次の通りです。
故人に関する項目
故人の氏名、住所、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍、配偶者の有無と年齢、故人の属する世帯の主な仕事・職業。
故人の氏名は戸籍に登録されている通りに記入してください。外国人の場合は、本国での名前を記載します。住所は故人の住民登録にある住所を記載してください。
死亡時刻、死亡場所は死亡診断書(死体検案書)に記載されている内容を書き写します。故人の属する世帯の主な仕事・職業は、国勢調査のための項目になり、分からない場合は空欄にします。
届出人に関する項目
故人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、生年月日。
この他、役所に届け出た際に、窓口で火葬を行う火葬場や埋葬予定の墓地の名称、故人と届出人の続柄が尋ねられます。なお、本籍地などが不明な場合、空欄のまま提出しても、役所の業務時間内であれば調べてもらえます。
関連記事

死亡届の書き方とは?提出場所や期日なども紹介
「死亡届」は人が亡くなった際、最初に必要となる公的な書類です。 その後のさまざまな手続きでも必要とされることが多く、正確に記入して、期日までに所定の場所へ確実に提出しなければなりません。 こ...
続きを読む



死亡届の受理後、火葬許可証が発行される
死亡届が役所で受理されると、火葬許可証が発行されます。市町村によっては、死亡届と一緒に申請書が必要な場合があることも押さえておきましょう。また火葬許可証がないと火葬はできません。
ちなみに、火葬許可証は地域によっては埋火葬許可証と呼び方が違う場合があります。
火葬許可証は火葬する際の大切な書類なので、火葬まで紛失しないように注意し、火葬当日は火葬場に持参します。
斎場・火葬場が公営の場合は、市町村によって斎場や火葬場の利用許可の書類の申請が必要な場合があります。またその際に火葬許可証の提出が必要な場合もあります。
火葬が終わり遺骨を骨壷に納めた後、斎場や火葬場で火葬執行済と記された火葬許可証が返却されます。「埋葬許可証」と呼ばれていることもあり、お墓に遺骨を納める納骨の際に必要な大切な書類になるので、なくさないように大切に保管しておきましょう。
死亡届はいつまで保管しておくとよいのか
死亡届は役所に提出してしまうので手元には残りません。ただし、各種手続きや保険の請求などで必要になるため、事前に複数枚コピーを取って、全ての手続きが終わるまでは手元で保管しておきましょう。
また全ての手続きが終わったと思っていても、提出を求められたり必要な事があるかもしれないので、しばらくの間は保管しておきます。
紛失などしてしまった場合、市町村役場で特別な理由があり、一部の利害関係者であれば再発行してもらうことも可能です。
関連記事

死亡後に必要な手続きとは?書類や期限についても解説
大切な身内を亡くされ深い悲しみにあったとしても、遺族にはやらなければならないことがあります。 それは、死亡後に必要とされる手続きです。なかには法的に期限が定められている手続きもあり、すみやかに...
続きを読む



死亡届を提出しないとどうなるか
死亡届は故人の死亡を法的に証明する書類なので、提出しないとさまざまな不都合が生じます。

埋葬・火葬ができない
死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されず、火葬や墓地への埋葬ができません。
この火葬許可証を取得するためにも、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内で早急に提出するようにしましょう。
また死亡届を出さずに期限が過ぎてしまった場合や火葬や埋葬をせずに放置していると戸籍法により罰則が課せられるので注意が必要です。
年金受給停止手続きが行えない
年金受給者が亡くなった場合、厚生年金受給者なら死亡後10日以内、国民年金受給者なら死亡後14日以内に支給停止手続きを行う必要があります。
手続きは必要な書類をそろえて、年金事務所または最寄りの年金相談センターに提出します。電話で問い合わせの上、郵送も可能です。もし、手続きを行わずに年金を受け取っていると、年金法により10万円以下の罰金が課せられます。
死後も年金を受給するなど悪質な場合は、不正受給として一括返還を求められたり、詐欺罪として罰せられたりする可能性があります。また、手続きを行わないと、故人の未受給の年金や遺族年金を受け取れないおそれもあります。
関連記事
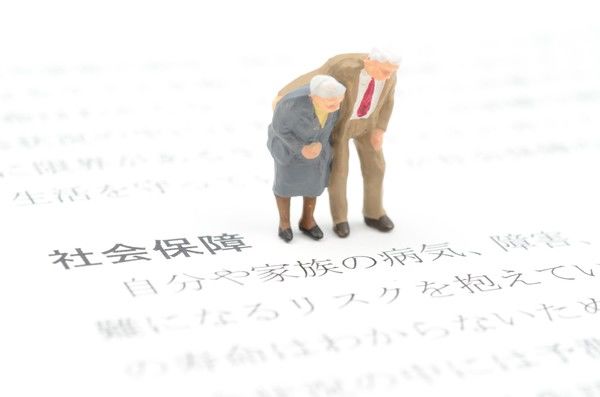
死亡後の手続き。年金の支給停止手続きの方法、流れについて
家族が亡くなると、まずは葬儀の準備に手一杯になりがちですが、それ以外にもさまざまな手続きや対応に追われます。 その一つが、亡くなった家族が年金の支給を受けていた場合の年金支給停止手続きです。 ...
続きを読む
介護保険資格喪失届が提出できない
故人が65歳以上の介護保険の第1号被保険者、または40歳~64歳未満で第2号被保険者だった場合には、死亡後14日以内に介護保険の資格喪失手続きを行わなければなりません。
手続きは、相続人に当たる人が故人の住民票のある市町村役場の介護保険担当窓口や介護保険課で行います。「介護保険資格取得・異動・喪失届」に必要事項を記載して、介護被保険者証と一緒に提出します。
手続き時には、マイナンバーか本人確認ができる書類を持参してください。この手続きを行わないと、未納分の保険料の支払いができず、納め過ぎた保険料の還付も受けることができません。
住民票が抹消されない
住民票の抹消届けは、死亡後14日以内に市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行うとされています。手続きの際には、届出人の印鑑と免許証、パスポートなど本人確認のできる証明書類が必要です。
ただし、死亡届を提出すると、故人の住民票は役所によって削除することが可能なので、実際には特別な手続きは不要です。住民登録が抹消された住民票は「住民票の除票」と呼ばれます。
世帯主の変更ができない
世帯主が死亡した場合は、住民票の世帯主変更届を14日以内に提出する必要があります。提出期限を過ぎると5万円以下の過料が課せられます。
手続きは、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行い、届出人の印鑑と免許証、パスポートなど本人確認のできる証明書類が必要です。
まとめ
死亡届は人が亡くなったことを法的に証明する書類です。
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外の場合は3カ月以内)に作成し、故人の死亡地または本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれかの市町村役場に提出します。
提出の際には、病院で亡くなった場合、死亡を確認した医師による「死亡診断書」、事故死・変死などの場合は監察医などによる「死体検案書」を添付しなければなりません。
死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬・埋葬が可能になります。また、役所や保険会社を対象にしたさまざまな手続きの際にも、死亡届(死亡診断書)が必要です。
万一、提出しないとさまざまな弊害が生じるので、必ず期日までに提出しましょう。



葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

















