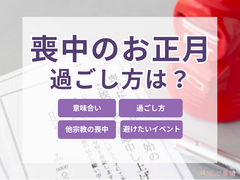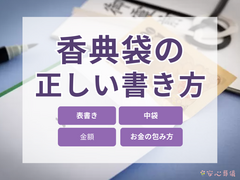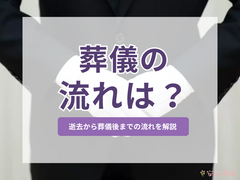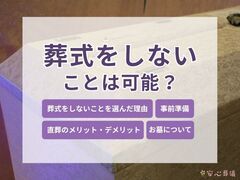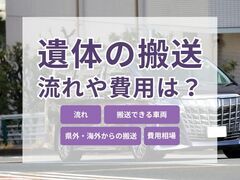不祝儀袋の選び方とは?表書きやお金の入れ方も紹介します

お葬式などの不幸ごとで使われる香典袋は、不祝儀袋とも呼ばれます。
不祝儀袋は急に必要となることも多いですが、いざというときに正しいマナーを知らないと困ることもあるでしょう。
そこで今回は、不祝儀袋について選び方やマナーなどを紹介します。



不祝儀袋とは
不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)とは、通夜・告別式などの弔事や法事の際に遺族などに渡す現金を包む封筒のことで、宗教宗派、地域、使うタイミングなどによって使用するべき袋の種類や表書きが異なります。
不祝儀袋のことを香典袋と呼ぶ場合もあります。本来「香典」は仏教に由来する言葉ですが、世間一般的には宗教宗派問わず香典袋という言葉が使われているのが実状です。
一方で不祝儀袋という呼び方は、宗教宗派を問わずに使われます。
宗教ごとの不祝儀袋
不祝儀袋にはさまざまな種類があり、宗教宗派ごとで選び方や扱い方に異なる部分もあるので注意が必要です。ここでは宗教ごとの不祝儀袋について説明します。
不祝儀袋の水引には黒白、双銀、黄白など、いくつかの種類がありますが、宗教宗派によって色が決まっているわけではありません。
最も多く使われるのは黒白の水引で、宗派を問わず使うことができます。
また、双銀も黒白で並んで一般的な不祝儀袋ですが、包む金額が比較的大きい場合やお布施を包むときなどに使われる傾向があります。
この他には、神道では黄白や双白の水引、キリスト教では白無地や十字架が書かれた不祝儀袋なども使うことがあります。
関西地方では、仏式を含めても黄白を用いるケースが見られるなどの地域性もあるので、各地域の慣習に合わせて選ぶとよいでしょう。
仏式の場合
仏式では、葬儀に参列する場合や四十九日法要の前までに渡す場合は、表書きが「御香典」や「御霊前」となっている不祝儀袋を使用します。
四十九日以降は「御仏前」または「御香典」の表書きです。
例外として、「霊」という考え方を認めていない浄土真宗では「御霊前」は使用しません。葬儀の段階から四十九日以降の法要でも、一貫して「御仏前」(「御香典」でも可)を使用します。
「御香典」「御香料」「御供料」などは、仏式全般の葬儀や法要どちらでも使用することができる表書きです。
どの表書きがふさわしいか判断できない場合は、「御香典」を選んでおくのが無難でしょう。
なお蓮の絵柄が入った不祝儀袋は仏式でのみ使用となります。
神式の場合
神式では、本来であれば「御玉串料」「御榊料」「御神前」という表書きの不祝儀袋を用いますが、「御霊前」を使用しても問題ないとされています。
玉串料は、玉串奉奠を行う際の神様のお供え物として納める玉串代のことで、御榊料は、御神前に供える時に使うもので榊の代わりという意味があります。
神饌料は、神様へお供えする食べ物のことを指す「神饌物(しんせんもの・しんせんぶつ)」の代わりに供える金銭のことです。
「御玉串料」「御榊料」「御神前」という不祝儀袋は「御霊前」という表書きと比べると入手しにくいかもしれません。
入手できない場合には、表書きの書かれていない不祝儀袋を購入して、「御玉串料」などの表書きを自分で書き入れます。
キリスト教式の場合
キリスト教式の場合は「御花料」や「献花料」という表書きが基本です。
しかし、神式の場合と同様に「御花料」や「献花料」という表書きの不祝儀袋は身近なところで入手できないこともあるので、自分で手書きしても問題ありません。
なお不祝儀袋は無地でもよいですし、もしくはキリスト教用の十字架や百合の絵柄が入ったものでも構わないでしょう。
キリスト教のどの宗派か分かる場合は、以下の表書きを使いましょう。
カトリックであれば「御ミサ料」、プロテスタントであれば「御花料」、キリスト教全般で使えるのは「御花料」「お花料」「献花料」です。
なお「御霊前」については、カトリックでは許容されていますが、プロテスタントでは使用できないので注意しましょう。
無宗教、宗教や宗派が不明の場合
お葬式に参列するときは、宗教宗派が分からない場合もあるかもしれません。この場合の表書きは「御香典」としておくことが一般的です。
無宗教葬やお別れ会に参列する場合は、「御香典」または「御花料」の表書きを使用するとよいでしょう。
お別れ会などで会費制の場合は、白無地の封筒を用いることが一般的です。



送り主の名前の書き方とは
「御霊前」や「お花料」などが書かれた不祝儀袋の表書きの下には水引がありますが、その下に送り主(多くの場合は自分です)の名前を書き入れます。
送り主の名前の書き方についても知っておきましょう。
表書き・水引の下に薄墨で書く
個人で参列する場合などにおいては、水引を挟んで表書きの下にフルネームで書き入れます。通夜・葬儀に持参する不祝儀袋に名前を書き入れる際は薄墨を使用することがマナーです。
本来は毛筆を使用して書くものでしたが、薄墨であれば筆ペンを使用しても構いません。
薄墨で書く理由は諸説ありますが「充分な濃さに墨を磨る余裕もなく、急いで駆け付けました」「故人を悼んで涙を落とし、墨が薄くなりました」など、弔意を表すことに由来していると言われています。
濃い墨しかない場合は、ペン先を少し水に浸して薄墨のように水分を多くして薄墨に近い状態にして書くようにします。
また筆ペンなどがないからといって、ボールペンを使うのはマナー違反になります。
なお、薄墨を使用するのは通夜と葬儀・告別式までが基本で、四十九日などの法要では通常の濃さの墨を使います。
また地域によっては通夜や葬儀も薄墨ではなく濃い墨を使用するところもあります。
夫婦で包む場合
夫婦ともに故人や遺族と深い付き合いをしている場合には、二人の名前を書きます。通常は夫の名前をフルネームで書き、その名前部分の左側に妻の名前のみを書き入れます。
夫婦で親しさにばらつきがある場合は、故人との関係が親しい代表者のみ姓名を書き、パートナーは名前のみにするのが一般的です。
特に深い付き合いでなかったのであれば、どちらかのフルネームのみとするのが一般的です。
複数人で香典を包む場合
3名までであれば横に並べて各人の名前をフルネームで書きます。4名以上になる場合には「〇〇一同」とします。
例:友人一同
友人関係で特に立場に上下関係がない場合は、左から五十音順で書きましょう。
「〇〇一同」の場合は、中袋に全員の名前を書いた紙を同封します。
職場の部署などで包む場合
職場の仲間で包む場合でもどのような括りとするかによって書き方も変わります。「◯◯有志一同」「◯◯会社◯◯課一同」「〇〇スタッフ一同」などと表記します。
会社として包む場合
会社名、もしくは会社名に代表者名を加えた形で書きます。会社名に代表者名を加える場合には、代表者名が不祝儀袋の中央にくるように書き、会社名や肩書は名前の右側に書き入れます。
香典を連名にする場合のマナーについては以下の関連記事をご覧ください。
関連記事
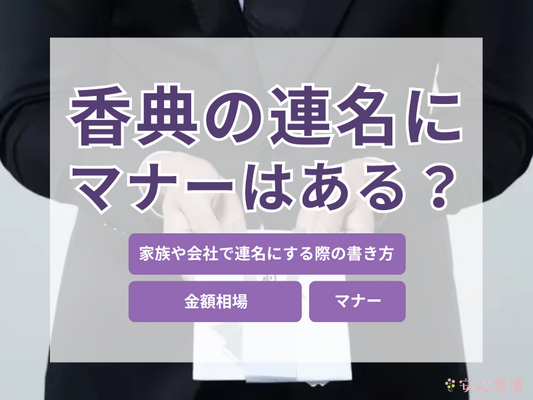
香典を連名にする場合のマナーとは?夫婦や会社から送る場合などをご紹介します
葬儀で香典を包む際、複数人でお金を出し合ったり、家計を同じとする方々が出す場合には連名にすることがあります。 香典を連名で出す場合、香典袋の書き方に決まったルールがあるなど、気を付ける点がいく...
続きを読む
中包みの書き方と包み方とは
不祝儀袋には、中に金銭を包む用紙が入っているものや袋が入っているものがあります。金銭を包む用紙のことを「中包み」と言い、袋状になっているものは「中袋」と呼びます。
中包み・中袋の書き方
表側に金額を縦書きで書きます。金額の上に「金」と書いてから金額を書きますが、金額は旧漢字で書くことが通例です。例えば、「金壱萬園」や「金参萬園」と表記します。
裏側には住所、氏名を書きます。
中包み・中袋によっては金額、住所、氏名を全て裏面に記入する欄が設けられているものもありますが、この場合は指定された箇所に書き入れます。
中包み・中袋に書く内容は、葬儀の前後に関わらず薄墨を使用する必要はありません。むしろ受け取った相手にとって読みやすいことの方が大事なので、ペン類を使用しても問題ありません。
住所や氏名、金額の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事
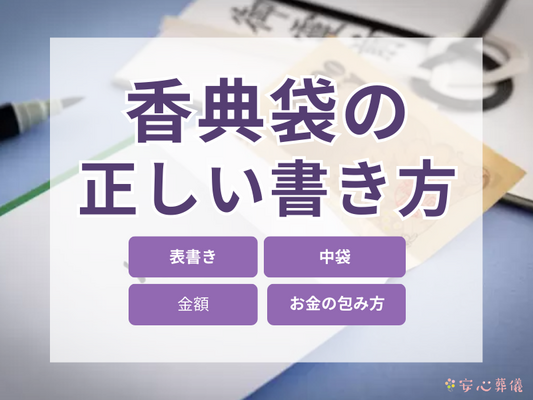
香典袋の正しい書き方とは?表書きや金額を書く時のマナーを解説
本記事の結論香典袋には主に①表書き②氏名③住所④包んだ金額を書く外袋に表書きと氏名を記入する際は、薄墨の筆ペンを使用する中袋には基本的に住所・氏名・金額を書く縦書きで金額を書く際には大字(だいじ...
続きを読む
中包みの包み方
中包みが付いている不祝儀袋の場合には、折り目に沿って畳んでいくことになります。
基本的に中包みの紙のやや左下寄りに置き、下から上へ、左右を折るときは左・右の順に折っていきます。最後に折り返した面が裏側です。
香典の合計額で端数が出ることは構いませんが、偶数になる金額や4(四)や9(九)になる金額は避けるようにしましょう。
四は死、九は苦を連想させることから、「忌み数」となります。



香典の渡し方とは
不祝儀袋にお金を包んで用意した香典ですが、渡す際のマナーにも注意しましょう。
ここでは、香典の渡し方について注意すべき主なポイントを紹介します。
袱紗に包んで持参する
本来、香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参することがマナーです。袱紗は不祝儀袋の汚れや破損を防ぎ、丁寧な気持ちを表すために用います。
葬儀の場ではお悔やみの言葉などの挨拶を添える
香典を差し出す前に「この度はご愁傷様でございます」「御霊前にお供えください」など一言添え、一礼してから香典を差し出します。
遺族は、悲しみの中で対応しています。また、葬儀で忙しい中での長い言葉はかえってマナー違反になるので注意が必要です。
葬儀会場での受付で渡す際も「この度はご愁傷様でございます」「お悔やみ申し上げます」などの言葉を添えて香典を出し、手短に受付を済ませましょう
なお、法要の場では遺族に直接渡すことが多いと思いますが、この場合は「御香典です」と申し上げつつお渡しすればよいでしょう。
香典を渡す際のマナー
香典を渡すときは袱紗から取り出し、袱紗の上に乗せて差し出します。
金封タイプの袱紗の場合は、袱紗をお盆のようにして香典袋を置いて渡しましょう。
香典を渡すときは、必ず両手で持って渡します。受付の香典盆が置かれ、そちらに直接のせる場合もあります。
香典の持ち方は、右手のひらに袱紗を置き、左手で袱紗を開いて香典を取り出します。
相手側が表書きや名前の文字が読めるように向きを変えてから渡しましょう。
葬儀会場ではなく葬儀後に自宅に訪問して渡す場合は、仏前に供えるか遺族に直接手渡しします。
仏前に供える場合は、自分で文字が読める向きで供えるようにして、供えずに遺族に直接渡す場合は、お悔やみの言葉に「御霊前にお供えください」と加えて渡します。
遺族の自宅へ弔問するケースで、菓子折りや御線香などの品物を持参している場合には、この品物の上に香典を載せて一緒に差し出すという方法も問題ありません。
ふくさの包み方については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
関連記事

葬式やお通夜でのふくさの包み方とは?ふさわしい色などの選び方も紹介します
葬儀に香典を持参する際、「袱紗(ふくさ)」に包んで持参するのが基本です。 袱紗の存在はなんとなく知ってはいるものの、袱紗の包み方や適した色、マナーなど、詳しくは知らないという方もいるのではない...
続きを読む
最後に
今回は、不祝儀袋について選び方やマナーなどを紹介しました。
一般的に香典袋と呼ばれるものも不祝儀袋です。
不祝儀袋には宗教によって選び方が異なったり、薄墨の筆記具を使用する場合とそうでない場合があったりと注意すべきことがいろいろあります。
どのような筆記具を使用する場合も、丁寧に書くことを心掛けましょう。
不祝儀袋は急に用意しなければならないものですが、いざというときに困らないように袋の選び方や送り主の名前の書き方など、適切な使い方を知っておくと安心です。
不祝儀袋が必要となった際には、今回の内容を参考にしてください。



葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。