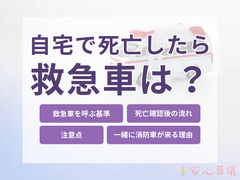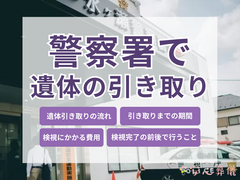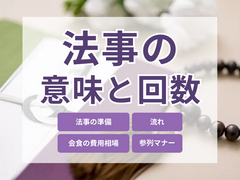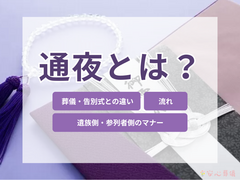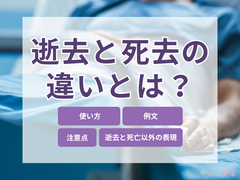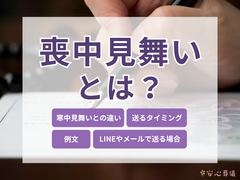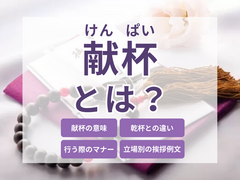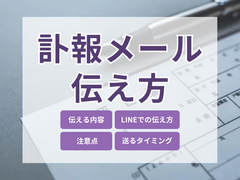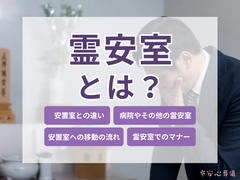コロナ禍での葬儀の現状、感染拡大防止のための配慮について解説

コロナ禍での葬儀の現状、感染拡大防止のための配慮について解説
※この記事は2020年7/27時点の状況を元に執筆しています。
参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及び疑いのある方の処置、搬送、葬儀、火葬などに関するガイドライン」
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止策の一環として、不要不急の外出や、多人数での集まりを避けるよう推奨されています。こうした状況下、葬儀にはどのような影響が及んでいるのでしょうか。
本記事では、コロナ禍での葬儀の現状や注意点、新型コロナウイルス感染により亡くなった方の葬儀について解説します。



コロナ禍で外出自粛要請が発令されていても葬儀は可能
外出を伴う「葬儀」は、コロナ禍においてどのように捉えられているのでしょうか。
葬儀場は自粛要請対象ではない
緊急事態宣言発令中は、多くの施設や店舗が休業・時短要請を受けます。
しかし、葬儀場は「社会生活を維持する上で必要な施設」であるとして、そうした要請を受けない施設に当たります。
葬儀場が自粛要請対象外であるという事実は、葬儀が必要性・重要性を持った儀式であるとする社会通念や、「不要不急の用件」には当たらないとする政府見解を裏付けていると言えるでしょう。
感染拡大に配慮した上での葬儀
外出自粛要請が発令されている場合にも、葬儀自体の自粛は求められません。
しかし、外出したり、複数人が一箇所に居合わせたりすることによる感染リスクは存在します。
そのため、感染拡大防止に配慮した形での葬儀になるよう、ほとんどの葬儀社で何らかの感染防止策(マスク着用、手指の消毒、検温など)が取られています。
なお、各社がどのような対策を取っているかについては、ウェブサイト上や葬儀社建物入口などに提示されていることが多いようです。気になる方は、事前に葬儀社のウェブサイトなどで確認するとよいでしょう。
コロナ禍で葬儀の規模は縮小傾向にある
コロナ禍によって葬儀規模は縮小傾向にあるようです。遺族や葬儀会社の各種対応にはどういったものがあるでしょうか。
コロナ禍での葬儀は火葬式や一日葬、家族葬が多くなっている
感染拡大防止のため、密閉・密集・密接のいわゆる「3密」を避けることが求められています。
一般的な葬儀では、多くの参列者が屋内会場に集まって式や会食を行いますが、コロナ禍では感染拡大防止の観点から、規模を縮小して行うことが多くなっています。
具体的には、通夜や告別式を行わず火葬のみ行う火葬式(直葬)や、通夜を省略して告別式のみとする一日葬、参列者をほぼ遺族・親族のみに限定する家族葬のスタイルで行われるケースが増えています。
また、通夜後に行われる通夜振舞いの会食も、参列者が集まって行うのではなく、お弁当を持ち帰ってもらう形式にするなどの対応も多いようです。
いわゆる「自宅葬(ステイホーム葬)」も
近年、都市部においては、自宅ではなく専用会場での葬儀が一般的となっていますが、コロナ禍の影響で自宅での葬儀が再び見られるようになっています。
葬儀社では「ステイホーム葬」などの名称のプランとして提案していることがあり、この場合、単に自宅を会場とするだけでなく、参列者をほぼ近親の遺族のみかつ少人数に限定することが大半です。
また自宅葬(ステイホーム葬)では、火葬場へ移動しての火葬や収骨といった実際に行われる火葬の手順を葬儀社スタッフが代行することもあります。外出や密集、多人数との接触も避けられるコロナ禍ならではの葬儀の形として利用者が増加しています。
関連記事

自宅葬とはどのような葬儀?葬儀の流れや自宅葬の条件も紹介
葬儀は葬祭ホールで行われることが一般的ですが、必ずしも葬祭ホールで行わなければならないことはなく、さまざまな選択肢があります。自宅もその一つです。 自宅で葬儀を行うことは家族には負担となる面も...
続きを読む
オンライン葬儀も登場
遠方の親族や、友人・知人といった方々に参列してもらうことが難しい現状に対する解決策として、「オンライン葬儀」も登場しています。
オンライン葬儀とは、基本的に遺族や近隣に住む近しい親族のみが葬儀会場へ集まり、その他の参列者はビデオ会議システムなどを利用して葬儀の様子をオンライン中継し、画面越しで葬儀に参列してもらうというものです。
オンライン決済での香典預かり機能や、生前の故人の思い出の写真の共有機能、弔電・供花手配機能など、オンラインならではの専用システムも用意されており、新たな葬儀の方法として注目されています。
関連記事

オンライン(リモート)葬儀とは?一般的な葬儀との違いやメリット・デメリットについて解説します
新型コロナウイルスの流行によって、葬儀にも変化の波が訪れており「オンライン葬儀」という新しい取り組みが始まっています。 オンライン葬儀は、葬儀会場から離れた場所にいる方々にも参列してもらえる葬...
続きを読む



新型コロナで亡くなってしまった方の葬儀について
新型コロナウイルス感染が原因で亡くなった方の葬儀は、どのように行われるのでしょうか。
新型コロナで亡くなった方も葬儀を行うことが可能
芸能人のニュースなどの影響もあり、新型コロナウイルスに感染して亡くなった方は、遺族との対面も叶わず、「お骨」となって自宅に戻るというイメージが強いようです。
しかし、厚生労働省からは「感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります」(参考:埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン)との見解が示されており、葬儀を行うことが禁止されているわけではありません。
とはいえ、新型コロナウイルス感染によって亡くなった方については、義務付けられてはいないものの、死亡してから24時間以内の火葬が認められており(通常は24時間経過後でないと火葬不可)、火葬によりウイルスを早急に死滅させる必要性があると認識されています。
葬儀の実施は可能ですが、感染リスクはゼロではなく、防止のために最善を尽くさなければなりません。先に火葬を済ませて日を改めて、後日に葬儀を行うケースも見られます。家族間や葬儀社としっかり検討し、葬儀の進め方を決めましょう。
遺体は非透過性納体袋に密封したまま納棺される
新型コロナウイルスについて、まだ分かっていない部分も多いのが現状です。葬儀では他の多くの感染症に照らし合わせた対応がなされています。
遺体は、非透過性納体袋(遺体から出る体液などを一定時間内部に留めておくことが可能な遺体収納袋)に密封され、袋の外側を消毒した上で納棺されます。
また、火葬する際も、非透過性納体袋に密閉されたまま行うのが望ましいとされています。
遺体への対面や接触も、法的には禁じられていない
感染防止の見地から、できる限り避けるべきことですが、遺族の心情として、故人の顔も見られず、触れることもできずにお別れしなくてはならないのは、あまりに忍びないと言えるでしょう。
実は、火葬前に遺体に触れることは法的に禁じられてはおらず、厚生労働省の見解も「火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください」としています。
ただし実際問題として、葬儀社スタッフへの感染のリスクなどの理由で、葬儀社側からストップがかかることも少なくないでしょう。
手袋や防護服、ゴーグルを装着するなどの対策を取った上での対面を含むプランを提案している葬儀社もあるようです。そうしたプランを検討するのも一つの方法です。
葬儀社によってはコロナによる死亡の葬儀は受けられない場合も
葬儀社側としては、遺族や参列者、自社スタッフの感染リスクについても考慮しなくてはなりません。
そのため、充分な感染対策が取れないと判断している葬儀社は、新型コロナウイルス感染により亡くなった方の葬儀を受け入れられない場合があります。
まずは、葬儀社に事情を説明して受付可否を確認しましょう。
新型コロナ禍での葬儀の注意点

コロナ禍での葬儀における注意点にはどういったものがあるでしょうか。
参列者・葬儀社スタッフはマスクを着用
遺族のみで行う葬儀であっても、葬儀社スタッフや火葬場の係員など、複数の人との接触は避けられません。参列する際はマスクを着用するようにします。
また、葬儀社スタッフも基本的にマスクを着用しているはずです。
関連記事

コロナ禍での葬儀はマスクを着けるべき?通常時の場合も紹介
※この記事は2020年8月19日時点の状況を元に執筆しています。 世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。 有効な薬品の開発を待ち望む状況下において、私たちが今すぐにできる感染対策...
続きを読む
搬送車(寝台車)に遺族が同乗できないことも
コロナ禍の現状を鑑み、ドアノブや椅子などの他に、遺体を運ぶ搬送車についても消毒を行っている葬儀社は多いでしょう。
それでも、ドライバー以外の誰かが同乗すれば車内での感染リスクがあるため、遺体を搬送する車への遺族の同乗が認められない場合もあります。
必要に応じて防護服、ゴーグル、手袋、ガウンなどを装着
一般的に、感染対策として身に着けるのはマスク程度ですが、状況によっては手袋やゴーグル、防護服といったより厳重な対策アイテムの着用が求められるケースもあるようです。
火葬場で時間制限が設けられている場合も
火葬場には一般的に複数の火葬炉があり、それぞれの炉の前に各遺族・親族や僧侶が集まることが多いです。
そうした状況において、多人数が密集することを避ける必要性が出てきます。炉前に立ち会う人数の制限、ロビーや待合室での待機の禁止、炉前に留まる時間を制限するなどの対応を取っていることがあります。また、通常は閉じておく扉を感染予防対策として解放している火葬場もあるようです。
葬儀社との打ち合わせ方法にも違いが
葬儀社との打ち合わせは、顔を合わせて行われることが当たり前でしたが、感染予防対策の一環として電話やオンラインで行われる場合があります。中には葬儀当日まで担当者と会わないといったケースもあるため、気になる方は一度葬儀社へ打ち合わせのやり方について確認しておくとよいでしょう。



まとめ
コロナ禍においても葬儀場は自粛要請対象ではなく、外出自粛要請が発令されていても葬儀は可能です。ただし、感染リスクの高まる密集状態を避けるため、家族葬や一日葬、火葬式などが増加傾向にあり、火葬後に遺骨を前にして行う葬儀も注目されています。
また、新型コロナウイルス感染によって亡くなった方でも葬儀を行うことは可能ですが、葬儀社によって受入状況が異なるので確認しておくと安心です。感染対策として遺体搬送車への遺族の同乗が認められない場合もあるようです。
コロナ禍の葬儀は、これまでのスタイルから変化しています。何に気を付け、何ができるのか、今回の記事を参考にして知識を蓄えておいてください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。