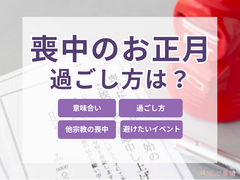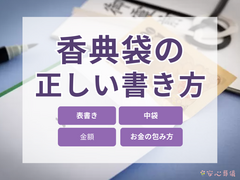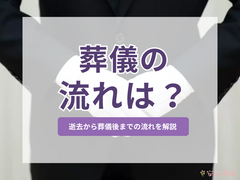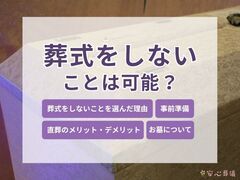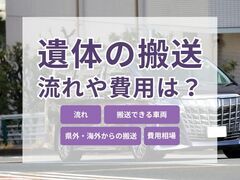納棺の手順とは?納棺の流れや注意点なども紹介します

葬儀を行う前に遺体は必ず棺に納められます。これを「納棺」と呼びます。
お葬式の一連の流れの中で、「納棺」は重要な意味を持つ儀式の一つです。納棺は家族や親族が参加して行いますが、どのように臨めばよいのか戸惑う方も多いことでしょう。
納棺を滞りなく進めるためには、手順や準備、注意点などを知っておくことが大切です。
今回は葬儀における納棺を解説します。



納棺とは
まず、納棺とはどういうものなのかを説明します。
納棺を行う意味
納棺は、遺体を棺に納めることです。遺体を洗い清め(または清拭したり)、死装束を整え、副葬品とともに棺に納めます。
昔は親族のみで納棺を行っていましたが、現在では、葬儀社や納棺専門スタッフの案内に従いながら、家族や親族が手伝う形で納棺が進められていきます。
納棺は自宅で行う場合と、葬祭ホールなどの施設で行う場合があります。自宅では充分なスペースが確保できない場合もあり、最近は病院から直接葬祭ホールなどの施設に搬送することが増えているため、施設で納棺を行うことの方が多くなっています。
納棺は、今まで布団に横たわっていた故人を棺に納めるということで、遺された方々にとっては大切な方の死を強く実感する場面になります。そのため、納棺に立ち会うことは、遺族が故人の死を受けとめながら最後の身の回りの世話をし、お別れの時間を過ごすという意味も持ちます。
遺体の処置や着替えが必要な場合、遺族や親族はその間は席を外し、納棺を担当するスタッフによって処置が行われるのが一般的です。
遺族や親族の立ち会いの中で故人の肌が多少露出するような場面があれば、遺族やごく近い親族(故人が女性の場合は女性の親族のみにするなど)に入室を限るようにし、故人の姿が整ってから他の親族も加わって納棺に臨むなど、故人の尊厳を守る配慮が必要です。
納棺は、故人にとっても遺族にとっても、大変プライベートな場面です。もし、親族以外の人物から納棺に立ち会わせてほしいと申し入れがあった場合は、よほど故人との仲が深く、遺族としても立ち会ってほしいと思う間柄でなければ、断っても失礼には当たりません。
納棺師とは
納棺師とは、遺体を清潔に整え、棺へと納める専門的な役割を務める人です。単純に遺体を棺に納めるだけでなく、納棺の儀式を担当します。
納棺師は、遺体を清める「湯灌」、故人の顔を生前の姿に近づける「死化粧」といった納棺の儀式での一連の内容に対応し、故人の安らかな旅立ちをサポートし、遺族の心情をケアします。
近年では、納棺師の肩書きをもつ人物が納棺の儀式を担当するケースだけでなく、葬儀社スタッフが対応することも増えています。
納棺のタイミングや時間とは
納棺が行われるタイミングや時間については、地域などの状況によっても異なりますが、通夜当日に行われることがほとんどです。例えば、18時から通夜式が始まるのであれば、当日の14:00〜15:00位に納棺が行われることが多いようです。
納棺の儀式に要する時間は30分から2時間程度が目安です。
納棺に立ち会う人
納棺は故人の身体に直接触れる場面が多く、場合によっては多少肌が露出することもあるため、遺族や親族といった故人のごく親しい近親者のみが参列します。通夜や葬儀とは異なり、よほど近しい間柄でなければ友人や会社関係者らは基本的に参列しません。
故人と付き合いがあって納棺への参列を希望する方がいた場合、断っても失礼には当たりません。



納棺の流れ
ここでは、納棺の流れを紹介します。
仏式葬儀の場合で、葬祭ホールに安置して通夜当日に葬祭ホールで納棺を行う例です。亡くなった場所や状況、地域などによって流れは変わることもあるので、あくまで一例になります。
参加者の場合
納棺に参加するのは一般的に家族と親しい付き合いのある親族のみです。葬儀社スタッフから納棺の儀を開始する案内があり、参加者は故人の周りを囲むようにして集まります。参加者全員で合掌および一礼をして納棺の儀が始まります。
湯灌
近年、湯灌は略式の「清拭湯灌」で行われることが多く、家族や親族が故人を囲んで、清浄綿や布を用いて肌を拭き清めます。バスタブを持ち込み、シャワーを用いて故人を入浴させるようにきれいに洗う湯灌は、オプションサービスになっているようです。湯灌後、着せ替えをしたのち、死化粧を行う場合もあります。
故人が亡くなってから火葬するまでに時間が空く場合(故人が海外で亡くなった場合など)には、時間経過に伴う遺体の損傷を防ぐためのエンバーミング処置が行われることもあります。
納棺師や葬儀社スタッフの案内の元で死装束を整える
納棺師や葬儀社スタッフの説明を受けながら、家族などの参加者が遺体に死装束を整えていきます。白足袋、脚絆、手甲などを身に付け、六文銭を入れた頭陀袋を首にかけます。経帷子(きょうかたびら)とよばれる着物は、着せるのではなく身体の上に掛けるだけの場合もあります。最後に木製の念珠を手にかけます。
以下の記事でも湯灌や死化粧について取り上げていますのでぜひご覧ください。
関連記事

湯灌とは?行う意味やマナー・流れ・費用について解説
普段の生活の中で「湯灌(ゆかん)」という言葉に触れることは、まずないでしょう。 湯灌は、人が亡くなった際に広く行われている儀礼の一つです。故人を見送った経験がある方ならともかく、そうでない方は...
続きを読む
関連記事

死に化粧やエンゼルケアとは?行うタイミングや手順とエンバーミングについても紹介
「死に化粧(しにげしょう)」という言葉を知っている人は多いのではないでしょうか。しかし、遺体に施す処置(化粧)であること以上に詳しく知る方は少ないと思います。 本記事では、「死に化粧とは何か」...
続きを読む
遺体を棺に移動
家族を中心に参加者の手で、遺体を棺へと納めます。
副葬品を棺へ
故人の姿を整えてから、故人の愛用品などの副葬品を棺の中へ納めます。
棺の蓋を閉じて納棺の儀終了
棺の蓋を閉じた後、今一度参加者全員で合掌し、一礼をして終わります。
死装束のしきたりとは
納棺に参加する際、知っておいた方がよい死装束のしきたりがあります。
死装束とは
死装束とは、亡くなった方に着せる衣装のことを言います。伝統的な死装束は白の仏衣ですが、宗派によって異なる場合があり、近年は故人が愛用していた洋服や遺族が旅立ちのために用意した服装に着せ替えることも増えています。
仏式の場合
死装束は「旅装束(たびしょうぞく)」または「旅支度(たびじたく)」とよばれることもあり、浄土へ旅立つための旅姿となります。仏式では、故人は「四十九日間」の旅に出ると言われていて、この旅装束(巡礼衣装)が用意されるのです。
旅装束は、天冠、手甲、頭陀袋、脚絆、足袋、杖、編笠、草履などで一式となります。天冠は額につける三角の布当てで、仏様の弟子になった証と言われています。
天冠(てんかん)を付けると顔の印象が変わってしまうため、実際には身に着けず棺の中に一緒に納めるだけで済ませる場合が多くなっています。
手甲(てっこう)はその名の通り手の甲に着け、脚絆(きゃはん)は足のすねに着けて道中の足元を守ります。
また、頭陀袋(ずだぶくろ)は首から下げる小物入れですが、この中には三途の川の渡し賃として六文銭(ろくもんせん)が納められます。このとき実物の硬貨は棺に入れることができないので、実際には紙に印刷された小銭をいれておきます。
ただし、「亡くなったらすぐに極楽浄土に行く」との考えから四十九日の旅がないとされる浄土真宗では、旅の姿にはしません。
神式の場合
神式の場合、故人は家や子孫を守る神様になるという考え方があり、神様の姿とするための浄衣(じょうえ)が用意されます。男性は白い狩衣(かりぎぬ)、烏帽子(えぼし)、笏(しゃく)、女性は白い小袿(こうちき)、扇(または扇子)です。
キリスト教の場合
キリスト教には決まった死装束はありませんが、故人が生前好んでいた服やドレスを着用させる場合が多いです。さらに、木製の十字架を手元に沿えることもあります。
その他
・経帷子の襟は左前(左が手前)になるように着せ、通常とは反対の着せ方をします。これには、この世と死後の世界が真逆であるという考え方や、お釈迦さまが入滅したときの着方に倣うためなどの説が理由として考えられています。
・死装束を身に付けるとき、帯や紐は縦結びで結びきりにします。解けないようにしっかりと結ぶ意味と、通常とは異なる結び方にするという意味があります。
・旅装束や神様の衣装ではなく、スーツや和服など生前に故人が好きだった衣装を死装束とすることもあります。
・最近では終活の一環で、納棺時に着用するエンディングドレスを事前に用意しておくこともあります。エンディングドレスには、一般的な死装束でみられる白以外にもピンクや花柄など、華やかな雰囲気のものが多くあります。
・死後硬直で実際に着せることが困難な場合など、死装束を身体の上から掛けるのみで済ませる場合もあります。
・地域によっては「逆さごと」という風習により、身体の上から死装束を掛ける際、上下逆さにするところもあります



副葬品の注意点とは
故人の愛用していたものなどを副葬品として全て棺に納められるわけではなく、棺に納められるものと、納められないものがあります。ここでは副葬品に関する注意点を解説します。
副葬品の注意点
・基本的には燃えるもの
副葬品として棺に納められるものは、基本的に燃えるもののみです。
・燃えるものならば何でもよいわけではない
水分を含んだもの、厚い書籍、硬質な木材製品は燃えにくいので避けましょう。
・有毒ガスや爆発にも注意
プラスチック製品など有毒ガスが発生する可能性があるもの、密封された缶や瓶など爆発の危険性があるものは納められません。プラスチック製品やゴム製品は、溶け出して遺骨に付着してしまう可能性もあるので要注意です。
・革製品は副葬品に適さない
革製品も燃えにくい素材です。燃え残りが遺骨に付着してしまったり、遺骨を傷付けてしまう場合があるため、納めるのは避けましょう。
・遺骨に付着する色などにも注意
色素の強い生花も遺骨に色が残る可能性があると言われていますので避けた方が無難です。
副葬品に向かない品の例
- 酒瓶
- メガネ
- 入れ歯
- ペースメーカー
- ゴルフクラブやゴルフボール
- 果物(小さくカットした上で少量なら可)
- 腕時計
- 貴金属(結婚指輪など)
- 宝石
- 金属製の仏具など
- 厚い書籍
- 紙幣や硬貨
- 革製品
- 釣り竿
- ライター
- ぬいぐるみ(サイズによっては燃え切らない可能性もあるため、事前に確認が必要)
- 靴などのゴム製品
特に注意が必要なのはペースメーカーです。見た目で確認することができないため、遺族からの申告がなければ把握できません。申告をしていないと、火葬中に重大な事故を引き起こす原因になります。故人が生前ペースメーカーを使用し体内に残っている場合は、必ず申告するようにしましょう。
また、意外と思われるかもしれませんが、果物も避けた方がよい品物に含まれます。「故人が好きだった」とお供えされていることもありますが、水分量が多く火葬に影響するだけでなく、種類や形状によっては破裂の危険もあります。
棺に納められないもので、メガネや腕時計などの小物については火葬が終わった後、骨壺の中に副葬品として納める場合もあります。
副葬品については火葬場によってルールが定められています。事前に葬儀社または該当の火葬場へ確認をすることがお勧めです。
副葬品の注意点については以下の記事でも解説しています。
関連記事

副葬品とは?葬儀の際に棺に入れて良いものといけないものを紹介します
故人と共に柩の中に納める副葬品。送り出す側は副葬品に想いを託して、故人が生前に愛用していたものや、送る側の想いを込めたものを納めます。しかし、どんなものでも副葬品として柩の中に入れてよいわけでは...
続きを読む
納棺に掛かる費用
葬儀社によって異なりますが、納棺の費用相場は10万円前後のケースが多いと言われています。納棺の費用が含まれているプランもありますし、逆にオプションとなっていることもあります。
納棺を希望する場合は、事前に葬儀社へ費用などを確認しておきましょう。



最後に
今回は葬儀における納棺を解説しましたが、納棺の意味、手順、注意点などについて理解してもらえたのではないかと思います。
家族として故人に対し、最後にしてあげられることは限られています。納棺は、その限られたことの一つとなる重要な儀式です。
この重要な儀式を滞りなく進めるためにも、今回の内容を参考にしてください。



葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。ギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。ギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。