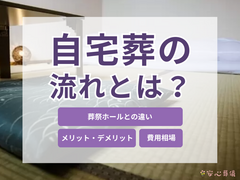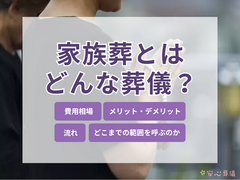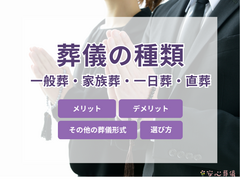家族葬で供花は送ってもいい?手配方法や注意点も紹介します

お葬式には「お花」が付き物で、それは家族葬であっても同様です。
お世話になった故人、大切な付き合いをしている遺族などに供花を贈りたいという思いは多くの方が抱く気持ちです。
しかし、家族葬では参列や香典とともに供花を辞退としているケースもあります。家族葬の場合、供花はどのように考え、対応をしたらよいのでしょうか。
そこで今回は、家族葬における供花のマナーや贈り方などを紹介します。



家族葬の場合、供花は贈ってもよい?
ここではまず供花とは何かを確認し、その後家族葬での供花の扱いについて説明していきます。
供花とは
供花とは、神仏や故人に対してお供えする花のことで「きょうか」や「くげ」と呼ばれています。
供花一つを1基(いっき)、2基を一組として一対(いっつい)と呼びます。一基と一対、どちらで贈るかは故人との関係性にもよって、特に決まりはありません。供花を一対で出すのは喪主や「子供一同」など故人と近しい親族の場合が多いため、友人や会社関係などは一基で贈るのが一般的です。
香典の代わりとして供花を贈る場合もあります。
一般的には生花をイメージされる方が多いと思われますが、生花だけでなく造花による供花もあります。
供花にはいくつかの種類があり、葬儀で最も多く見られるのはスタンド花や籠花(かごはな)と呼ばれるスタイルです。
スタンド花や籠花は、プラスチック製の鉢などにオアシス(生花用吸水スポンジ)を用いて生花を活けたもので、スタンド(脚)を備えつけて飾ります。
その他、小さいカゴにアレンジメントした供花、花束による供花もあり、集まった供花を「組み込む」という形で花祭壇を設けるケースもあります。
なお、最近は見かけることが少なくなりましたが、花環(はなわ)も供花の一つです。花環については通常、造花で作られています。
供花に使われる花の種類は、信仰している宗教や宗派によって異なるため事前に確認が必要です。
仏教の場合は菊・カーネーション・ユリ・蘭などの白がベースの花がよいでしょう。
つるや毒がある花、香りの強い花は仏式の供花に向かないので注意が必要です。ただし、樒はその毒性から魔除けや獣よけ、清めの意味を持つとして仏事に使用されます。また、とげのある花も敬遠される傾向がありますが、最近では故人が好きだったなどの理由でバラが使用されることもあります。
神式の場合は白菊・カーネーション・百合・カスミソウなどの白色のお花にしましょう。
キリスト教の場合はカーネーション・百合・胡蝶蘭などの白やピンクなどの明るい色のお花を贈ることもできます。
家族葬での供花の役割
供花の役割は主に二つあります。
一つは、祭壇の周囲や式場に花を飾って故人を弔うためです。
仏式の場合では、特に花を飾ることを大事にしていて、香を焚く香炉、ろうそくを灯す燭台、そして花を飾るための花立ては、故人を供養するために必要な三つの道具(三具足)とされています。
また、お釈迦様が亡くなるときにそのそばで満開の花が咲いたといわれていることから、「その様子を再現して祭壇花や供花を飾り故人の冥福を祈る」という説もあります。
式場に飾った供花は祭壇花とともに、出棺前の故人との最期のお別れの際にお棺の中に納める「お別れ花」として使用することもあります。
もう一つの役割は、故人に対する弔意と遺族に対する慰めの気持ちを示すことです。
参列できない場合や香典を辞退されている場合など、それらの代わりとして供花を贈ることもあります。
家族葬で供花を贈ってもよいかは遺族の意向次第
家族葬では香典や弔問を辞退する方が多く、同様に供花も辞退される場合があります。
遺族が供花辞退の意志表示しているのであれば、供花は贈らないことがマナーです。
供花辞退となっているか意向が分からないときは、遺族に問い合わせる、葬儀会場に問い合わせる、訃報が書面であれば記載内容を確認するなどして把握します。
葬儀に招待されていない場合は、遺族にとって負担になってしまう場合もあるので供花を贈るのは避けた方がよいでしょう。
供花の手配方法、贈り先、タイミングについて
供花に関する遺族の意向が確認できたら、具体的にはどのように供花を手配すればよいのでしょうか。
ここでは、初めて手配する方でも困ることがないよう供花の手配方法などについて紹介します。
供花の手配方法
供花の注文は葬儀社や生花店を通して行えますが、注文先を決める際は、まず家族葬の施行を担当している葬儀社に供花の手配について確認しましょう(葬儀社が不明な場合は葬儀会場や遺族に確認します)。
これは、葬儀社によって他の葬儀社や生花店からの供花持込みを禁止している場合があるためです。
また、家族葬を施行する葬儀社は、宗教宗派や遺族の意向に合わせた供花を用意していたり、祭壇の装飾花と統一感を出すために供花の種類を指定して受け付けていたりすることが考えられるため、別途注文してしまうと統一性が損なわれる可能性があるのも理由として挙げられます。
なお、遺族や親族分の供花は喪主が取りまとめて葬儀社に手配をするケースがあります。
もし、遺族や親族の立場で供花を出したいと考えている場合は、まず喪主(また実際に葬儀を取り仕切っている家族の方など)に供花の手配について確認をした方がよいでしょう。
自分で供花を手配する場合には次の手順で行います。
- 葬儀社や生花店に電話をして供花を送りたい旨を伝えます。
- 電話で供花の贈り先(喪家名、葬儀日時、葬儀会場名や住所)を伝えます。供花の値段、供花の名札に記載する名前、供花代金の精算方法について確認を行います。名札に記載する名前の文字に誤りが生じないよう、電話のあとFAXの送信を求められる場合もあります。FAXを使わない場合は電話のみでの注文になるため、漢字の誤りなど札名の間違いがないように入念な確認が必要です。
供花の値段は、一番多く見られるスタンド花や籠花で、約1万2000円~2万円程度が相場と言われています。
最近の葬儀社や生花店では、インターネットからの注文に対応しているところもあります。
インターネットでの注文の場合、併せて手配できる場合もあり、別々で注文するよりも手間が省けるのでお勧めです。
インターネットでの注文の際も、喪家名、葬儀日時、葬儀会場名を間違いなく入力するようにしましょう。
供花の贈り先
供花の贈り先は基本的に家族葬が行われる会場です。
葬祭ホールが会場となるのであれば、葬祭ホールが送り先となりますし、自宅で家族葬が行われるのであれば自宅が贈り先となります。
供花を贈る際は、宛名を喪主名にするのがマナーです。喪主名が不明な場合は、宛名を「〇〇家様」や「〇〇家ご遺族様」として贈るようにします。
故人の名前を宛名にしないように注意しましょう。
供花を贈るタイミング
供花は原則、通夜の開式前までに葬儀会場に届くように手配します。遅くとも通夜の翌日に行われる葬儀告別式の開式前までに届かなければなりません。
ただし、開式直前に新たな供花が届くようなことがあると、遺族に慌ただしい思いをさせてしまいます。供花の手配は基本的に、通夜日の前日までに行うようにしましょう。
通常は、注文を受けた葬儀社や生花店が適切なタイミングで家族葬の会場に供花を届け、飾り付けるところまで対応してくれます。



家族葬で会社から供花を贈る場合の注意点
取引先の関係者や、会社の従業員の身内で不幸が発生し、家族葬が行われる場合において、会社として供花を送るケースも考えられます。
家族葬へ会社として供花を贈る場合には、次の点が注意しておきたいポイントです。
供花を辞退されていないか確認する
供花の手配をする前に、供花を辞退していないかの遺族の意向を確認する必要があります。
もし遺族が供花辞退の意向であれば、無理に贈ることはかえって失礼に当たります。供花辞退の意向が示されていないときにだけ供花の手配をするようにします。
また、辞退しているのに無理に贈ると遺族の負担にもなるので注意しましょう。
その他、家族葬では香典や弔電についても辞退としている場合がありますので、供花に関する意向と合わせて、辞退していないかを確認をしておくとよいでしょう。
供花を贈る際の名札の記載
家族葬の会場では、供花を出した人の名前が名札に表記されることになります。
名札に記す名前は誰が供花代を負担したかによって書き方が異なります。
会社負担の場合、名札には「会社名のみ」または「会社名+代表者名」で記載するケースが多く見られます。その他社員で出し合った場合「〇〇会社 社員一同」や「〇〇会社 ▲▲課一同」というような名前を名札に記載することもあります。
また贈ってもよい供花の種類やサイズ、宗教や宗派を葬儀会場に問い合わせて確認しておくことも大切です。
最後に
今回は家族葬における供花のマナーや贈り方などについて紹介しました。
家族葬では「供花辞退」としているケースが珍しくありません。
供花を贈りたいと考える場合には、まず対象の家族葬が供花辞退となっていないかどうかの確認をすることが大事です。
供花辞退となっていないことを確認できたら、葬儀社や生花店に供花の手配を行う手順となります。
訃報を受け家族葬で行われることを知り、供花を贈ろうかと考えた場合などで今回の内容を参考にしてください。



花籠をお届け致します。
こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より
提供しております。
葬儀の費用を抑えるためのポイント
「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。
「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」
「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」
「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」
そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。
関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...
続きを読む
安心葬儀 ご利用の流れ
-
ステップ1
お客様センターまでお電話ください
安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。
-
ステップ2
ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介
お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
-
ステップ3
葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定
葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。
※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
- 急いで葬儀社を手配したい
- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい
- 葬儀の費用相場を知りたい
- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。
安心葬儀おすすめプラン
安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。
\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /
葬儀のご相談はこちら
\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /
依頼・見積り通話
無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。